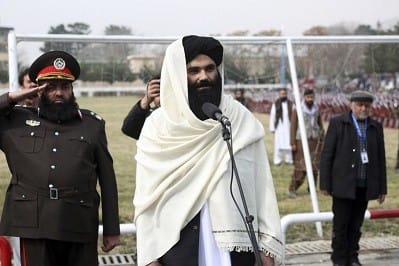(アジア開発銀行が発表した2023年の経済成長率の見通しは、ベトナムは6.5%と東南アジアの主要国の中で最も高くなっています。【4月7日 NHK】)
【22年GDP成長率、過去10年間で最高の8%超 中国からの生産移転先としての優位性】
ベトナムは日本にとって、進出企業・在住日本人も多く、また、日本で働くベトナム人も40万人超えて最多・・・・というように非常に関係の深い国となっています。
ベトナム経済は成長著しく、「人口が間もなく1億人を突破して、世界で15番目の人口1億超えの国となり、昨年のGDP成長率は8%超だ」(中国メディアの毎日経済新聞)と、“明るい未来”が期待されています。
****ベトナム、人口が間もなく1億人突破、昨年のGDP成長率8%超―中国メディア****
中国メディアの毎日経済新聞は11日、東南アジアのベトナムについて「人口が間もなく1億人を突破して、世界で15番目の人口1億超えの国となり、昨年のGDP成長率は8%超だ」とする記事を掲載した。
記事によると、ベトナムの人口は昨年4月1日時点で9920万人。今年4月には1億人を突破する見込みで、世界で15番目、東南アジアでは3番目の人口1億超えの国となる。
ベトナムの昨年の実質経済成長率は前年比8.02%で、政府による目標の6〜6.5%を上回り、1997年以来の高い伸びとなっただけでなく、過去10年間で最高の数字となった。
ベトナム中央経済管理研究所(CIEM)のチャン・ティ・ホン・ミン所長は「2022年はベトナムと世界経済にとって非常に困難な1年だったが、政府各当局の努力の結果、GDP成長率は国会で承認された数値を大きく上回り、インフレ率は3.15%に抑制された」と述べた。
一方で、今年は、世界的なインフレ圧力や各国中央銀行による金融引き締め傾向、主要な貿易相手国の景気減速、グローバルなバリューチェーンの継続的な中断などの外部リスクに加え、高インフレや金融不安などの内部リスクに直面することになる。
世界銀行の専門家は「ベトナムは、1人当たりGDPが過去30年間で5倍になり、2045年の高所得国入りを目指している。中所得国のわなに陥るのを避けたいなら、一連の制度改革を推進しなければならない。そうして初めて、世界と国内における新しく複雑な課題に対処する能力を伸ばすことができる」と指摘する。【3月13日 レコードチャイナ】
**********************
投資先としてベトナムが注目されたのは、米中対立の激化や中国国内の政治的動向などから中国へ投資を集中させることの危険性「チャイナ・リスク」の回避策として、中国からの生産移転先としてベトナムが選択された経緯があります。
****チャイナ・プラスワンで優位に立つベトナム****
コロナ禍でもベトナムは他のASEAN諸国とは対照的にプラス成長を維持した。低賃金、中国との近接性、積極的な貿易協定等の締結、が中国からの生産移転先としての優位性を高めたことが大きな要因である。
新型コロナ禍でもプラス成長を維持
(中略)こうした需要面の動きに加え、近年の米中対立の激化を受け企業が中国から生産拠点を移し、これら需要増に対応できる生産能力がベトナムで高まっていたという、供給サイドの要因も指摘できよう。
新型コロナ禍でもプラス成長を維持
(中略)こうした需要面の動きに加え、近年の米中対立の激化を受け企業が中国から生産拠点を移し、これら需要増に対応できる生産能力がベトナムで高まっていたという、供給サイドの要因も指摘できよう。
これは、海外拠点を中国へ集中させることによるリスクを回避し、中国以外の国・地域へも分散して投資する経営戦略である「チャイナ・プラスワン」によって中国依存度の低下が図られるなか、ベトナムが生産移転先の最有力国となっていることを象徴する動きでもある。
ベトナムに生産拠点移転が進む三つの要因
もっとも、ベトナムのビジネス環境は他のASEAN諸国と比べ大幅な改善はみられない。(中略)ビジネス環境がそれほど整備されているとはいえないにも関わらず、企業が中国からの生産移転先としてベトナムを選ぶ要因として以下の3点がある。
1点目が安価な労働力である。
ベトナムに生産拠点移転が進む三つの要因
もっとも、ベトナムのビジネス環境は他のASEAN諸国と比べ大幅な改善はみられない。(中略)ビジネス環境がそれほど整備されているとはいえないにも関わらず、企業が中国からの生産移転先としてベトナムを選ぶ要因として以下の3点がある。
1点目が安価な労働力である。
(中略)賃金水準はマレーシアとタイの55%、インドネシアの75%であり、同程度のフィリピンと並んで労働コストの面で高い競争力を持っている。
2点目が中国との近接性である。
2点目が中国との近接性である。
(中略)中国で事業を拡大した企業は中国外への生産移管を考える場合も、原材料や部品の中国依存を大きく変えられないことが多い。この点において、北部で中国と国境を接し、陸路での輸送が可能であることがベトナムの優位性となっている。(中略)
3点目が貿易協定等の締結による輸出環境の整備である。
ベトナムは国際経済統合という国是のもと積極的なFTA(自由貿易協定)戦略を展開しており、(中略)企業は他のASEAN諸国に立地した場合、FTAを活用できる市場は世界輸入の約3割であるが、ベトナムに立地することで世界の輸入市場の65%に競争的な条件でアクセスできる。
今後の成長には産業構造の高付加価値化が必要
以上のように、①低賃金、②中国との近接性、③積極的な貿易協定等の締結、という要因が、ベトナムの生産移転先としての優位性を高め、足元での急速な経済回復につながったと言える。
今後の成長には産業構造の高付加価値化が必要
以上のように、①低賃金、②中国との近接性、③積極的な貿易協定等の締結、という要因が、ベトナムの生産移転先としての優位性を高め、足元での急速な経済回復につながったと言える。
米国での政権交代後も米中対立が緩和する可能性は低いうえ、新型コロナ感染拡大初期の中国での物流停止などを受け、中国依存の低下を図る動きはさらに強まっている。こうした優位性は当面変わらないとみられるなか、ベトナムは輸出をけん引役に堅調な成長を続ける可能性が高い。
しかし、現状のベトナムは「チャイナ・プラスワン」での成長、つまり中国の「低付加価値分野での下請け的な存在」に過ぎないとも言える。(中略)
しかし、現状のベトナムは「チャイナ・プラスワン」での成長、つまり中国の「低付加価値分野での下請け的な存在」に過ぎないとも言える。(中略)
今後、より賃金の低いカンボジアやラオス、ミャンマーが低付加価値産業の受け入れを拡大させてくることになれば、ベトナムはその地位を維持することが難しくなる可能性がある。
ベトナムが中長期的においても安定的な経済発展を遂げるには、将来的に中国の下請け的な存在から脱し、低付加価値産業の受け入れだけでなく、より高付加価値な産業の育成を強化していくことが求められる。(後略)【2021年01月28日 塚田雄太氏 日本総研】
ベトナムが中長期的においても安定的な経済発展を遂げるには、将来的に中国の下請け的な存在から脱し、低付加価値産業の受け入れだけでなく、より高付加価値な産業の育成を強化していくことが求められる。(後略)【2021年01月28日 塚田雄太氏 日本総研】
*****************
日本や欧米の企業だけでなく、米中対立の影響を避けたいのは中国企業も同じで、取引関係にある企業がすでにベトナムに生産拠点を有しているということもあって、中国企業のベトナム進出も盛んなようです。
****中国企業のベトナム投資活発化、米中摩擦の回避狙う****
中国が昨年12月、新型コロナウイルスの感染を徹底的に封じ込める「ゼロコロナ」政策を解除して以来、同国からベトナムへの企業投資が急増している。
見えてくるのは、既にベトナムに進出している中国や世界各国の大手メーカーと取引関係がある中国のサプライヤーが、米中貿易摩擦の影響を回避するためにベトナムに拠点を設けるという構図だ。(中略)
背景には、米政府がハイテク関連製品の中国向け輸出規制をじわじわと強化していることや、米中双方が互いに報復関税を発動する展開の中で、中国にいては商売がしにくいという事情がある。さらに中国の人件費高騰も背中を押す要因だ。(中略)
<歴史的な対立>
中国企業のベトナム進出にはリスクもある。両国は血で血を洗う戦いを繰り返してきた歴史があり、今も南シナ海の領有権を巡る対立は消えていない。そうした中でベトナム国民の反中感情の高まりから、2014年には中国への大規模な抗議デモの一部参加者が暴徒化し、中国企業を襲う事件もあった。
ベトナムでは中国企業からの投資申請は特に注意深く審査される傾向があり、あるコンサルタントによると、従業員の労働ビザや労働許可の取得にもより長い時間がかかる。
それでも中国のサプライヤーがベトナムにやってくる流れは止められない。BWインダストリアル・デベロップメントのチャン氏は「中国企業の大半は、先にベトナムに移動した顧客のために進出してきている」と指摘した。【3月18日 ロイター】
*******************
上記のような有利な環境にあるベトナム経済ですが、持続可能な成長のためには、経済における改革はもちろん、経済を取り巻く環境の整備も必要とされています。
****成長力は突出のベトナム 環境悪化で持続可能性に課題****
ベトナムは、“超人気国”だ。新型コロナウイルス禍もマイナス成長を経験せず、国際通貨基金(IMF)による経済成長予測は2023年が6.2%、24年は6.6%、今後5年平均も6%を超え、東南アジア諸国連合(ASEAN)でも突出する。
人口も間もなく1億人に達するなど魅力的条件がそろい、直接投資も右肩上がりだ。そのせいか筆者はハノイ在住だが、誰もが今日より明日が良くなると信じており、前向きで明るい気持ちをもらえる。
もちろん良い点ばかりではなく、直近の不動産市場の急落や改正消防法による建設着工の遅れ、昨今判明したコロナ禍での汚職による一連の政府幹部更迭のあおりを受け、今年と来年の成長率や直接投資は下振れする可能性もある。
一方で、1党支配体制をとる共産党と国民の信頼関係は約束された経済成長の上で成り立ち、党が極端な中国重視の政策に偏らない限り、今後5年程度は内需を目的とした投資も堅調だろう。
日本とベトナムの関係も良好だ。両国は今年で外交関係樹立50周年を迎えるが、ベトナムに進出する企業の数は約2000社、在住日本人も2万人に上る。また、日本で働くベトナム人の数も40万人を超え、中国を抜いて世界最多となった。両国首脳は毎年のようにお互いを訪れ、旅行客も後を絶たない。日本がこれまでに緊密な関係を築けている国は、世界を見渡しても他にはないのではないか。
一方で国際社会は、この東南アジアの人気国に対しても「持続可能な」成長を求める。この観点で、ベトナムには潜在リスクが多く存在する。例えばハノイの大気汚染は世界最悪の水準で、ゴミ問題や交通渋滞も年々悪化、都市と地方の医療格差や少子高齢化といった課題も山積している。(後略)【4月3日 緒方亮介氏 エコノミスト Online】
*********************
なお、足元の経済状況は「減速」と芳しくないようです。
****ベトナム経済が急減速****
連続利下げ 輸出・不動産不振
ベトナム経済が急減速している。強みの電子機器輸出が振るわず、不動産市況の低迷が鉄鋼業など幅広い産業に波及。1~3月期の国内総生産(GDP)が市場予想を大きく下回り、政府・中央銀行は連続利下げで景気の下支えに躍起だ。政府が掲げるGDPの年6.5%成長の目標達成は難しいとの見方が大勢だ。(後略)【4月10日 日経】
**********************
【汚職スキャンダルが相次ぎ、国家主席が任期途中で引責辞職】
一方、国内政治の分野ではコロナ禍のもとで汚職スキャンダルが相次ぎ、1月17日にはフック国家主席が責任を取り任期途中で辞職するという異例の事態に。
汚職スキャンダルの一つは、国内の検査キット製造会社が価格を水増しして納入し、計約8千億ドン(約44億円)の賄賂を納入先幹部らに支払っていたとされる2022年の事件で、元保健相や元科学技術相ら100人以上が逮捕されました。
もう一つは、コロナ禍で通常フライトが運休となった状況で、在外ベトナム人の帰国のための特別帰国便をめぐる事件です。認可を希望する運航会社が政府関係者らに約1700億ドン(約9億円)の賄賂を渡し、その負担は乗客の料金に転嫁していたとされ、前駐日大使や旅行会社の幹部ら約40人が逮捕されました。
汚職の蔓延が常々指摘されるベトナムにあって、汚職追放を掲げる最高指導者チョン共産党書記長の反汚職キャンペーンの一環で、それなりの効果をあげてはいますが、官僚が萎縮するなどの副作用も。このあたりは、中国・習近平国家主席が権力闘争手段として行った反汚職キャンペーンと類似しています。
(チョン共産党書記長が21年の党大会で党規約の規定を超えて異例の3期目に入り、権力集中を進めているあたりも習近平主席とよく似ています)
****国家主席辞任にまで至ったベトナムの反汚職運動 今後の行方は?****
英エコノミスト誌1月28日号は「反汚職でベトナム大統領辞任」との解説記事を掲げ、コロナを巡る汚職摘発の動きを説明、反汚職キャンペーンはそれなりに成功しているが、役人の責任回避で経済に悪影響を与えつつあると論じている。要旨は以下の通り。
ベトナム政府は、コロナ禍の国境閉鎖で海外に取り残されたベトナム人のチャーター機による帰還に関する大使館員の汚職を巡り、役人逮捕を始め、複数大臣を含む数十人を起訴。1月17日にはフック国家主席が責任を取り辞職した。
ベトナムで汚職は珍しくないが、国家主席辞任は稀だ。フック氏の辞職は、最高指導者チョン共産党書記長の10年に渡る看板政策の「反汚職」が大きく進んだことを示している。
習近平と同様、チョンは自身と共産党への権力集中のため汚職撲滅を使ってきた。解任された高官のほとんどが政府で昇進してきた者で、結果、党は政府に対しますます優勢になった。
取り締まりは改革努力の一環でもある。78歳のチョン書記長は5年任期の三期目で、対米戦争を成人で経験した最後の世代だ。90年代の市場経済導入以降広がった汚職を追放したいと考えている。
コロナ禍での汚職は挑発的なことだ。2021年12月に医療機器会社CEOが自社のコロナ検査機器購入の為の贈賄容疑で起訴され、保健大臣、科学技術大臣を含む役人が共謀の疑いで逮捕。大使館職員は帰国便便宜で処罰され、4月には副外相逮捕。1月5日には副首相2人失職。うち一人は将来の首相候補の外務大臣だ。
反汚職キャンペーンは、それなりに成功してきた。汚職ランキングでベトナムは世界111位から87位に改善した。(中略)
経済に複雑な影響もある。賄賂を取れない腐敗官僚は投資プロジェクト実施に無関心となり、汚職を嫌う実直な官僚はプロジェクトの認可さえしない。結果、資本投資の支出割合は2011〜14年の70%から2019年に50%に低下。コロナ後反転したものの、昨年は58%に低下した。
官僚はあらゆる形の関与を恐れている。徴税も停滞し、高速道路や地下鉄などの重要インフラプロジェクトも遅延している。(後略)【2月21日 WEDGE】
*******************
なお、後任国家主席にはチョン共産党書記長の側近とされる若手、ボー・バン・トゥオン共産党書記局常務(52)が選ばれています。
トゥオン氏は「クリーンな人物」ということで、チョン共産党書記長が自らの引退後の体制づくりを進めているとの評価も。
なお、ベトナムは中国同様に、表現、結社、平和的集会、そして宗教と信仰の自由を含む基本的な市民的及び政治的権利を厳しく抑制し続けています。
【常に意識される「大国」中国との距離感 ベトナムと関係強化したいアメリカ 微妙なバランス】
外交面では「全方位外交」が基本姿勢ですが、特に問題となるのがその隣の「大国」中国との距離感。
南シナ海・南沙諸島の領有権をめぐっては中国と厳しく対立するベトナムですが、中国に接する地理的条件、これまでも戦火を交えた歴史的経緯もあって、過度に中国を刺激するのは避けたいところ。昨年10月にはチョン共産党書記長が訪中し習近平国家主席と会談、共に社会主義を掲げる両国関係を固めることで一致しています。
習近平主席は、両国関係について「誰にも邪魔させない」と述べ、アメリカを暗に牽制も。
その中国を牽制する意味でも、また、最大の輸出市場という経済的意味でも、かつて「ベトナム戦争」を戦ったアメリカへの接近も目立ちます。
****米国務長官がベトナム初訪問、最高指導者らと会談****
ブリンケン米国務長官は15日、ベトナムの首都ハノイで同国最高指導者グエン・フー・チョン共産党書記長やファム・ミン・チン首相らと会談した。ブリンケン氏がベトナムを訪問したのは国務長官就任後初めて。
米国は中国に対抗するために東南アジア諸国との結びつきを強めることを目指しており、ブリンケン氏はベトナムに対しても二国間関係の強化を働きかけた。
ブリンケン氏は記者団に、両国の関係において重要な要素は安全保障で、米政府がベトナムに3隻目の沿岸警備艇を供与する手続きの最終段階に入っている点を挙げて、この安全保障分野の協力は拡大していると指摘した。
またブリンケン氏は、二国間関係強化の正式な取り決めについても、数週間から数カ月以内に実現する可能性があるとの期待を示した。
ただ専門家の間からは、ベトナムが米国と連携をさらに強めるかどうか懐疑的な声も出ている。ベトナムとしては、米国と接近しすぎて中国を無用に刺激するのを避けたいからだ。【4月17日 ロイター】
米国は中国に対抗するために東南アジア諸国との結びつきを強めることを目指しており、ブリンケン氏はベトナムに対しても二国間関係の強化を働きかけた。
ブリンケン氏は記者団に、両国の関係において重要な要素は安全保障で、米政府がベトナムに3隻目の沿岸警備艇を供与する手続きの最終段階に入っている点を挙げて、この安全保障分野の協力は拡大していると指摘した。
またブリンケン氏は、二国間関係強化の正式な取り決めについても、数週間から数カ月以内に実現する可能性があるとの期待を示した。
ただ専門家の間からは、ベトナムが米国と連携をさらに強めるかどうか懐疑的な声も出ている。ベトナムとしては、米国と接近しすぎて中国を無用に刺激するのを避けたいからだ。【4月17日 ロイター】
*******************
中国を無用に刺激したくないのはアメリカも同じで、ブリンケン国務長官はこの日、報道陣の前で中国を直接名指しすることはなかったとのことです。
3月には最高権力者のチョン書記長がバイデン大統領と電話会談し、関係強化を協議しています。