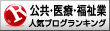「八州廻り 桑山十兵衛」と題して今TVされている(どうやら来週で終わるらしい)原作者佐藤雅美氏の著書「官僚 川路聖謨の生涯」を読んでいる。著者いわく最高の官僚とのこと。そうだと思う、なにしろ百姓身分から勘定奉行にまでなった人だから。
立身出世という面ではなく、それ以外、種々考えさせられる。
1つには時代は人を求める、そのときそのときで必要な人材を排出するような気がする。

海音寺潮五郎、司馬遼太郎、最近では藤沢周平が話題、なかなか佐藤氏は取り上げられないが、佐藤雅美氏の小説は幕末しかも経済面からのアプローチが多い。
幕末の対応を幕府側から見た小説でいままでの明治維新とは別の面が見える。勝海舟などは当時の幕閣をけなしているだけの話が伝わっているが、幕府は幕府でやはりそれなりの対応をしている事情をうかがわせる。

官僚として分を尽くす、気構えを持ってことに処す、職分をわきまえることが川路聖謨の生き方として描かれている。これだけであれば何という官僚でもない。しかし、時代なのだと思う、こうした人物が幕府の中心にいることで外交での舵取りが行えたのかと。

生き方として参考とはなる、とは読後感(半分しか読んでないが)。
立身出世という面ではなく、それ以外、種々考えさせられる。
1つには時代は人を求める、そのときそのときで必要な人材を排出するような気がする。

海音寺潮五郎、司馬遼太郎、最近では藤沢周平が話題、なかなか佐藤氏は取り上げられないが、佐藤雅美氏の小説は幕末しかも経済面からのアプローチが多い。
幕末の対応を幕府側から見た小説でいままでの明治維新とは別の面が見える。勝海舟などは当時の幕閣をけなしているだけの話が伝わっているが、幕府は幕府でやはりそれなりの対応をしている事情をうかがわせる。

官僚として分を尽くす、気構えを持ってことに処す、職分をわきまえることが川路聖謨の生き方として描かれている。これだけであれば何という官僚でもない。しかし、時代なのだと思う、こうした人物が幕府の中心にいることで外交での舵取りが行えたのかと。

生き方として参考とはなる、とは読後感(半分しか読んでないが)。