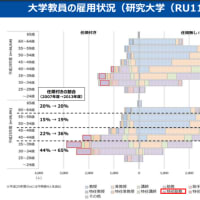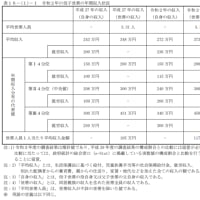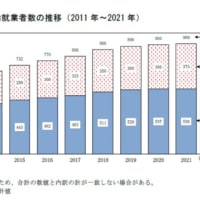「円高」が止まらない。
日に日に上がっている状態が続いている。
その理由などは、述べる必要もないだろう。
そして円高の勢いは、1ドル=50円説まで飛び出すほどだ。
その円高傾向を受け、朝日新聞の「WEBRONA」では、同志社大学大学院教授の浜矩子さんが「1ドル=50円になってもおかしくは無い。なぜなら、米ドルは既に基軸通貨ではなくなったのだから」という内容のコラムを掲載している。
浜先生の言いたいことは、判らないわけでは無い。
実際、様々なメディアが今回の円高に対しては「日本経済が好調で、円高となっているわけでは無い。アメリカやユーロ圏経済の行き詰まり感や経済不安が、円高を呼んでいるだけ」という内容を理由としている。
私が気になったのは、基軸通貨というコトなのだ。
何故「基軸通貨」というコトを気にするのか?といえば、商取引をする上で単純に対相手国通過で取引が出来ないからだ。
商取引をする上では、やはり「基準となるモノ」が必要だと感じているのだ。
例えば、経済が好調なインドやブラジルの通貨で直接商取引をする世界的企業が、どれだけあるだろう?
「金本位制」で取引を行うというのだろうか?
浜先生が上げていた「イギリス・ポンド」は、第一次世界大戦や第二次世界大戦など、欧州が戦火に巻き込まれたコトなどが要因で、その力を失ってしまったという経過があったと思う。
もちろん、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間にある「世界大恐慌」も忘れてはならないと思うが、「世界大恐慌」の発端は米国経済の破綻がキッカケだったと考えれば、当時の「金本制」の経済が含んでいる問題も明らかだと思うのだ。
とすれば、やはりグローバル経済といわれる中では、何らか「基軸通貨」となるモノが必要な気がする。
かの国の「元」というのは、考え難く、上述したインドやブラジルといった今現在好調な国々の通貨が「基軸通貨」となるとも考え難い。
とすれば、やはり米国ドルかユーロ、はたまた日本の円というコトになるのでは?
ただ、世界各国の中央銀行が集まり、独自の基軸通貨となる単位を決めることが出来れば、また違ったコトになるかもしれない。
そのために、一時的には経済の縮小が起きるとは思う。
というより、今までが「経済=拡大路線」という、思い込みがこのような事態を招いたのかもしれない。
それを見直す時期が来ている、と考える必要があるのかもしれない。
日に日に上がっている状態が続いている。
その理由などは、述べる必要もないだろう。
そして円高の勢いは、1ドル=50円説まで飛び出すほどだ。
その円高傾向を受け、朝日新聞の「WEBRONA」では、同志社大学大学院教授の浜矩子さんが「1ドル=50円になってもおかしくは無い。なぜなら、米ドルは既に基軸通貨ではなくなったのだから」という内容のコラムを掲載している。
浜先生の言いたいことは、判らないわけでは無い。
実際、様々なメディアが今回の円高に対しては「日本経済が好調で、円高となっているわけでは無い。アメリカやユーロ圏経済の行き詰まり感や経済不安が、円高を呼んでいるだけ」という内容を理由としている。
私が気になったのは、基軸通貨というコトなのだ。
何故「基軸通貨」というコトを気にするのか?といえば、商取引をする上で単純に対相手国通過で取引が出来ないからだ。
商取引をする上では、やはり「基準となるモノ」が必要だと感じているのだ。
例えば、経済が好調なインドやブラジルの通貨で直接商取引をする世界的企業が、どれだけあるだろう?
「金本位制」で取引を行うというのだろうか?
浜先生が上げていた「イギリス・ポンド」は、第一次世界大戦や第二次世界大戦など、欧州が戦火に巻き込まれたコトなどが要因で、その力を失ってしまったという経過があったと思う。
もちろん、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間にある「世界大恐慌」も忘れてはならないと思うが、「世界大恐慌」の発端は米国経済の破綻がキッカケだったと考えれば、当時の「金本制」の経済が含んでいる問題も明らかだと思うのだ。
とすれば、やはりグローバル経済といわれる中では、何らか「基軸通貨」となるモノが必要な気がする。
かの国の「元」というのは、考え難く、上述したインドやブラジルといった今現在好調な国々の通貨が「基軸通貨」となるとも考え難い。
とすれば、やはり米国ドルかユーロ、はたまた日本の円というコトになるのでは?
ただ、世界各国の中央銀行が集まり、独自の基軸通貨となる単位を決めることが出来れば、また違ったコトになるかもしれない。
そのために、一時的には経済の縮小が起きるとは思う。
というより、今までが「経済=拡大路線」という、思い込みがこのような事態を招いたのかもしれない。
それを見直す時期が来ている、と考える必要があるのかもしれない。