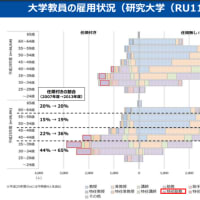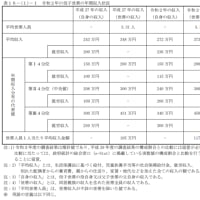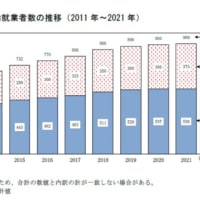早稲田大学の社会人向け講座のマーケティングを担当していた、吉野家の取締役員の舌禍はまだまだ尾を引いているようだ。
といっても、問題視されている内容は多岐にわたる。
例えば、この問題をSNSで投稿したのが、女性受講者であったという点。
投稿をした女性は、男性受講者の中にはこの話を聞いて笑いが起きていた、という指摘もしている。
逆に言えば、不快に感じたのは女性受講者であり、男性受講者は問題だと感じていなかった、ということになる。
実際の受講者がどのくらいの年齢が中心であったのかは不明だが、このような講座に積極的に参加したい!と考えるのは20代後半~40代くらいなのでは?と、想像している。
とすれば、問題にならなければ、笑った男性受講者も「問題点に気付かなかった」ということも十分に考えられる。
そんな中、以前拙ブログでもエントリをしたが「日本のマーケティング業界の問題」という指摘があった。
確かに、マーケティングという仕事をしていると、ドラッカーやコトラー、T・レビット等「マーケティングの神様」とか「マーケティングの父」と呼ばれるような方々の著書とは、随分違うと感じるコトは多々ある。
何より顕著な例は、「know-howやhow-to」ばかりを求めて、自社については?とか自分ならどうするのか?といった「成功例から考える」ということを半ば放棄し、「成功事例のknow-howやhow-toを提供して、売り上げがアップする」コトをマーケティング担当者の仕事だと思い込んでいる担当者が多いというのも事実だろう。
ただ、そのような傾向は、日本の様々な企業(特に古い体質の企業)に多くみられる。
「日本の減点主義」とか「リスクを負わない思考」等が根強いからだ、とも言われる理由でもある。
と同時に「マーケティング」そのものを「ビジネスの鵺」のように、見ているからではないだろうか?
そう考えると、ITMediaに掲載された記事も納得できるが、それはマーケティングに限ったことではないのでは?と、疑問を呈したいと思うのだ。
ITMedia:吉野家元常務の舌禍事件から考える マーケティング業界の病巣とシニア権力を持ち続けるリスク
確かに、今回の舌禍となったマーケティング担当者は、外資でマーケティングの担当者として、辣腕を振るってきた人物なのかもしれない。
当然、それなりのプライドを持って仕事をしてきたはずだ。
だが、消費財と食品とでは全く同じ思考で、マーケティングができるわけではない。
まして、もともと所属していた外資と違い、吉野家は築地で働く人たちに「安い・速い・美味い」を提供し、大きくなってきた企業だ。
同じ食品を扱う企業であっても、銀座に店を構えるレストラン等とは違う。
マーケティングの基本である、生活者を見ていないということでもあるのだ。
それだけではなく、企業におけるマーケティング担当者は、黒子のような存在でもある。
会社員時代、上司から「自分の企画で数字が出たら、営業の手柄だと思え。逆に数字が出なかったら、自分の失敗だと思え」といわれてきた。
マーケティングに携わる為に必要なコトは、おそらく「謙虚さ」なのだと思う。
ましてシニアと呼ばれる年齢になれば、メンターとして人財を育てる立場になる。
メンターがシャシャリ出てあれこれ、自慢話をしていては育てるべき人財も育たない。
マーケティングに限らず、どのような職種・業種であっても同じことではないだろうか?
そのような問題が一気に噴き出すこととなったのが、今回の「吉野家常務の舌禍」であり、日本の企業が抱えている問題ではないだろうか?
最新の画像[もっと見る]