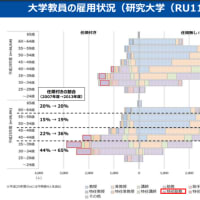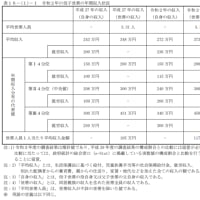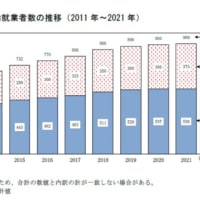テスラのE・マスク氏が、Twitterを買収した、というニュースが報じられている。
Huffpost:世界一の富豪イーロン・マスクがTwitterを5.6兆円で買収。青い鳥を手に入れる
E・マスク氏が、Twitterを買収するまでの経過については、すでにご存じのビジネスパーソンも多いと思う。
買収成立のニュースはある意味、意外な決着だったような印象があるほど、Twitter側はE・マスク氏の買収には乗る気ではなかったはずだ。
乗る気ではない、どころか反対の姿勢を示していたはずだ。
それが、急転直下のように買収が決まったのには、それなりの事情があるのだろう。
何より、この買収によりTwitter社が非上場になる、ということも、どうなのだろう?という疑念がある。
さて、そのようなTwitterではあるが、以前から指摘されている「若者と言葉」という視点で見ると、面白い関係性があるようだ。
最近、若者の間で「短歌」がブームになっている、ということをご存じだろうか?
今朝のFM番組を聞いていたら、特定の書店で142冊売れている歌集がある、と話題になっていた。
その「歌集」というのが、岡田真帆さんの「水上バス浅草行き」という歌集なのだという。
私の世代で、大ヒットした歌集といえば俵万智さんの「サラダ記念日」だと思うのだが、この時と今の短歌ブームとの違いは、自分で短歌を作る若い世代が多いという点だという。
もちろん、年齢の高い方の中には、趣味として長い間新聞などの短歌欄に投稿をしてきている、という方も少なくないだろう。
今の若い世代の「短歌」は、日常の風景を切り取り、自分のことばで書いている、ということらしい。
ありきたりな日常風景といっても、自分の生活の中にある言葉を短歌として書くことで、より共感性を呼ぶということのようなのだ。
そのような背景を見ていると、フッと気づくのが、今日買収の話題があったTwitterだ。
Twitterそのものは全角で140字という、文字制限がある。
その文字制限の中で、自分の思っているコトを書くことは、短歌を作るのと似ているのかもしれない。
Twitterが社会的認知を得られ始めた時のように「〇〇なう」などの、実況型のつぶやきではなく、「自分の見ている風景を心情に置き換え、140文字で表現する」ということと「短歌を作る」ということが、似ているのかもしれない。
短歌といえば、与謝野晶子や正岡子規、北原白秋のような人たちを思い浮かべ、ハードルを勝手に高くしているのは中高齢者で、岡田真帆さんに代表されるような、20代の若い歌人たちが増えてきたのは、Twitterにつぶやくような感覚でその時々の風景から感じられる内省性を短歌を通して表現しているのが、今の若い世代なのかもしれない。
その点で、Twitterと短歌は親和性が高いのかもしれないし、何より漢字という文字文化によって表現がしやすいという背景も見逃せない、日本の文化なのだと思う。