
明日が父の祥月命日なのだが、都合で今日、東本願寺にお参りすることにした。数珠を忘れたことに途中で気づいたものの、取りに引き返す気になれなかった。父にはごめんしてもらおう。
父の通勤と私の通学の時間が一緒になる日が時々だがあって、話をしながら同じ電車に揺られていた。そうか、そんな日があったのだ。おおかたは父が喋っていた気がする。父や母の存在がなくなってから、家族として暮らした時間の少なさをつくづく実感するようになった。弟を含め、寿命をもらっているのかもしれない。父の最期を思いだしながら、健康でありたいとだけ願うのだった。


建仁寺の塔頭の庭に、矢島の傘寿を祝って結社の門弟たちで建てた歌碑があり、その歌の中に「惜身命(しゃくしんみょう)」の文字が見える。
『惜身命』(上田三四二)に収められた「惜身命」を読んだ。
「仏道の側に立つ限り、身命を惜しむことは迷いであり、煩悩にほかならない」
とされ、厳しく責めている。
歌を選択するとき矢島は関谷に、この文字を使うことはどうだろうかと尋ねた。
【矢島は若い弟子との再婚で得た第二の人生を大事に生きていた。毎日、毎夜、身を労り、心を労わって一日でも健やかな生をこの世につなぐことを、喜びともし、かみしめながら生きていた】
関谷はそれを理解するようになっていたから、今生の思い、「先生の真実が出ている」、と共感を述べた。
そして、別れがたき別れを思う凡夫の嘆きを声にして、その声がどこまで澄むかに賭けるのが詩歌というものだと思う。
30歳までは生きられないと予言された矢島の米寿の祝いに再度集まった。関谷も大患を癒された。
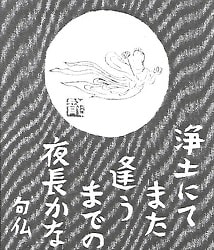
今日を生きていることが尊いのだ。
身命を惜しむ、いとおしむことは人間の持つまともな、あたりまえの心情と思う。
出会った一人ひとりの人間の運命に対する関谷の思いは、常に深く、篤い。そこに読んでいて救いがある。
(絵は黒田龍雄さんの版画)
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます