〈日本にはかつて、財産も戸籍も持たずに全国を渡り歩く漂泊民「サンカ」がいた。彼らの知らざれざる生活や精神性を探る〉、映画「山歌」の案内を新聞で読んだのが今月上旬だったろうか。
「漂泊民」「サンカ」について知らなかった。
映画、見てみようか。そう思って公開日20日を待ったが上映は一日1回10:00からのみ。これが微妙な時間で、せめてもう1時間遅くと願いたいのだ。ほなやめとけ!ということになる…。
今日、立ち寄り先の書店で背表紙を追っているとき「サンカ」という文字に目がとまった。『サンカの民と被差別の世界』五木寛之著。
こういう本があったのか!と少し驚きだった。映画の記事に触れていなければ生涯読む機会はないままで、映画とも縁なく終わったかもしれない。
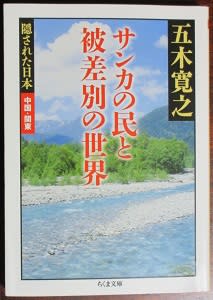
〈私は隠された歴史のひだをみなければ、“日本人のこころ”を考えたことにはならないと思っています。今回は「家船」漁民という海の漂泊民から「サンカ」という山の漂泊民へ、そして日本人とはなにかという問題まで踏み込むことになりました。それはこれまでに体験したことのなかった新しいことを知り、自分自身も興奮させられる旅でした。〉裏表紙に著者の言葉が記されていた。
映画、見てみようっと。

クワの実が色づきだしている。暑い一日だった。雷が鳴り始めた。激しい雨まで。
「漂泊民」「サンカ」について知らなかった。
映画、見てみようか。そう思って公開日20日を待ったが上映は一日1回10:00からのみ。これが微妙な時間で、せめてもう1時間遅くと願いたいのだ。ほなやめとけ!ということになる…。
今日、立ち寄り先の書店で背表紙を追っているとき「サンカ」という文字に目がとまった。『サンカの民と被差別の世界』五木寛之著。
こういう本があったのか!と少し驚きだった。映画の記事に触れていなければ生涯読む機会はないままで、映画とも縁なく終わったかもしれない。
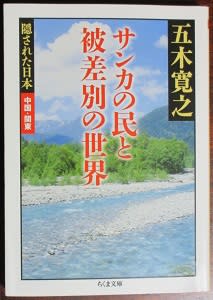
〈私は隠された歴史のひだをみなければ、“日本人のこころ”を考えたことにはならないと思っています。今回は「家船」漁民という海の漂泊民から「サンカ」という山の漂泊民へ、そして日本人とはなにかという問題まで踏み込むことになりました。それはこれまでに体験したことのなかった新しいことを知り、自分自身も興奮させられる旅でした。〉裏表紙に著者の言葉が記されていた。
映画、見てみようっと。

クワの実が色づきだしている。暑い一日だった。雷が鳴り始めた。激しい雨まで。
















「山窩」ですよね?
海の漂泊民は初めて知りました。
被差別と聞きますと部落民とかアイヌが
浮かびますが・・・
↓
糸遊>蜘蛛の子が糸に乗じて浮遊する現象とありましたが
よくわかりません。
俳句は言葉の「宝庫」ですね。
以前展覧会で見たのですが(名前忘れました)
高齢の女性日本画家が写生に行けなくなり
庭に張った蜘蛛の巣に霧吹きで吹き付け
描いていました。何点も。美しいでした。
今できることをするという姿勢にも感動しました。
瀬戸内海で暮らす様々な人々には、村上水軍が知られていますが、海賊、水軍、漁師、それ以外にも様々いて、
その中には陸に家を持たず船で暮らす「家船(えぶね)」という人々がいたそうです。
海の漂泊民となったのが家船漁民、とあります。
広島や瀬戸内海を訪ねるところから始まります。
律令以来の農耕文化、そこからくる定住民、非定住民。「土地」への執着?に触れられています。
アウトサイダー、「マージナル・マン」という呼び方にも…。
「糸遊」は春の季語で陽炎のことです。