今日の「光る君へ」が終わった後、藤原氏由緒の春日大社の紹介が出てきた。
ふと思い出したことがある。母がまだ存命のころだから22・23年ほど前だと思うが、春日大社から奉納のご案内を頂戴したことがある。
いまだに「何故」という気持ちがあるのだが、一応は苗字に「藤」がついている我家だが、これは2代目が母方の苗字を継いだからで、私は出自を藤原氏だとは思っていない。
しかし、さすがにそのまま放っておくわけにもいかず、母が幾ばくかの御寄附をしたようである。
母が春日大社に詣でたということもなく、私もいまだかって出かけたことはないから、思い当たることがない。
「藤」をつけた苗字の半分くらいは、明治維新後につけられたものだというが、春日大社に寄付をしたからと言って、我が家も藤原一族の詰めの端に入れていただいたことにはなるまい。
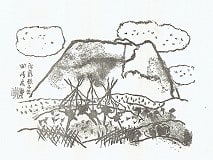
最近版画にチャレンジしたいという気持ちが沸々としているが、私の大好きな田崎廣助氏の作品集や随筆を見たり読んだりするうちに、
この「根子岳」と題するスケッチをお手本にしてみようかと思っている。
まずは線彫りをして、私が勝手に何色か色付を施してみるというのはどうだろうか。
私の田崎廣助LOVEは相当極まっていて、過日はある作品のオークションにも応札してみたが、相当の高値になり断念した。
ならば、八女市の「田崎廣助美術館」まで出かけて、本物を拝見しようと思ったりしている。
車で行けば老人の脚に負担もないが、免許証を返納した身としてはどうにもならない。
新幹線で羽犬塚までいって、TAXIで往復するかなどと、頭の中ではだんだん本気になってきている。
ある一文に、軽井沢の別荘が近所だという中曽根康弘と美術談義をしたとき、中曽根は「あなたの阿蘇の、灰色を基調としたあの色は
どうしたら出るのですか」と聞かれ、絵のわかる人だと感じたとある。
「あの色を出すために、阿蘇の前に何日座り続けたか・・・十日も二十日も山の周りをぐるぐるまわり・・・噴煙が見える日には幾日も
阿蘇の前にじ~っと座禅を組み座り続けた」と答えている。
山の画家と言われる画伯は、阿蘇に関する作品がいくつもあり、熊本人としては敬愛に値する人物である。
いまだ美術館も訪ねたことはないというのは、田崎廣助LOVEが極まっていない。5月くらいには出かけてみたいと思っている。
清源院とは細川重賢の同母妹で、宇土支藩興生に嫁いだ。興生が結婚生活10ヶ月、わずか21歳の若さで亡くなるが、弟・興周(おきちか)を急養子にたて相続せしめた。これが名君の誉れ高い興文(おきのり)である。
このように細川宗家と宇土支藩の間では婚姻によるつながりが深く、重賢の世子・治年には興文女・埴が正室として入っている。
さてこの治年が天明七年の参勤の際に長旅の疲れが病となり病床に就いた。病状が好転しない中、宇土支藩藩主・立禮は本藩重役・長岡主水(松井営之)から極内密の懇請を受けた。
義兄・治年にもしものことがあったときの為の継養子の話である。
細川宗家は綱利の男子が亡くなり、弟・利重の新田藩から利重の次男が綱利の継養子・宜紀が入ったことから新田藩の血が宜紀・宗孝・重賢・治年と四代続いており、立禮はこれを慮って固辞し続けた。
その際、立禮の祖母・清源院が「此義はいか躰にも御断は相立不申候」と強く説得し、ついに承諾するに及んだ。清源院の政治的才覚が細川宗家の危機回避に大きな力となった。
清源院もまた新田藩の血を受け継いだ人ではあるが、重賢公の妹として、また治年公の伯母として強力な助言であったろう。ここに細川宗家10代・斎茲が誕生することになる。
一方、宇土支藩は嫡子・立之がわずか4歳で相続することになる。
その後、斎茲の子斎樹に継嗣子がなく病床に就くと、宇土支藩・立之の嫡子・立政が本藩を相続し斎護となる。















