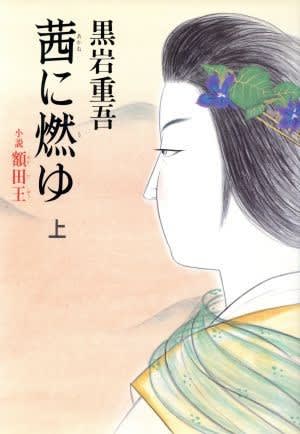行孝公御一代之覺
一、寛永十四丁丑三月四日戌ノ刻、於肥後國八代三ノ丸御誕生。御氏神妙見宮也。御若名宮松。帯刀、其後丹後守。御名乗行孝。
御母公慈廣院殿、元禄辛末六月十日御年八十三御逝去、末ノ年也。
御法名雲岸性浄。
一、御誕生之儀御妾腹故、三斎公御機嫌之程無御心許被思召、御穏便也。依之村上金左衛門江御預被成、御部屋迄参上仕候者、長
岡河内、佐方与左衛門、此両人迄折々御容躰奉伺候也。
一、同十六巳卯御歳之夏京都江御登り、其節村上金左衛門母子共ニ、御醫師永井良安御供仕候。従 立允公萩原兼連卿江御縁在之ニ
付、御預ケ被成候。(兼連卿ハ三斎公御甥也) 荻原殿御家来鈴鹿藤右衛門、同弟半之允御附被成候。河嶋八之允無程御奉公仕候。
一ヶ年程間有之、志水元英、御物よみの為被召出、おのつから御奉公人ニ罷成候。森権十郎御出入奉公之様ニ毎度参上相勤、
江戸へ御下り被遊候は、必可被召出旨御意被成、右之者共昼夜相勤申候也。人見丹蔵義其節御草履取ニ被召出、同前相勤、夫ニ
付江戸江御下り已後権左衛門、丹蔵義被召出候也。
(正保ニ年五月十一日、立允公逝去)
一、正保二乙酉閏五月十五日京都御發駕、同月廿五日江府江御着座被遊候。萩原殿ニハ七ケ年程被成御座候。御供仕候者、河嶋八之
允、志水元英、鈴鹿藤右衛門、其外末々迄都合拾壱人也。
一、御着之日堀田加賀守様御出、初而宮松様御逢被成候テ不大方御懇意也。其後 肥後守様ニモ御出逢被成候也。
一、同年八月十八日、立允公御遺物首尾能被献候也。其日、加賀守様江初而宮松様御出被成、殊之外之御馳走ニテ、御鞍置馬被進候。
尤右之趣肥後守様ヨリ 三斎公江御飛脚ヲ以被仰上候也。
(正保ニ年十二月月ニ日、三斎公逝去)
一、御目見之義肥後守様ヨリ御願被成候。翌(三)年戌ノ五月九日被達上聞候處、肥後守願之義候間、御序次第御目見可被仰付旨御
座候由、則肥後守様、宮松様江被仰進、其已後五月十五日井門文三郎、興津弥五右衛門江被仰渡は、宮松様御目見之義、三斎様
御遺言之御事御老中江被仰入候処、御目見之義ハ三斎様御存命之時ヨリ御願候御事ニ候や、御老中御談合之分ニテハ被仰出候事
難成様ニモ被思召候や、然は内上意迄為得候ハテハ不叶事之様ニ候や、左様之義ニテ御延引ト、是は肥後守様後推量ニテ御座候。
右之子細ニテ程延申トハ不存、何茂無心許可存ト被思召候ニ付、為安堵被仰聞候由、御直ニ両人之者ニ 御意被成候也。
一、同年六月十一日肥後守様ヨリ小笠原備前、田中左兵衛御使者被進、今度三斎様被仰置ニテ八代ヨリ差登せ候書付之通、御老中江被
懸御目、御口上ニテモ被仰入候は、内々肥後守様江被仰置タル儀ニテモ無之候。其上御墨付之在之被仰置ニテモ無之候。御側ニ居申
候者共江被仰置タル様子ニテ御座候。如何可仕候や。又八代ハ堺目之儀ニ付、宮松幼少之事ニ候条、八代ニハ家来長岡佐渡召置、宮
松儀は中務跡三万石を宇土ト申所ニ召置、如何可有御座候や、ト御談合被成候江は、下二テハ如何ト被思召候、然は 上意ニ、肥後
守内ヨリ三万石宮松江遣、所替之儀も奉得上意候分ニ可仕旨、酒井讃岐守殿、松平伊豆守殿、阿部豊後守殿、此衆ヲ以仰渡候。
御知行割之儀ハ肥後守様御帰国之上ニテ可被仰付との御事也。
一、正保三丙戌九月、肥後守光利公八代之諸士江同所於御城、長岡勘解由、庭亀之丞ヲ以被仰渡候趣ハ、右之通御跡滅申候付、御入も
多ク入不申候間、直ニ御奉公仕度ト存候輩、又御暇申上度ト存候輩、何も心次第ニ相極、書付上り申候。直ニ御奉公申上候者共之
子孫ニ尓今御当家江存之は此自分申候輩也。又御暇申上候諸士之分、別ニ望無之候ハ、先地ニテ光利公江可被召抱由ニ付、何も在難
由ニテ御奉公申上候、其内長岡河内、熊谷権太夫抔は存寄有之、他国江罷出候。此時志方半兵衛御暇申上候故、願之通御暇被下候
得共、不届之子細在之ニ付、行孝公ヨリ身上御構被成、熊本江被召出候事も不被為成、御扶持方被下一生埋レ罷在候也。
一、宮松様御名之義、肥後守様加州様ト御相談之上、戌ノ七月帯刀ト御改被成候也。
一、戌ノ七月廿九日御知行三万石、宇土益城両軍の内ニテ被進候旨、朝山修理、田中兵庫、興津作太夫方ヨリ佐方与左衛門方江、以
御帳引渡申候也。
一、同戌ノ八月四日両上様江帯刀様初而御目見被遊候。殊之外御首尾宜候由。御目見之節は前日阿部對馬守様ヨリ被仰渡候也。
一、右御目見之節 家光公公方様江御太刀一腰、御時服五ツ、家綱公大納言様江御太刀一腰、御時服三
ツ、御老中方江銀馬代、御時服ニツ宛被進候也。
一、慶安四辛卯四月廿日 大猷院様御他界ニ付、日光山江御参詣被成候也。
一、同年之冬上野并日光山御佛殿江石燈籠ニ基ツゝ被献候也。
一、同年十月中目黒野屋敷御求被成候也。
一、承應元壬辰八月十一日御入部、御十六歳、御半元服ニテ御下り被成、翌巳ノ年御参勤御元服也。
一、同ニ癸巳十二月廿八日御官位被仰付、御名丹後守様と御改。右ノ節御所司江ノ御奉書之写。
細川丹後守諸大夫被 仰付候間口
宣之儀傳奏衆江被申入相調候様尤候
恐々謹言
承應二年 阿部豊後守
十二月廿八日 信秋
松平伊豆守
信綱
酒井雅楽頭
忠清
板倉周防守殿
(以降の事績については記述なし)