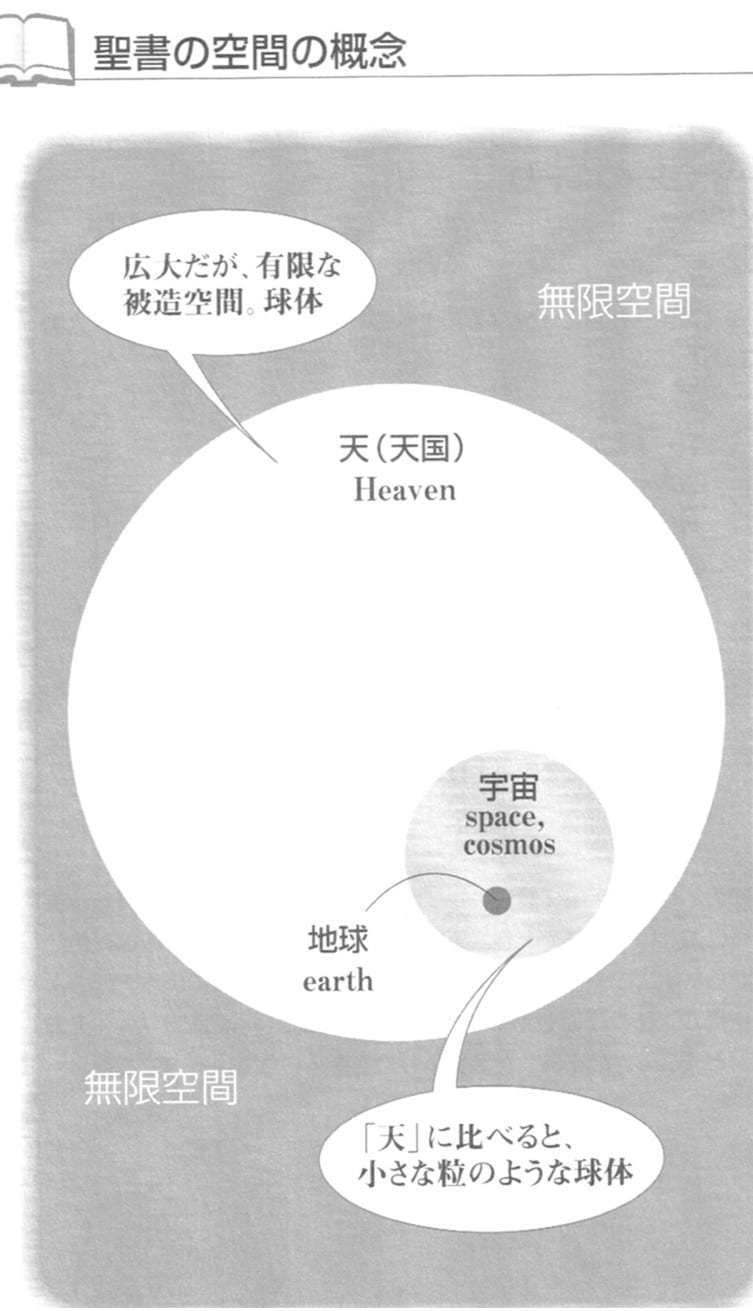エルサレムでのイエス宣教は、大衆には広がらなかった。
・・・前回そう述べたが、イエスの宣教は~それ以前のガリラヤ宣教の頃から~意外な結果を生み出していた。
富豪たちがイエスを支援し始めていたのである。
<福音書に名を残した男>
福音書には、アリマタヤのヨセフという名が登場する。
「ルカの福音書」によれば、彼はイスラエル政府の議員だったが、イエスの死後、ローマ総督ピラトにその死骸の引き取りを願いでている。
そして許可を得て十字架から死体を下ろし、処刑場近くにもっていた新しい墓にイエスを葬っている。
+++
その墓は、山肌を横方向にくりぬいてできたもので、大人が2~3人たって歩けるほどの空間をもった巨大なものであった。
入り口は大きな石の板をころがして閉じられるようになっていた。
イエスの遺体は、長い亜麻布で巻いて、中央の台に寝かされた。
そんな墓を使わずに所有しているというのは、かなりな富者でないとできない。
<最後の晩餐の会場と食事>
アリマタヤのヨセフ以外にも、イエスを支援した富豪の存在は推定できる。
「最後の晩餐」で有名な晩餐は、イエスが弟子と共に「過越の祭り」の夕食会場だった。
イエスは弟子に、「ある男について行くと、会場と共に過越の食事も備えられてるよ」と軽く言っている。
そんな会場を首都エルサレムの市街でイエスに提供してた人物は、やはり富豪のイエス支援者以外に考えられない。
<「マルコの部屋」は門前町の超一等地>
120人のイエス信徒が聖霊のバプテスマを受けた「マルコの部屋」もそうだ。
イエスは昇天する前に、弟子たちに「エルサレムに留まっていなさい」と言い残した。
その言葉通り、120人の信徒たちが一堂に会していたのがその部屋だ。
そこに聖霊が降臨する音を聞いて、神殿広場に来ていた参拝者が、部屋に殺到してきている。
+++
我々は『使徒行伝』におけるその記述を、何でもないことのように読んできているが、この事態も普通ではない。
エルサレム神殿広場で音を聞き、駆けつけられる距離にある土地は、神殿の門前にある超一等地だ。
そこで120人もの人が一堂に会して祈っておられた巨大な部屋は、普通の不動産ではない。
この部屋を弟子たちが持っていたはずもない。やはり、富豪のイエス支援者が提供していたのだ。
(続きます)