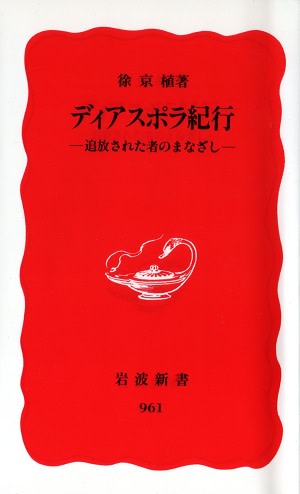ブラックセイントやソウルノートからLP・CDを出しているジャズマンの安価なボックスセットが最近いくつか出ていて、ヘンリー・スレッギルのものは(リマスターの文句に動揺したが)全部持っているのでパス、他にチャーリー・ヘイデンのものなんか欲しいと思っている。まずはセシル・テイラーの5枚組を入手した。どれも聴いたことがなかったのでこれは嬉しい。今日、この5枚を日がな聴いていた。

セシル・テイラーは強靭、超人である。構造にもセグメントにも恐ろしいほどの力が漲っている。どこかでセシル・テイラーがキース・ジャレットのことを坊や呼ばわりしていた記憶があるが、彼の前には誰でも坊やである。
ピアノソロは『Olim』(1986年)、ジミー・ライオンズの魂に捧げられている。最初に長尺のソロがあり、耳が釘付けになる。
マックス・ローチ(ドラムス)とのデュオ2枚組、『Historic Concert』(1979年)は、両者の個性がかち合っている。マックス・ローチも構造主義的といえばそう言えなくもない。2枚目にはふたりのインタヴューが収録されており、マックスはセシルのことを「Strong Force」、セシルはマックスのことを「elastic」などと評していて、確かにその通りなのだった。マックスの音がさまざまなパーカッションにより多彩になってきた後半、セシルは抒情的に攻める。
『Winged Serpent』(1984年)はメンバーが豪華で、エンリコ・ラヴァ+トマス・スタンコ(トランペット)、ジミー・ライオンズ(アルトサックス)、フランク・ライト+ジョン・チカイ(テナーサックス)、ギュンター・ハンペル(バリトンサックス、バスクラリネット)、ウィリアム・パーカー(ベース)など11人編成。4曲それぞれコンパクトにまとまってはいるが、チカイの詰まったような音やライトのでろでろと垂れ流す音など聴きどころが多い。
そして最も印象的だったのが、『Olu Iwa』(1986年)。これも『Olim』同様、86年に亡くなったジミー・ライオンズの記憶に捧げられている。1曲目はペーター・ブロッツマン(テナーサックス、タロガド)、フランク・ライト(テナーサックス)、アール・マッキンタイア(トロンボーン)、サーマン・バーカー(マリンバ)、ウィリアム・パーカー(ベース)、スティーヴ・マッコール(ドラムス)という凄い面々。最初はバーカーのマリンバが目立つ大人しめの演奏だが、次第に皆、構造的かつ野獣的に暴れはじめる。その中でのピアノとパーカーのベースの存在感が際立ちまくっている。2曲目はバーカー+ピアノトリオであり、シンプルな編成とは思えないカタルシスが得られる。
セシル・テイラーはいつだって素晴らしい。

セシル・テイラーとトニー・オクスレー、アントワープ(2004年) Leica M3, Summitar 50mm/f2.0, スペリア1600
○イマジン・ザ・サウンド(セシル・テイラーの映像)