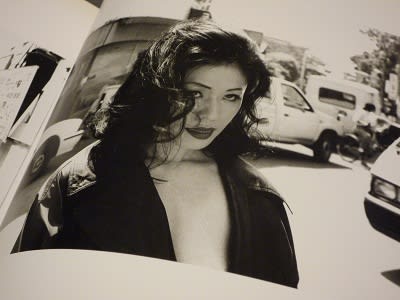LP棚を見ていると、デイヴ・リーブマン『Lookout Farm』(ECM、1974年)があった。こんなの持っていたっけ、全然意識していなかった(笑)。
折角なので久しぶりに聴く。ジョン・アバークロンビーのギターもリッチー・バイラークのエレピもいい感じである。スパニッシュ・コードもある。時代を感じさせる混沌としたサウンドの中、リーブマンはソプラノサックス、テナーサックス、フルートを吹く。マイケル・ブレッカーにもあるような、コードからアウトしてとにかく器楽的に吹きまくるこういうの、何て言うんだろう。最初は面白いんだけど・・・。
ライナーノートで油井正一が解説を書いている。曰く、このような奏法はスティーヴ・グロスマンにも共通していて、どっちがどっちかわからない。しかし、ジャズは個性の音楽であるから、こちらの身体と耳が慣れてくれば、それぞれを認識できるであろう、それが時代というものであろう、と。グロスマンとリーブマンは明らかに違うと思うが、自信があるからこその解説であり、他のジャズ評論家と違って古びない。

ついでに思い出して、ジョージ・ガゾーンがピアノレス・トリオ「The Fringe」名義で発表した『Live in Israel』(Soul Note、1995年録音)を聴く。もうこれは、いろいろなサウンドで彩っていないだけに、器楽のアスリートそのものである。機械ではない、機械にはこんなことはできない。しかし圧倒されはしても、全く、情も味もない。オリジナル曲の中に、1曲だけのスタンダード「Body and Soul」が演奏されているが、歌詞の世界とは無縁である。
いつだったかにガゾーンにサインを貰いつつ訊ねてみたら、この盤がもっともお気に入りだとのこと。「紅海ジャズ・フェスティヴァル」での録音であり、まあジャズフェスで聴いたなら呑みこまれて熱狂するかもしれないが。