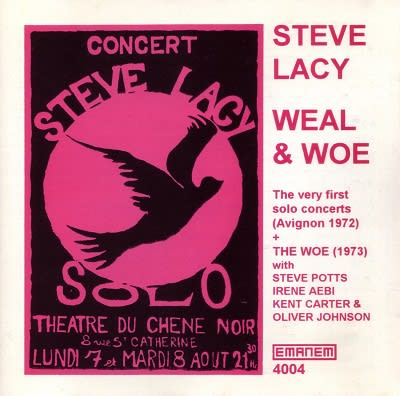と、いうタイトルのDVDを、出演もしている川下直広氏のヤフオクで買ったはいいものの、観ようと思ったら行方不明になっており、しばらく探索してようやく発見したという2014年。満を持して2時間鑑賞。

川下直広 (ss, ts)
近藤直司 (ts)
吉田哲治 (tp)
不破大輔 (b)
のなか悟空 (ds)
松原隆一郎 (司会)
副島輝人 (プロデューサー)
小黒洋太 (撮影)
1988年12月5日、旧・ピットイン
5人のプレイヤーがひたすらにエネルギーを噴出、としか言いようのない演奏。のなか氏などは叩き続けながら、歯を喰いしばったり叫んだりさえしている。ほとんど大仁田厚である。塩辛のような川下氏のサックスも良い。押しまくる不破氏のベースももちろん良い。観ていると元気が出たような気がする。
暑苦しい(失礼)のはプレイヤーだけではなく、観客席からも阿鼻叫喚。何なんだ、旧ピットインはそんなところだったのか。(なおわたしは移転前のピットインには入ったことがなく、このライヴ当時は田舎の高校生で、そもそも知るわけがない。)
DVDに封入されたのなか氏の解説がとても愉快で、どういうわけか、裏面には1988年の詳細な年表が付いている。それによると、同年7-8月に、サン・ラ・アーケストラがピットインに出演、のなか氏は外で「自作の凱旋カーの上に立ち、長蛇の入店待ちの客に向かって、『サンラをキリストに例えるならば、俺は釈迦だ。釈迦はキリストの説法は聴かない』などとアジ演説をした」そうであり、不興を買ってピットインに出演などできないはずが、副島輝人氏の尽力によりライヴが実現したのだという。(といってもよくわからない。)
ライヴはのなか氏のアフリカ演奏旅行の直前に行われた。確か、アフリカでドラムスを叩いていたら、現地の子どもたちがいとも簡単に難しい技を習得してしまい、凹んだ、といった本人の手記をどこかで読んだ記憶があるが、録音などは残っていないのかな。