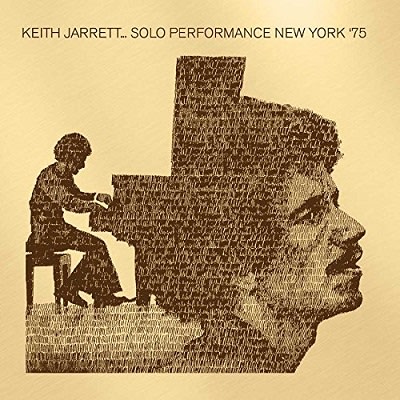NHKのETV特集として放送された『今よみがえるアイヌの言霊~100枚のレコードに込められた思い~』を観る(2016/12/17放送)。
北の先住民族・アイヌ民族は話し言葉であり、固有の文字を持たなかった。従って研究や伝承というものが重要になる。その一方で、NHKが戦後すぐに行ったアイヌ語の録音レコードが、最近になって発見されたという。確かにこれは大変な事件なのだろう。
聖地・二風谷(ニブタニ)のある平取(ビラトリ)町では、カムイ。人間の力を超える神の存在(それが人間ではこぼしてしまう汁を受けとめる食器であっても)を称える歌である。貝澤アレクアイヌが知里真志保(知里幸恵の弟)・金田一京助というふたりの言語学者をもてなして歌ったものだという。
釧路では、祭り歌たるウポポ。生きてゆくことを、自然からの収奪ではなく、自然との共存として位置づけたものである。手拍子を叩きながらフクロウの声を真似てみたりして、確かに、ウポポを取り入れて伝えているマレウレウのようだ(MAREWREW, IKABE & OKI@錦糸公園、マレウレウ『cikapuni』、『もっといて、ひっそりね。』)。
登別では、叙事詩ユーカラ。ここでは金成(カンナリ)マツという人物が、ユーカラを残さんとして、20年かけてその発音をノートに記録し、レコードに吹きこんでいる。ユーカラは何日もかけて歌うスケールの大きなものであり、大人の娯楽でもあったという。
旭川では、踊りにあわせて即興で歌うシノッチャ。ここでは、尾澤カンシャトクという人が、日本の悪政が戦争と郷土の荒廃をもたらしたのだと歌っている。
白老町では、トラブルが起きたときにお互いに言い分を歌いあうチャランケ。中野で毎年行われているチャランケ祭は、日本においてアイヌ民族、そして沖縄人が祭りを行うことの意味を示唆してのものだろうか。
いずれも歴史的な意義を思い知らされると同時に、残された声の力に感激してしまう。
番組では明治政府の植民地化政策を主に取り上げている(1869年の「北海道」命名、1899年の「旧土人保護法」、それらに基づく鮭・鹿などの狩猟制限と農業の押しつけ、同化政策、日本語の強制)。もっとも、日本政府(松前藩)による侵略は江戸期から顕著になってきており、1669年に蜂起したシャクシャインは騙し討ちにされている(このあたりの経緯については、新谷行『アイヌ民族抵抗史』や瀬川拓郎『アイヌ学入門』に詳しい)。琉球・沖縄とアイヌモシリ・北海道とを対比してみれば、ヤマトンチュ・和人の行為として、1609年の島津藩による琉球侵攻(上里隆史『琉日戦争一六〇九 島津氏の琉球侵攻』に詳しい)と松前藩の侵略とを、また明治政府の第二次琉球処分と開拓の本格化とを並置すべきものだろう。
ちょうどそれは、『帰ってきたウルトラマン』第33話の「怪獣使いと少年」において、アイヌの孤児と在日コリアンの老人を描いた沖縄人・上原正三氏の視線のように(上原正三『金城哲夫 ウルトラマン島唄』)。また、施政権返還前の沖縄に移住し、沖縄の絵を描き、「わが島の土となりしアイヌ兵士に捧ぐ」という作品さえも描いた宮良瑛子氏のように。岡和田晃氏と李恢成氏との応答において紹介される、アイヌ、朝鮮人、和人の関係を見つめた文学にもあたっていきたいと思う(植民地文化学会・フォーラム「内なる植民地(再び)」)。
さらには、アイヌ侵略が、一連のアジア侵略に伴う植民政策の事前検討のようになされているということも、重要な視点なのだろう(井上勝生『明治日本の植民地支配』)。竹内渉「知里真志保と創氏改名」によれば、アイヌに対する「創氏改名」政策は、実は朝鮮に対する適用前のトレーニングであった(『けーし風』読者の集い(14) 放射能汚染時代に向き合う)。支配中にも、アイヌに農業を押し付けたように、朝鮮でも東南アジアでも農業を強制し、大変な歪みと被害とをもたらしたのであった。
●参照
新谷行『アイヌ民族抵抗史』
瀬川拓郎『アイヌ学入門』
マレウレウ『cikapuni』、『もっといて、ひっそりね。』(2016年)
MAREWREW, IKABE & OKI@錦糸公園(2015年)
OKI DUB AINU BAND『UTARHYTHM』(2016年)
OKI meets 大城美佐子『北と南』(2012年)
植民地文化学会・フォーラム「内なる植民地(再び)」
新大久保のアイヌ料理店「ハルコロ」
上原善広『被差別のグルメ』
モンゴルの口琴