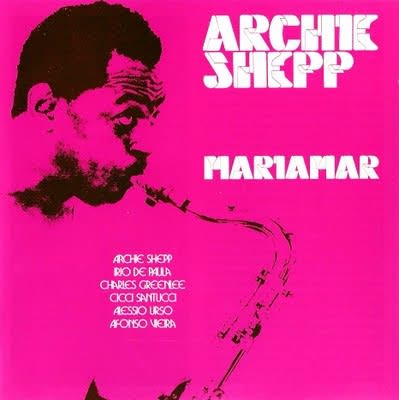『けーし風』第99号(2018.7、新沖縄フォーラム刊行会議)の読者会に参加した(2018/8/11、秋葉原/御茶ノ水レンタルスペース会議室)。参加者は5人+1人(懇親会)。

特集は「沖縄戦非体験者として伝える戦争」、「追悼・新崎盛暉先生」。さらにこの3日前に亡くなった翁長雄志沖縄県知事のこと。
沖縄現代史のアーカイブ
●県・市町村の歴史資料保管に対する予算不足という大きな問題。
●村岡敬明さん(明治大学)は沖教組(沖縄県教職員組合)が読谷村に寄贈した約8万点の写真等の資料をデジタルアーカイブ化するにあたって、自治体予算ではなく、クラウドファンディングを用いた。
●特に、資料の分散、保管状態の悪さ(8ミリフィルムがどんどん劣化していくなど)、人員不足といった問題が挙げられる。貴重なはずの資料の内容が把握されないと予算もつかないという悪循環がある。
●故・大田昌秀元知事の沖縄国際平和研究所の資料は、数か所に分けられて保管されるという話がある。
●沖縄県が運営する「沖縄平和学習デジタルアーカイブ」がこの4月に突然見られなくなった問題。渡邉英徳さん(東京大学大学院教授)が中心となって5千万円の予算を投じて作成されたもの。県からの反応は遅く、ようやく最近になって、150万円ほどの運営費が不足しているためとの回答があった。再開の方向だが経緯には不可解なところがある。
記憶の継承
●歴史の記憶を継承しようとする運動も、生活が大変な沖縄においては困難。(数十年前に「公務員年金が安定しているからできるんだろう」と言われたことがあるとの発言。)
●小中高校に平和学習専門の人がいない。県内の大学には沖縄戦や沖縄近代史の研究者もいない(少ない)。
●県・市町村で戦争遺跡の整備予算がほとんどついていない。首里の32軍司令部壕さえ未指定の「ほらあな」。
●「日の丸」の問題。新崎盛暉『沖縄現代史』にあるように、1987年海邦国体の前後に、大きな中央からの圧力によって、「日の丸」掲揚率が全国平均を追いぬいた。もとは「復帰」のシンボルだった。その87年国体では知花昌一氏が「日の丸」を焼いた事件があった(ドキュメンタリー映画『ゆんたんざ沖縄』で描かれている)。
●一方、この頃、沖教祖が「日の丸」について総括しようとする動きがあったが、それは頓挫した。「日の丸」や天皇制に対する視線が一貫性をもたなかったことが、その背景にあった。なお、昭和天皇がアメリカ側に沖縄の長期占領の希望を伝えた「天皇メッセージ」が表に出てきたのは1979年だった。
●海邦国体の「日の丸」事件により、右翼がチビチリガマの平和の像(金城実)を壊した。2017年9月12日に少年4人が像を壊したのは2回目ということになる。このときかれらはチビチリガマの中も徹底的に荒らした。誰のどのような意向かはともかく、平和教育と記憶の継承がうまくいかなくなってきたことを象徴するものだった。
●チビチリガマは「霊感スポット」として語られることがある。歴史に対する深い考察よりも、スピリチュアリズムやダークツーリズムが持て囃される浅薄さにも共通するものがある。
●読谷村は2018年6月に「世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアム」を開いた。その中にはチビチリガマのジオラマがあり、子が母に首を切られる「集団自決」の場面が展示されている。稲嶺知事時代に、平和祈念資料館で住民に銃口を向ける日本兵の像の向きが変えられた事件を思い出すがどうか。
●記憶の継承を「学びなおし」として示した屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす』の視点。
新崎盛暉さん
●CTC闘争を中心とした『琉球弧の住民運動』(~1990年)から『けーし風』(1993年~)への動きが明確。
●『琉球弧の住民運動』は2014年に復刻(『けーし風』読者会がきっかけになった)。原典はほとんど残っていなかったが沖縄大学にあった。
●『沖縄現代史』などが韓国語、中国語に翻訳され出版されたことの効果は大きい。研究者、メディア、運動家、アーティストなどの間で新崎さんの知名度は高い。新崎さんははじめから国境を越えた社会のあり方を考えていた。
沖縄県知事選
●名護市長選(2018/2/4、稲嶺進市長が敗北)は、知的な展望が先走り、市民の暮らし目線が足りなかったとの指摘。
●オール沖縄からは金秀グループ、かりゆしグループが離脱。若い人の間には政治への諦めが蔓延している(つまり、どちらにも付きうる)。
●そのような状況下で翁長知事が亡くなり、果たして知事選(9月末?)はどうなるか。
●候補者として出てきている名前。自民は、佐喜眞淳(宜野湾市長)が軸、あるいは安里繁信(実業家)。県政与党の翁長後継者としては、謝花喜一郎(副知事)、糸数慶子(参議院議員)、城間幹子(那覇市長)、前泊博盛(沖縄国際大学)。
●沖縄の政治を保革の切り口で分析しようとする研究者もいるが、それは間違っている。
その他
●戦後、沖縄戦で破壊された土地における緑化運動が、米国の意向により民政府を通じて進められた(緑の学園運動)。表彰制度もあった。米軍機が墜落した宮森小学校も表彰されたことがある。
●その宮森小学校については、戦時中に民間の「石川学園」として発足し、戦後、宮森小学校、城前小学校に分校し公立の小学校となった経緯がある。
紹介された本
●乗松聡子編著『沖縄は孤立していない』(金曜日)
●ジョン・ミッチェル『日米地位協定と基地公害』(岩波書店)
●林博史『沖縄からの本土爆撃』(吉川弘文館)
●『世界』2018年9月号、特集「人びとの沖縄」(岩波書店)
●櫻澤誠『沖縄現代史』(中公新書)
参照
『けーし風』