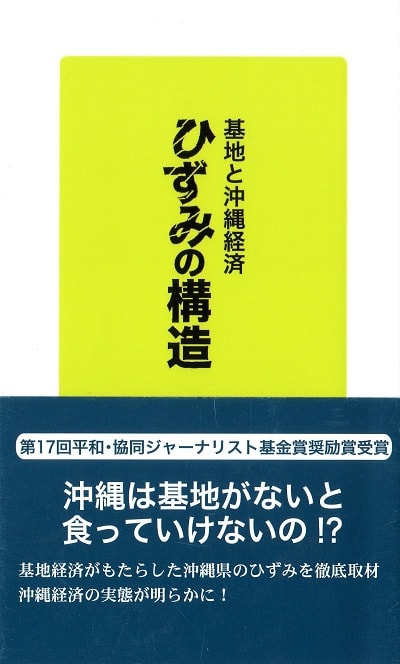NHKスペシャル枠で放送された『"核のゴミ"はどこへ~検証・使用済み核燃料~』(2013/2/10)を観る。
核燃料サイクルが実現せず、その中で使用済み核燃料の再処理工場(青森県六ケ所村)も、技術的な目途が立たず、操業延期を19回も繰り返している。六ヶ所村に住む菊川慶子さんは、東日本大震災よりずっと前から、「遠隔操作で修理を続けているが、処理対象の高レベル放射性廃棄物は廃液のまま置かれている。地震などで電源が止まることへの対策(予備電源等)はなされていない。ひたすら危険な状況だ」との警告を発していた(2009年3月、>> リンク)。要は、ここが詰まっており、もはや使用済み核燃料を抱えられないため、各々の原発において、自ら出した使用済み核燃料を保管している状況であった。わたしもそれは認識していたが、まさか、各原発の同じ建屋内のプールに、あのような無防備な形で置かれているとは、原発事故まで知らなかった。
番組では、現在までの使用済み核燃料は総量1.7万トンだと紹介している。確かに、2010年3月末現在でも総量約1.6万トンであり、54基から年間約1千トンが排出されるペースであったから、稼働停止を含めたこの2年弱で約1年分が増えたことになる(>> リンク)。残りは総量で6千トン程度であり、場所によってはあと2年間で一杯になる。さあ、どうする。

使用済み核燃料の貯蔵量(2010年3月末現在)(「東京新聞」2010/11/28等より作成)
再処理が仮にできたとして、それによりリサイクルされた核燃料を使う計画だった高速増殖炉も、やはり実用化がストップしている。そして、一方、もう使えない高レベル廃棄物は、どこかに最終処分しなければならない。しかし、その場所はない。
番組では、最終処分を行う自治体決定のプロセスを紹介している。それによれば、手を挙げて文献調査を受け容れただけで20億円、次の地上からの調査で70億円、さらに地下での調査、建設と進む。しかし、少なくとも15箇所(公表されていないが、佐賀、鹿児島、長崎、高知、滋賀、福井、青森といった場所)の一部の者が手を挙げるも、すべて、住民の反対によって潰れるか、先に進んでいない。透明性に乏しく、何万年というタイムスケールでの安全性を担保できない前提では、当然のことだと言える。
このうち紹介された地域は、滋賀県の旧・余呉町(現・長浜市)と、長崎県の対馬。対馬では原発事故によりその危険性に気付かされ、ほぼ断念に至っている。逆に言えば、危険だと思わなかったということだ。ここでは、六ヶ所村への見学が9年間で600人にも及んだという。おそらくはどこでも行われている立地工作である。勿論、納得してもらうためであるから、基本的にポジティブな紹介である。番組に登場する対馬の人も、学校や公民館や病院など立派なハコモノに圧倒されて帰ってきたという。わたしも、つい先日、いつも髪を切ってくれる美容師さんが、自分は六ヶ所村の隣で生まれ育ったが、原発を安全だとする教育が徹底しており、事故により批判の声をはじめて聞いて驚いたという話をしてくれて、その温度差にこちらも驚かされた。
他国では、最終処分地が決まっているのはフィンランドとスウェーデンだけだという。番組で紹介された英国とスイスでも苦慮している。日本と大きく違うのは、乾式キャスクを使っていることである。冷却用の電気を使わず、まずは鋼鉄で封じ込め、40-50年間「中間貯蔵」する方法である。日本がプールで貯蔵するのは、使用済み核燃料を直接最終処分するのではなく、再処理後に最終処分する方針だからである。
リスクばかりがありビジネスメリットを見いだせないにも関わらず、再処理を行う方針は撤回されていない。なぜなら、やめてしまうと、国策会社とはいえ民間会社の日本原燃の経営破綻が必至となり、そのマイナスの波及効果が大きいからだ、とされる。また、六ヶ所村に保管されている使用済み核燃料が「資源」から「廃棄物」へと転じ、約束通り各原発に戻そうとしても、それを受け容れる場所はない。
あまりの難題であり、答えはない。しかし、継続は、中長期的なビジョンを決定的に欠いていることは確かである。
番組では、科学部の記者が、「日本の技術力の低下を懸念する米国との関係」についても口にしていた。これは、日本側と提携するGEやWHへの影響のことばかりではないだろう。再処理で生成されるプルトニウムを、核兵器に転用できるということが、米国にとっての日本の核燃料サイクルの大きな意義であった。勿論、NHKはそこまで言及できない。
●参照(原子力)
○鎌田慧『六ヶ所村の記録』
○『核分裂過程』、六ヶ所村関連の講演(菊川慶子、鎌田慧、鎌仲ひとみ)
○『原発ゴミは「負の遺産」―最終処分場のゆくえ3』
○使用済み核燃料
○『活断層と原発、そして廃炉 アメリカ、ドイツ、日本の選択』
○大島堅一『原発のコスト』
○小野善康『エネルギー転換の経済効果』
○『これでいいのか福島原発事故報道』
○山本義隆『福島の原発事故をめぐって』
○開沼博『「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか』
○高橋哲哉『犠牲のシステム 福島・沖縄』、脱原発テント
○前田哲男『フクシマと沖縄』
○原科幸彦『環境アセスメントとは何か』
○『科学』と『現代思想』の原発特集
○石橋克彦『原発震災―破滅を避けるために』
○今井一『「原発」国民投票』
○『大江健三郎 大石又七 核をめぐる対話』、新藤兼人『第五福竜丸』
○有馬哲夫『原発・正力・CIA』
○黒木和雄『原子力戦争』
○福島原発の宣伝映画『黎明』、『福島の原子力』
○東海第一原発の宣伝映画『原子力発電の夜明け』
○『伊方原発 問われる“安全神話”』
○長島と祝島
○長島と祝島(2) 練塀の島、祝島
○長島と祝島(3) 祝島の高台から原発予定地を視る
○長島と祝島(4) 長島の山道を歩く
○既視感のある暴力 山口県、上関町
○眼を向けると待ち構えている写真集 『中電さん、さようなら―山口県祝島 原発とたたかう島人の記録』
○1996年の祝島の神舞 『いつか 心ひとつに』
○纐纈あや『祝の島』