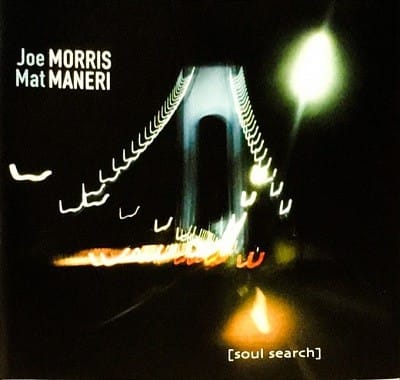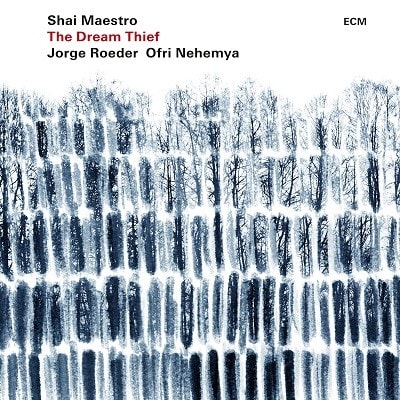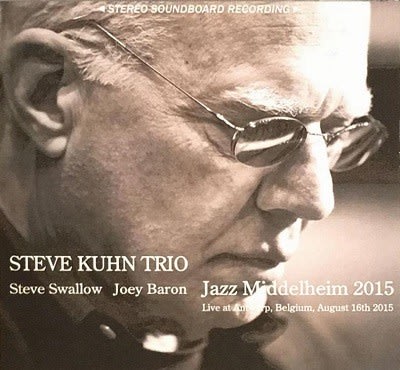横濱エアジンにおいて、ロジャー・ターナー、喜多直毅、齋藤徹のトリオ(2018/10/18)。

Roger Turner (ds)
Naoki Kita 喜多直毅 (vln)
Tetsu Saitoh 齋藤徹 (b)
ぎりぎりに着いてみると会場は満員ソールドアウト。予約しておいてよかった。不況はどこに行った。
同じ場所でのライヴ(ロジャー・ターナー+喜多直毅+齋藤徹@横濱エアジン(JazzTokyo))以来、ほぼ1年ぶりである。おそらく4年連続5回目の共演ということになる。前回はカラフルな展開で、それが演劇的でもあった。今回はというと、目に見える(耳に聴こえる?)展開の多彩さではなく、むしろシンプルな中での連続的な変化が目立っていた。紐帯が強くなったということかもしれない。
外からは車の音や酔っ払いの叫び声が聴こえる。その環境音と混じるようにして、テツさんの弦の音、続いてふたりの注意深く静かな音が放出されてきた。そこからは、じわじわと変化し、グラデーションが付けられてゆき、少しでも気を散らすのが勿体ない。
発散する音の展開があれば、ロジャーさんはスティックの動きを横方向に思い切り拡張する。また大小ふたつのシンバルを近づけ、その間をスティックで叩く。その周波数は曲面がじつになだらかに尖っていて、それが増幅される。
サウンド全体は、周波数プロファイルを選りすぐった綺麗な抑制から、騒乱まで、気が付くと高速でシフトしていた。
セカンドセットは、ざわめきから音を浮上させてきた先とは異なり、最初から既に音が浮上してしまっている。ここでロジャーさんが見事なブラシを見せる。触るか触らぬかという微妙な間合いでの摩擦であり、こうなると叩くという言葉が乱暴に思えてくる。喜多さんとテツさんふたりの弦は、ふたつの独立した流れではあるが、絡み合い、重なり合って、無限にも思える波の形を創り続ける。ここにロジャーさんの美しい火花が散らされる。
ロジャーさんの音のレンジは実に幅広い。喜多さんのヴァイオリンは心の震えのようでもあり、一筆書きのようでもある。ときには風になる。そしてテツさん独特の叢の山々。3人が密やかに無限のグラデーションを提示し、その中で、眼が醒めるようなパルスをもってロジャーさんが参加する。
このセットはやや短く終わったが、変化が集中しており、満足させられた。







Fuji X-E2、XF60mmF2.4、7Artisans 12mmF2.8
●ロジャー・ターナー
ロジャー・ターナー+喜多直毅+齋藤徹@横濱エアジン(JazzTokyo)(2017年)
ロジャー・ターナー+広瀬淳二+内橋和久@公園通りクラシックス(2017年)
ロジャー・ターナー+今井和雄@Bar Isshee(2017年)
蓮見令麻@新宿ピットイン(2016年)
齋藤徹+かみむら泰一、+喜多直毅、+矢萩竜太郎(JazzTokyo)(2015-16年)
ドネダ+ラッセル+ターナー『The Cigar That Talks』(2009年)
フィル・ミントン+ロジャー・ターナー『drainage』(1998、2002年)
●喜多直毅
ファドも計画@in F(2018年)
齋藤徹+喜多直毅@板橋大山教会(2018年)
齋藤徹+喜多直毅+外山明@cooljojo(2018年)
齋藤徹+喜多直毅+皆藤千香子@アトリエ第Q藝術(2018年)
ロジャー・ターナー+喜多直毅+齋藤徹@横濱エアジン(JazzTokyo)(2017年)
翠川敬基+齋藤徹+喜多直毅@in F(2017年)
喜多直毅+マクイーン時田深山@松本弦楽器(2017年)
黒田京子+喜多直毅@中野Sweet Rain(2017年)
齋藤徹+喜多直毅@巣鴨レソノサウンド(2017年)
喜多直毅クアルテット@求道会館(2017年)
ハインツ・ガイザー+ゲリーノ・マッツォーラ+喜多直毅@渋谷公園通りクラシックス(2017年)
喜多直毅クアルテット@幡ヶ谷アスピアホール(JazzTokyo)(2017年)
喜多直毅・西嶋徹デュオ@代々木・松本弦楽器(2017年)
喜多直毅+田中信正『Contigo en La Distancia』(2016年)
喜多直毅 Violin Monologue @代々木・松本弦楽器(2016年)
喜多直毅+黒田京子@雑司が谷エル・チョクロ(2016年)
齋藤徹+かみむら泰一、+喜多直毅、+矢萩竜太郎(JazzTokyo)(2015-16年)
うたをさがして@ギャラリー悠玄(2015年)
http://www.jazztokyo.com/best_cd_2015a/best_live_2015_local_06.html(「JazzTokyo」での2015年ベスト)
齋藤徹+喜多直毅+黒田京子@横濱エアジン(2015年)
喜多直毅+黒田京子『愛の讃歌』(2014年)
映像『ユーラシアンエコーズII』(2013年)
ユーラシアンエコーズ第2章(2013年)
寺田町の映像『風が吹いてて光があって』(2011-12年)
『うたをさがして live at Pole Pole za』(2011年)
●齋藤徹
かみむら泰一+齋藤徹@喫茶茶会記(2018年)
永武幹子+齋藤徹@本八幡cooljojo(JazzTokyo)(2018年)
かみむら泰一+齋藤徹@本八幡cooljojo(2018年)
DDKトリオ+齋藤徹@下北沢Apollo(2018年)
川島誠+齋藤徹@バーバー富士(JazzTokyo)(2018年)
齋藤徹+喜多直毅@板橋大山教会(2018年)
齋藤徹+喜多直毅+外山明@cooljojo(2018年)
かみむら泰一+齋藤徹@本八幡cooljojo(2018年)
齋藤徹+喜多直毅+皆藤千香子@アトリエ第Q藝術(2018年)
2017年ベスト(JazzTokyo)
即興パフォーマンス in いずるば 『今 ここ わたし 2017 ドイツ×日本』(2017年)
『小林裕児と森』ライヴペインティング@日本橋三越(2017年)
ロジャー・ターナー+喜多直毅+齋藤徹@横濱エアジン(JazzTokyo)(2017年)
長沢哲+齋藤徹@東北沢OTOOTO(2017年)
翠川敬基+齋藤徹+喜多直毅@in F(2017年)
齋藤徹ワークショップ特別ゲスト編 vol.1 ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+佐草夏美@いずるば(2017年)
齋藤徹+喜多直毅@巣鴨レソノサウンド(2017年)
齋藤徹@バーバー富士(2017年)
齋藤徹+今井和雄@稲毛Candy(2017年)
齋藤徹 plays JAZZ@横濱エアジン(JazzTokyo)(2017年)
齋藤徹ワークショップ「寄港」第ゼロ回@いずるば(2017年)
りら@七針(2017年)
広瀬淳二+今井和雄+齋藤徹+ジャック・ディミエール@Ftarri(2016年)
齋藤徹『TRAVESSIA』(2016年)
齋藤徹の世界・還暦記念コントラバスリサイタル@永福町ソノリウム(2016年)
かみむら泰一+齋藤徹@キッド・アイラック・アート・ホール(2016年)
齋藤徹+かみむら泰一、+喜多直毅、+矢萩竜太郎(JazzTokyo)(2015-16年)
齋藤徹・バッハ無伴奏チェロ組曲@横濱エアジン(2016年)
うたをさがして@ギャラリー悠玄(2015年)
齋藤徹+類家心平@sound cafe dzumi(2015年)
齋藤徹+喜多直毅+黒田京子@横濱エアジン(2015年)
映像『ユーラシアンエコーズII』(2013年)
ユーラシアンエコーズ第2章(2013年)
バール・フィリップス+Bass Ensemble GEN311『Live at Space Who』(2012年)
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹@ポレポレ坐(2011年)
齋藤徹による「bass ensemble "弦" gamma/ut」(2011年)
『うたをさがして live at Pole Pole za』(2011年)
齋藤徹『Contrabass Solo at ORT』(2010年)
齋藤徹+今井和雄『ORBIT ZERO』(2009年)
齋藤徹、2009年5月、東中野(2009年)
ミシェル・ドネダと齋藤徹、ペンタックス43mm(2007年)
齋藤徹+今井和雄+ミシェル・ドネダ『Orbit 1』(2006年)
ローレン・ニュートン+齋藤徹+沢井一恵『Full Moon Over Tokyo』(2005年)
明田川荘之+齋藤徹『LIFE TIME』(2005年)
ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹+今井和雄+沢井一恵『Une Chance Pour L'Ombre』(2003年)
往来トリオの2作品、『往来』と『雲は行く』(1999、2000年)
齋藤徹+ミシェル・ドネダ+チョン・チュルギ+坪井紀子+ザイ・クーニン『ペイガン・ヒム』(1999年)
齋藤徹+ミシェル・ドネダ『交感』(1999年)
齋藤徹+沢井一恵『八重山游行』(1996年)
久高島で記録された嘉手苅林昌『沖縄の魂の行方』、池澤夏樹『眠る女』、齋藤徹『パナリ』(1996年)
ミシェル・ドネダ+アラン・ジュール+齋藤徹『M'UOAZ』(1995年)
ユーラシアン・エコーズ、金石出(1993、1994年)
ジョゼフ・ジャーマン