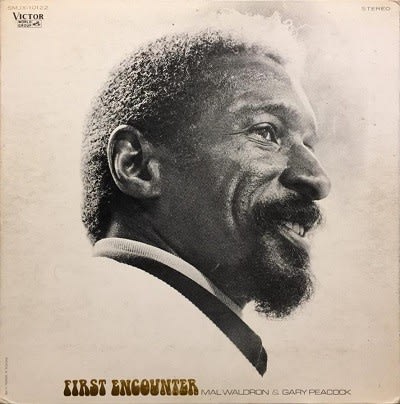先日亡くなったハミエット・ブリューイットを悼むつもりで、ザ・360ディグリー・ミュージック・エクスペリエンス『In: Sanity』(Black Saint、1976年)を聴く。LP 2枚組。(それにしても「360度音楽経験集団」ってカッコいいな。)

Keith Marks (fl)
Francis Haynes (steel ds)
Hamiet Bluiett (bs, cl, fl)
Azar Lawrence (ts)
Titos Sompa (conga)
Sunil Garg (sitar)
Cecil McBee (b)
Dave Burrell (p, org, celeste)
Beaver Harris (ds)
Steel Ensemble (D-2 only):
Francis Haynes (soprano)
Coleridge Barbour (alto)
Alston Jack (tenor)
Michael Sorzano (tenor)
Steve Sardinha (b)
Lawrence McCarthy (iron)
なるべく多くの多様な要素を抱え込むコンセプトの360度。その通りというべきか、洗練されてはおらず、現代ジャズの知的なスマートさもない。とはいえこの野性的なアンサンブルは狙って作れるものではないのだろうし、その隙間がある感覚は好きである。エイゾー・ローレンスはイモのままに吹いているし、残響まで手をかけているようなセシル・マクビーのベースも良い。
個人技のクライマックスはC面で訪れる。ハミエット・ブリューイットがずっとぶりぶりとバリサクを吹き続けており、その音は低音から高音まで縦横無尽。テンポもバリサクの重さより先に走っていくようで、狙ってたたらを踏むようなカッコよさもある。安定のハラハラ感というのだろうか。そしてリーダーのビーヴァー・ハリスは焦っているかのように叩き、デイヴ・バレルは共演者がいようといまいと関係ないと言わんばかりに何者かを煽り続けている。何なんだ。
ブリューイットの勢いはD面にも続く。ここでのソロは闊達で、それがセシル・マクビーの音を長く持たせるベースともフランシス・ヘインズのスティールドラムとも絡んで脳内快感物質を分泌させる。最後はスティールドラムのアンサンブル中心で賑々しく終わる。こういう展開ならエイゾー・ローレンスもなかなか悪くない。
●ビーヴァー・ハリス
アーチー・シェップ『The Way Ahead』 その2(1968年)
アーチー・シェップ『The Way Ahead』(1968年)
アーチー・シェップ『Mama Too Tight』(1966年)
●デイヴ・バレル
スティーヴ・スウェル『Soul Travelers』(2016年)
デイヴ・バレル『Conception』(2013年)
ウィリアム・パーカー『Essence of Ellington / Live in Milano』(2012年)
サニー・マレイ『Perles Noires Vol. I & II』(2002、04年)
●ハミエット・ブリューイット
ワールド・サキソフォン・カルテット『Yes We Can』(2009年)
アーサー・ブライス『Hipmotism』(1991年)
ハミエット・ブリューイット+ムハール・リチャード・エイブラムス『Saying Something for All』(1977、79年)
●エイゾー・ローレンス
エイゾー・ローレンス@Jazz at Lincoln Center(2014年)
●セシル・マクビー
エルヴィン・ジョーンズ+田中武久『When I was at Aso-Mountain』(1990年)
アミナ・クローディン・マイヤーズのベッシー・スミス集(1980年)
チコ・フリーマンの16年(1979, 95年)
チコ・フリーマン『Kings of Mali』(1977年)
セシル・マクビー『Mutima』(1974年)
ハンプトン・ホーズ『Live at the Jazz Showcase in Chicago Vol. 2』(1973年)
ハンプトン・ホーズ『Live at the Jazz Showcase in Chicago Vol. 1』(1973年)