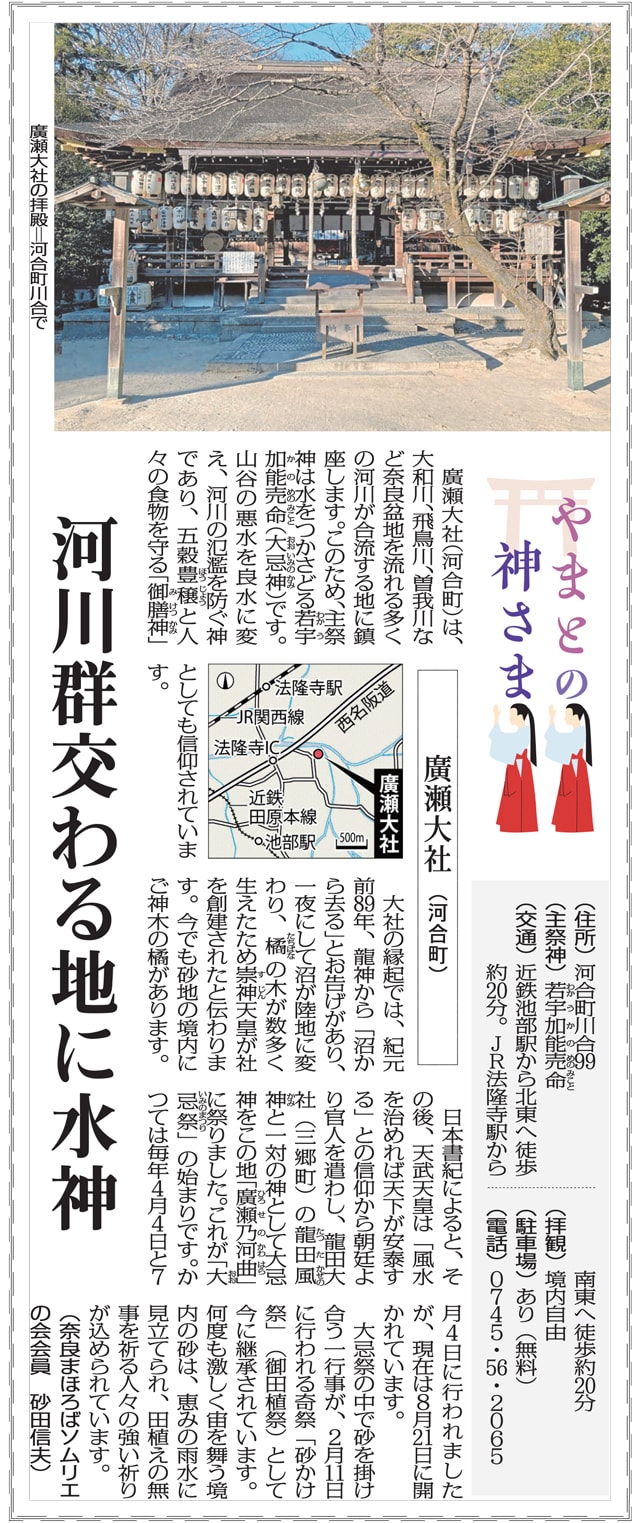今日の「田中利典師曰く」は、〈『山に祈る~峯寺老僧随想録~』を読んで…〉(師のブログ 2015.2.25 付)である。真言宗の機関誌「六大新報」に寄稿された書評である。
※トップ写真は、吉野山の桜(2022.4.7 撮影)
『山に祈る』著者の松浦快芳大僧正は、峯寺(島根県雲南市)の名誉住職である。利典師は〈山あいの風土に溶け込んだ老僧の人柄と、まさにローカリズムを生きることの豊かさを教えてくれる〉と評されているように、いかにも「近代と戦う山伏」らしい書評をお書きである。以下に全文を紹介する。
先日少し書いた『山に祈る~峯寺老僧随想録~』の書評が、六大新報の2月25日号に掲載された。ちょっと分量が多すぎたので、200字ほどカットされたが、読み返して、まあ、頑張って書いていると思う。以下、オリジナルの文章を貼り付けます。掲載された方が良い仕上がりになってはいますが、よろしければご覧下さい。
****************
松浦快芳著『山に祈る~峯寺老僧随想録~』(山陰中央新報社刊)を読んで…
知人を介して、峯寺の名誉住職松浦快芳大僧正が刊行された随筆集『山に祈る~峯寺老僧随想録~』(山陰中央新報社刊)の書評を書いてくれないかと申し出があった。
小生のような愚禿(ぐとく)が、先徳の著書に書評など、おこがましいことだと逡巡していたが、手元に届いた玉稿を読ませて頂いて、私自身、とても大きな教えを得ることが出来た。とても有り難かった。そのお話を書こうと思う。
私の生涯のテーマは「修験道を通してみた近代主義との戦い」である。私は奈良県吉野山にある修験道の根本道場・金峯山寺に暮らしているが、修験道は明治初年の神仏分離政策と、そのあとにつづく修験道廃止令によって大法難に遭遇する。金峯山寺も一時期廃寺とされ、また全国にあった修験霊山の多くは解体されて、修験道そのものが廃絶の危機を迎えたのである。
さてこの神仏分離政策、修験道廃止とはいったいなんだったのかを考えると、行き着くところは日本の近代化という背景にぶち当たる。欧米諸国による植民地化が進むアジアにおいて、植民地にされないためにも、その当時の国策として日本は近代化による富国強兵を急がないといけない事情があった。
そのためには国民国家への社会機構や習俗の作り替えが急務とされ、その精神的な支柱である国家神道確立に伴う、神仏分離や修験道廃止が必然となった。幸い、日本はアジア諸国でいち早く近代化に成功し、それにより植民地となる難を逃れたのも事実である。
ところで、その近代化がもたらした欧米主義によるグローバリゼーションによって、世界は本当に幸せになったのだろうか。近代社会が人類を幸福に導くという幻想は、そろそろ終わりつつあるのだはないか、という現実に我々はいま直面している。
過度な物質文明社会は人間性を疎外し、理由なき殺人を行う若者や尊属殺人を生み、また文明社会の精緻を集めた原子力発電は、福島原発事故に際して先祖代々受け継いで来た土地を奪われた同胞たちを生んだ。
さらに世界に目を向ければ、文明の衝突とも言える、欧米諸国とイスラム世界の絶望的な相克を思うとき、私たち人類の未来に希望の光はあるのだろうかと、立ち尽くす日々である。
翻ってみれば、近代がヨーロッパ社会で生まれて以降、世界はユニバーサル、あるいはグローバルという美名のもとに、一つの価値観で画一化することを目指してきた。ユニバーサルもグローバルも普遍性を持っているという理解なのである。
そして現にいまもグローバリゼーションという嵐によって、その土地の文化、その土地の風土が世界中で破壊され続けている。
修験道もまた日本の近代化の生け贄とされたのだった。しかしその風土、その土地で生まれたものを大事にすることのほうが、人類や地球にとっては普遍的なことなのではないか、私はそう気づいたのである。それを私は「近代主義との戦い」と呼んでいる。
日本も又、明治以降、近代化の美名のもとに欧米的な価値観を植え付けられてしまったわけだが、いままさに、あらためて自分たちの風土を見つめ直して、その文化を耕していくことが求められていると言っていいだろう。その鍵を握るのは私はグローバルからローカリズムへの転換だと思っている。私にとっての「修験道を通してみた近代との戦い」とは新たなローカリズムへの目覚めという段階までに進んできた。
ところが、実はそれをどう具現化するのか、戦後のグローバル洗脳世代の私にはなかなか難しい課題である。その難問に見事に答えていただいたのが、本書『山に祈る』であった。
峯寺は修験道の開祖役行者の由緒も伝える出雲の国の山間に位置する古刹である。その峯寺に住し、四季折々の移ろいの中で、壇信徒とともに自然に学び、茶道をたしなみ、長年にわたりユースホステルを営み、訪れる若者や、お迎えしたチベットの高僧たちとの交流を楽しむ。
そこには愛犬ポチがいて、出雲神話も息づいている。その日々は山あいの風土に溶け込んだ老僧の人柄と、まさにローカリズムを生きることの豊かさを教えてくれる。本書のあじわいはそこにあると私は感じている。
文中に出る一節がある。〈小坊さんが大きくなっていかっしゃる間には、難儀なこともある。困ったときはね、この山に登って胸を張ってね。大きな息をしてみなはい」。正月の山頂は、風が冷たく身に沁みる。今川おじさんは話に一区切りをつけると、「さあ」と、私の背中をおしてくれて下山の途に就いた…〉。
冒頭から「近代との戦い」などと大仰なことを言ったが、時代はかわり、生活も大きく変化していくといえども、里山や四季の寒暖のなかで、細やかに生きる風景を私達は失ってはいけないと、そう教えていただいたのだった。 (金峯山寺宗務総長 田中利典)
※トップ写真は、吉野山の桜(2022.4.7 撮影)
『山に祈る』著者の松浦快芳大僧正は、峯寺(島根県雲南市)の名誉住職である。利典師は〈山あいの風土に溶け込んだ老僧の人柄と、まさにローカリズムを生きることの豊かさを教えてくれる〉と評されているように、いかにも「近代と戦う山伏」らしい書評をお書きである。以下に全文を紹介する。
先日少し書いた『山に祈る~峯寺老僧随想録~』の書評が、六大新報の2月25日号に掲載された。ちょっと分量が多すぎたので、200字ほどカットされたが、読み返して、まあ、頑張って書いていると思う。以下、オリジナルの文章を貼り付けます。掲載された方が良い仕上がりになってはいますが、よろしければご覧下さい。
****************
松浦快芳著『山に祈る~峯寺老僧随想録~』(山陰中央新報社刊)を読んで…
知人を介して、峯寺の名誉住職松浦快芳大僧正が刊行された随筆集『山に祈る~峯寺老僧随想録~』(山陰中央新報社刊)の書評を書いてくれないかと申し出があった。
小生のような愚禿(ぐとく)が、先徳の著書に書評など、おこがましいことだと逡巡していたが、手元に届いた玉稿を読ませて頂いて、私自身、とても大きな教えを得ることが出来た。とても有り難かった。そのお話を書こうと思う。
私の生涯のテーマは「修験道を通してみた近代主義との戦い」である。私は奈良県吉野山にある修験道の根本道場・金峯山寺に暮らしているが、修験道は明治初年の神仏分離政策と、そのあとにつづく修験道廃止令によって大法難に遭遇する。金峯山寺も一時期廃寺とされ、また全国にあった修験霊山の多くは解体されて、修験道そのものが廃絶の危機を迎えたのである。
さてこの神仏分離政策、修験道廃止とはいったいなんだったのかを考えると、行き着くところは日本の近代化という背景にぶち当たる。欧米諸国による植民地化が進むアジアにおいて、植民地にされないためにも、その当時の国策として日本は近代化による富国強兵を急がないといけない事情があった。
そのためには国民国家への社会機構や習俗の作り替えが急務とされ、その精神的な支柱である国家神道確立に伴う、神仏分離や修験道廃止が必然となった。幸い、日本はアジア諸国でいち早く近代化に成功し、それにより植民地となる難を逃れたのも事実である。
ところで、その近代化がもたらした欧米主義によるグローバリゼーションによって、世界は本当に幸せになったのだろうか。近代社会が人類を幸福に導くという幻想は、そろそろ終わりつつあるのだはないか、という現実に我々はいま直面している。
過度な物質文明社会は人間性を疎外し、理由なき殺人を行う若者や尊属殺人を生み、また文明社会の精緻を集めた原子力発電は、福島原発事故に際して先祖代々受け継いで来た土地を奪われた同胞たちを生んだ。
さらに世界に目を向ければ、文明の衝突とも言える、欧米諸国とイスラム世界の絶望的な相克を思うとき、私たち人類の未来に希望の光はあるのだろうかと、立ち尽くす日々である。
翻ってみれば、近代がヨーロッパ社会で生まれて以降、世界はユニバーサル、あるいはグローバルという美名のもとに、一つの価値観で画一化することを目指してきた。ユニバーサルもグローバルも普遍性を持っているという理解なのである。
そして現にいまもグローバリゼーションという嵐によって、その土地の文化、その土地の風土が世界中で破壊され続けている。
修験道もまた日本の近代化の生け贄とされたのだった。しかしその風土、その土地で生まれたものを大事にすることのほうが、人類や地球にとっては普遍的なことなのではないか、私はそう気づいたのである。それを私は「近代主義との戦い」と呼んでいる。
日本も又、明治以降、近代化の美名のもとに欧米的な価値観を植え付けられてしまったわけだが、いままさに、あらためて自分たちの風土を見つめ直して、その文化を耕していくことが求められていると言っていいだろう。その鍵を握るのは私はグローバルからローカリズムへの転換だと思っている。私にとっての「修験道を通してみた近代との戦い」とは新たなローカリズムへの目覚めという段階までに進んできた。
ところが、実はそれをどう具現化するのか、戦後のグローバル洗脳世代の私にはなかなか難しい課題である。その難問に見事に答えていただいたのが、本書『山に祈る』であった。
峯寺は修験道の開祖役行者の由緒も伝える出雲の国の山間に位置する古刹である。その峯寺に住し、四季折々の移ろいの中で、壇信徒とともに自然に学び、茶道をたしなみ、長年にわたりユースホステルを営み、訪れる若者や、お迎えしたチベットの高僧たちとの交流を楽しむ。
そこには愛犬ポチがいて、出雲神話も息づいている。その日々は山あいの風土に溶け込んだ老僧の人柄と、まさにローカリズムを生きることの豊かさを教えてくれる。本書のあじわいはそこにあると私は感じている。
文中に出る一節がある。〈小坊さんが大きくなっていかっしゃる間には、難儀なこともある。困ったときはね、この山に登って胸を張ってね。大きな息をしてみなはい」。正月の山頂は、風が冷たく身に沁みる。今川おじさんは話に一区切りをつけると、「さあ」と、私の背中をおしてくれて下山の途に就いた…〉。
冒頭から「近代との戦い」などと大仰なことを言ったが、時代はかわり、生活も大きく変化していくといえども、里山や四季の寒暖のなかで、細やかに生きる風景を私達は失ってはいけないと、そう教えていただいたのだった。 (金峯山寺宗務総長 田中利典)