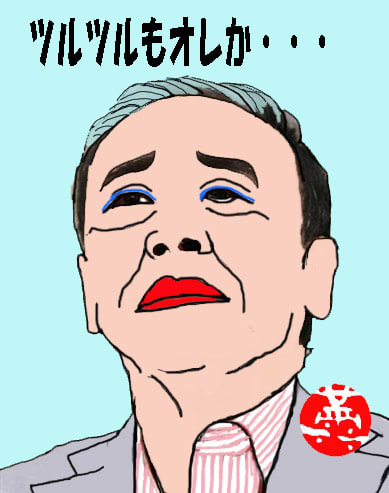都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
「海苔(のり)」の語源は、ヌルヌルするという意味の「ヌラ(滑)」が転訛して「海苔」になったと考えられています。
つまり「ぬら」→「ぬらり」→「のり」というわけです。
事実、海苔ももともとはヌルヌルしています。
「糊(のり)」も、ヌルヌルしていますが、語源は違います。「膠(にかわ)」、「沈糊(じんのり/小麦粉を袋に入れて、もみ出した澱粉を煮たもの)」、「続飯(そくい)/米飯を練ったもの」、これらの粘性のあるものを「ねまり」と呼び、これが「糊」の語源であるといわれています。
つまり「ねまり」→「ねり」→「のり」というわけです。
飛鳥時代に書かれた『風土記(670年頃)』には「常陸(ひたち)の国、ノリ浜で紫菜(むらさきのり)を干していた」という記述が見られるそうです。
奈良時代の大宝律令(701年)には、アマノリ(のりの仲間の総称)・ミル・アラメ・テングサなど海藻が海産物29種の1つに指定され租税として徴収された記録があります。
平安時代の『延喜式(927年)』にも、租税の対象としてアマノリを含む10数種類の海藻が定められていました。平安時代の貴族は米を主食として副食に海藻をかなり食べていたようです。しかし、庶民の食べ物ではなく、五位以上の貴族に限ってのみ支給される大変な貴重品でした。
平安時代は「紫菜(むらさきのり)」「甘のり」と呼ばれていました。
江戸時代になってから「のり」と呼ばれるようになり「海苔」の漢字が使われたそうです。
ちなみに、海苔は韓国で「海衣(ハイホ)」、中国では「紫菜(シーツアイ)」と呼ばれているそうです。
 本題の海苔の表裏ですが、まず海苔の製造法を知っておかないといけません。
本題の海苔の表裏ですが、まず海苔の製造法を知っておかないといけません。
アサクサノリあるいはアオノリ、アマノリを岩から採取、よく洗いそれを包丁で細かく刻みます。あとは、海苔簀(のりす)に流し込んで日光で乾燥させるそうです。
ここまでは、問題ないのですがここから意見が分かれます。
この製造法だと、どうしても海苔に「光沢」のある面と、ない面が生じます。この時、日光に直接当たった面はその「光沢」がありません。(理由は後述)
当然日光に直接当たった方が表とされるべきで、光沢のない面が「表」という説です。
いやいや、光沢のあるほうが当然表だとする説もあります。
山本山のQ&Aには下記のように載っていました。
弊社で現在確認できている「海苔の裏表」については、ツルツルした艶のある方が表面で、比較的ザラザラした面が裏でございます。
昔は手作業で海苔を製造する際に海苔を天日干しにするのですが、その時の干し方により海苔の表が決められたとのことです。その当時は、海苔簀(のりす…竹を編んだすだれ状のもの)の上にミンチ(海苔の原藻を細かくし真水で洗う)した海苔を水と共にすきました。
その後、海苔簀側の面から海苔簀ごしに、先に太陽にかざし乾燥させたことから、最初に日に当たる海苔の面を表面としたと聞いております。この時、最初に日に当たる面は海苔簀に海苔が張り付いているため、はがすとざらざらとしておりました。
しかし、最近では海苔すき・乾燥とも自動機械化されております関係上、また、海苔の見た目も考慮され、先にも申しあげましたとおり、ツルツルした面を表としておりますのが通説でございます。
山本山さんの言うように、昔はざらざらした面が表だったのですが、今はツルツルした面が表のようです。
したっけ。