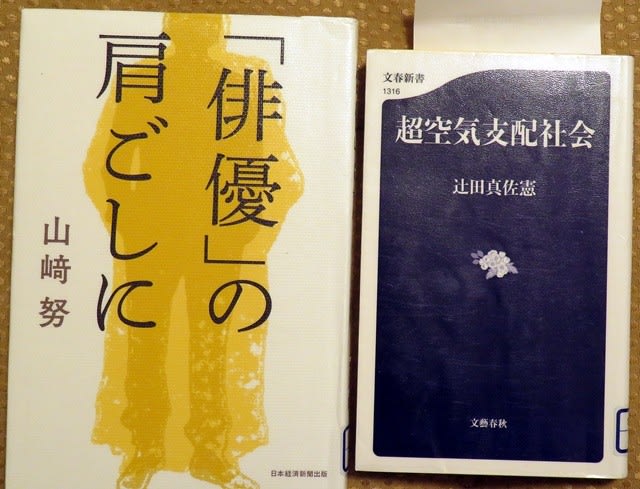|
2012年12月23日 朝刊
 防護服を身にまとい汚染物質を詰めたバッグを仮置き場に集める作業員。福島県内の除染は遅れ気味だ=11月、飯舘村で 防護服を身にまとい汚染物質を詰めたバッグを仮置き場に集める作業員。福島県内の除染は遅れ気味だ=11月、飯舘村で
東京電力の福島第一原発事故で放出された放射性セシウムなどの除染のため、三年間で一兆円を超える公費が投入される。だが放射線量が高い地域では
、効果に疑問の声も根強く、事業は遅れ気味だ。除染によって住民が元通り暮らせるという将来像を示さぬまま
、巨額事業を推し進めようとする国などに対し、住民の不信感は消えない。 (小嶋麻友美)
全村避難をしている福島県飯舘村の前田地区で区長を務める長谷川健一さん(59)が疑問を口にする。
「家の周りをいくら除染しても、山を除染しなければ放射性物質が流れ込んでくる」
国が直轄で除染を行う飯舘村では、本年度の除染対象の四地区で事業を発注済み。一方、十月に、住民が帰還する見込み時期について、
地域ごとに二〇一四~一七年春とすることで村と政府が合意した。しかし、村の二地区では住民の同意が得られず、除染作業にまだ着手できていない。
除染の効果も不透明だ。山に近い福島市東部では、三月に除染で毎時一・八マイクロシーベルトまで下がったのが、
十月には七・八マイクロシーベルトに再上昇した例もある。
飯舘村は森林が七割以上を占める。除染を行う森林は当面、住宅や農地から二十メートルほどの隣接部分だけ。
長谷川さんは「ほとんどの民家は山のすそにある」と指摘する。
国の除染計画は、来年度末までに被ばく線量が年間二〇ミリシーベルトを超える地域を「二〇ミリシーベルト以下」に下げることを除染の目標としている。
だが、国際放射線防護委員会(ICRP)が、健康に影響が出ないように考慮し、
一般市民の平常時の基準としている年間一ミリシーベルトの被ばく線量と隔たりがある。
長谷川さんは「二〇ミリシーベルトに下がっても若い人や孫の世代は帰ってこない」と話す。
高齢の住民には早期帰村を望む人も多いが、「除染をして、子どもが外で遊べるぐらい線量が下がらなければ意味がない。
だが、国も県もどこまで下げるつもりかを示さない。お金を投入し、形だけ除染して『帰村しなさい』と押しつけられるのでは」と懸念する。
一時帰宅した自宅で除染事業への疑問を話す長谷川健一さん(左)。右はスイスから取材に訪れたスーザン・ボースさん=飯舘村で
◆「住民の選択肢広げて」チェルノブイリ取材したボースさん
「除染直後は線量が下がっても、時間の経過で元のもくあみになる可能性がある。チェルノブイリでもそうだった」。
こう指摘するのは、チェルノブイリ原発事故後、二十年にわたってウクライナを取材してきたスイス人ジャーナリスト、スーザン・ボースさん(49)だ。
昨年来日して福島原発事故を取材し、著書「福島からのメッセージ」をスイスとドイツで刊行。これを含め、長年の原発報道が評価され、
ドイツのNGOが創設した「核のない未来賞」を受賞した。
今月、三度目の取材に福島を訪れたボースさんは、福島市でも除染後しばらくして放射線量が再上昇する事例を聞いた。
「妊婦や小さな子どもの自主的な避難にも、補償などの財政措置を行い、選択肢を広げるべきだ」
ウクライナでの取材経験を踏まえ「ウクライナでは、除染も被ばくによる健康問題も解決には長い年月がかかり、莫大(ばくだい)な金額になった。
行政はどこにお金をかけるべきかを考える必要がある」と指摘した。
<国の除染事業> 福島第一原発から20キロ以内と、事故後1年間の積算の被ばく線量が20ミリシーベルトを
超える福島県内の11市町村では、国が直轄で除染を行う。
公共施設などの先行除染を経て今年7月以降、楢葉町、飯舘村など4市町村で住宅や農地などの本格除染が始まった。
また被ばく線量が年間1ミリシーベルトの地域を含む汚染状況重点調査地域の101市町村では、国の財政支援を受け市町村が除染を行う。
国は除染費用として2011、12年度で5700億円を計上。13年度も5000億円を予算要求している。
|