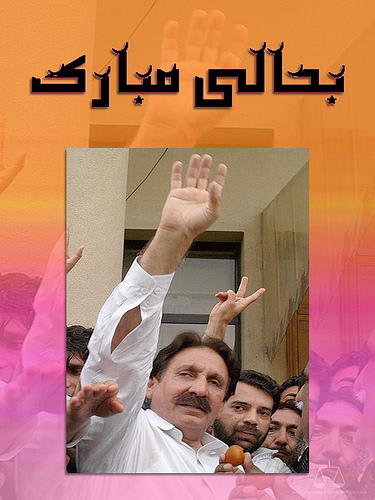(北朝鮮・平城の柳京ホテル 今年4月に工事が再開されたと伝えられています。【5月19日 読売】
105階建て、高さ約330メートルの巨大建造物です。
1987年に北朝鮮最大の建築物として着工されましたが、経済状態の悪化による資金難、技術的問題があって92年以降建設途中で放置されていました。
食糧事情の悪化、餓死者の発生、アメリカの食糧支援が報じられている北朝鮮ですが、今ホテル建設の余力があるのでしょうか?
“flickr”より By Pricey http://www.flickr.com/photos/pricey/478953519/ )
*****ラングーン事件の実行犯が死去 北朝鮮の工作員******
ビルマ(現ミャンマー)訪問中の全斗煥(チョン・ドファン)韓国大統領(当時)の暗殺を北朝鮮が謀った83年10月のラングーン事件で、実行犯の一人だった北朝鮮のカン・ミンチョル工作員が18日、ミャンマーの病院で死去した。軍政筋が19日、朝日新聞に明らかにした。53歳。死因は肝臓がんだった。ビルマ当局(当時)に逮捕され、死刑判決を受けたが、犯行を自白したことで終身刑に減刑されていた。ほかの実行犯の2人はすでに死亡している。【5月21日 朝日】
*********************************
ラングーン事件、もう25年前になります。
【ウィキペディア】から事件の概要を引用すると以下のとおりです。
【ラングーン事件概要】
1988年のソウルオリンピック開催を目指していた韓国は、北朝鮮と親密だった非同盟中立諸国に閣僚を派遣し、韓国でのオリンピック開催や、その際の参加を熱心に説得に回っていた。金日成主席は外交的孤立の危険に非常に苛立ち、全斗煥韓国大統領の暗殺計画を実行した。
計画の立案は金日成の長男である金正日であるといわれている。
1983年10月、チン・モ少佐(85年絞首刑)とカン・ミンチョル上尉(今回死亡)およびキム・チホ上尉(逮捕時射殺)の3人がビルマの首都・ラングーン(現・ヤンゴン)へ入り、大統領一行が訪れるアウン・サン廟の屋根裏に遠隔操作式のクレイモア地雷を仕掛けた。
10月9日、大統領一行は、アウン・サン廟へ献花に訪れた。その時、遠隔操作によって廟の天井で爆発が起こり、韓国側は副首相や外務部長官ら閣僚4名を含む17名、ビルマ側はアウン・チョウ・ミン情報文化相、タン・マウン情報文化省次官など閣僚・政府関係者4名が爆死し、負傷者は47名に及んだ。全斗煥自身は、乗っていた車の到着が2分遅れたため、危うく難を逃れた。
ビルマ警察の調査と追跡により、工作員3名は追い詰められ、銃撃戦の末に逮捕された。逮捕された2人は警察に対して案外簡単に作戦の全貌を自供し、11月4日にビルマ政府は犯行を北朝鮮によるものと断定して、3人の北朝鮮軍人を実行犯として告発、有罪となった。これによって、建国の父であるアウン・サンの墓所をテロに利用されたビルマは北朝鮮との国交を断絶するのみならず、国家承認の取り消しという極めて厳しい措置を行った。
*******************
外国で、敵対国首脳を一網打尽に爆殺しようというこの事件の“荒っぽさ”は衝撃的で、ながく記憶に残っています。
【朝鮮半島情勢の変化】
今回亡くなったカン元被告は獄中で、「北朝鮮に戻れば“裏切り者”扱いされ、韓国に行けば全斗煥元大統領を暗殺しようとした罪で起訴されるのではないか」と心配していたこと、また、韓国政府関係者との数回の面談では、自らが犯したテロ行為を反省し、韓国に行きたいと話していたことも伝わっています。
しかし、韓国側は「北朝鮮は爆弾テロ事件を韓国の自作自演だと主張している。その事件の主導者を韓国に連行すれば、北朝鮮が“自分らが犯行を命じた人物を再び連れ戻そうとしている”と主張することもあり得る」として難色を示していたとか。【07年4月25日 朝鮮日報】
ラングーン事件を含め、当時の北朝鮮・韓国の関係は一触即発の厳しい対立関係にありました。
その頃のイメージが強く、昨今の、特に盧武鉉前政権時代の南北協調は、良し悪しは別として、なんだか狐につままれたような奇妙な感じがしています。
【ミャンマーと北朝鮮】
ところで、当時ビルマは非同盟中立国として国際社会でも一定の信頼を得ていましたが、現在の軍事政権は昨年の民主化要求弾圧、最近のサイクロン被害に対する国際援助拒否など、国際社会無視の強権体質を鮮明にしています。
その体質はかつてラングーン事件で国家承認取消しにまで至った北朝鮮のそれと共通するものを感じます。
ミャンマーでは被災者救援活動の遅れ、国際援助物資の軍部による横流しも報じられています。
北朝鮮における飢餓による国民の困窮、援助物資の闇市への流失、一部特権者の恵まれた生活などが報じられる北朝鮮の姿とそっくり重なるものがあります。
(もっとも、ミャンマーは弾圧・災害時以外は普通に外国人が観光もでき、市民生活もそれなりに営まれているように、北朝鮮の異常さとはレベルが異なるとも言えます。)
国際社会に背を向ける両国は、その似た体質・境遇からか、近年急速に関係を改善しており、昨年4月には外交関係回復で正式合意しています。
この“アジアのお荷物”をバックアップしているのが中国。
中国に両国との関係を見直すように求めるしか、とりあえずの方策はないようにも思えます。