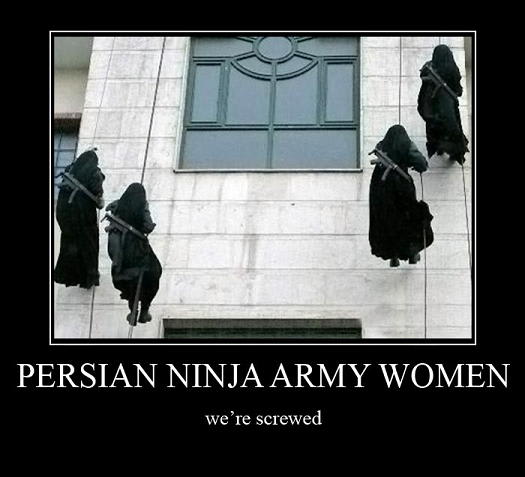(トゥールーズの事件後、保護者に付き添われて学校を去る生徒 “flickr”より By juanzi615 http://www.flickr.com/photos/21427686@N03/7001527917/ )
【「反ユダヤ主義や人種差別的な発言が不安定な環境を作り出した」】
フランスで19日に起きたユダヤ人学校前での銃乱射事件は、特定人種を狙ったテロと思われることから、大きな衝撃を国内に与えました。
****フランス:ユダヤ人学校前で銃乱射、4人死亡****
フランス南西部の都市トゥールーズで19日午前8時ごろ(日本時間19日午後4時ごろ)、バイクに乗った男がユダヤ人学校前で銃を乱射し、地元当局によると、少なくとも4人が死亡した。うち3人は子供だった。
男は銃器2丁で武装し、乱射後、逃げる子供らを追って学校内まで侵入して逃走した。トゥールーズ周辺では先週、同様にバイクに乗った男が仏軍兵士3人を殺害する銃撃事件が相次いでおり、捜査当局は関連を調べている。
サルコジ大統領やゲアン内相が現場に急行した。1カ月後に控えた仏大統領選では、欧州債務危機に伴う景気の低迷で移民規制の強化など「右傾化」が目立っており、事件後、在仏ユダヤ人団体は「反ユダヤ主義や人種差別的な発言が不安定な環境を作り出した」と批判した。
警察などによると、事件当時、学校前では子供や保護者、教師らが送迎バスを待っていた。男は45口径の銃などで武装し、「動くものは何でも標的にした」という。先の仏軍兵士銃撃事件でも45口径が使われており、関連性が疑われているが、サルコジ大統領は「結論を出すには早すぎる」と慎重な姿勢を示した。
イスラエル外務省報道官は「背筋の凍る事件だ」と述べ、背後関係の徹底解明を求めた。イスラエルのメディアによると、襲われた学校はユダヤ教系。トゥールーズには約2万5000人のユダヤ人が住んでおり、学校は地域のユダヤ人社会の中核だった。【3月19日 毎日】
******************************
おりしもフランスは大統領選挙のさなかで、サルコジ大統領など各候補は選挙運動を一時中断して現地を訪れています。
****フランス:与野党候補が現地入り…学校銃乱射*****
フランス南部の都市トゥールーズのユダヤ人学校で19日、男が銃を乱射し、男性教員と児童3人が殺害された事件を受け、4月に大統領選を控えたサルコジ大統領や最大野党・社会党のオランド前第1書記ら各候補は相次いで現地入りし、追悼式典などに参列した。また各候補は犠牲者を悼んで選挙運動の一時中断を決めた。国民の団結や治安を重視する姿勢を訴えつつ、約55万人のユダヤ人票にも配慮したとみられる。
ゲアン内相は20日のラジオ番組に出演し、犯人が首にビデオカメラをさげていたとの目撃証言を明かしたが「犯人像は絞り込めていない」と述べた。捜査当局は人種差別主義で極右思想の持ち主か、イスラム過激派による犯行の可能性があると見て捜査している。
現地のユダヤ系フランス人社会では、治安への不安が広がっている。19日午後、追悼集会が開かれたトゥールーズ中心部のシナゴーグ(ユダヤ教礼拝所)では数百人のユダヤ教徒が集まり、犠牲者に祈りをささげた。近隣の高校に通うフィンケンチムさん(15)は「理解できない。犯人は反ユダヤ主義というより、精神的に異常な人間だと思う」と話した。
大統領選で極右支持層への浸透を狙うサルコジ氏が「移民半減」を公約に掲げ、与党・国民運動連合幹部が人種差別的発言を繰り返すなど、選挙戦の「右傾化」の影響を指摘する声もある。心理療法士のダアンさん(53)は「大統領選がとても険悪な雰囲気を作り、それが高い代償を払う結果につながったと思う。選挙戦がここまで右傾化するのは初めてではないか」と語る。サルコジ大統領は事件を受けて19日、トゥールーズ周辺の警戒レベルを最高の「深紅」に上げた。仏メディアによると、90年代に4段階の警戒レベルが定められて以来、「深紅」の適用は初めてという。
現地入りしたサルコジ氏は「この憎むべき行為は必ず罰する」と強調した。一方、オランド氏は「反ユダヤ主義や人種差別にフランス全体の固く団結した意思で立ち向かう」と表明。極右政党「国民戦線」のルペン候補はテレビに出演し「今こそ政治活動を取りやめ共感と団結のための時だ」と述べた。【3月20日 毎日】
***************************
【人種や政治信条を理由に無抵抗な市民を殺す新しい「欧州型のテロ」の増大】
各記事が触れているように、フランスでは増大する移民への反発から、社会の右傾化が目立っており、そのことが、ひところの極右政党「国民戦線」のルペン候補の躍進、そしてここへきてのサルコジ大統領の「右旋回」による極右票取り込み、追い上げに繋がっていると見られています。
そうした右傾化・反移民の社会風潮は、フランスだけでなく欧州全体に共通した流れでもあり、一般市民を巻き込んだテロが起きています。
ユダヤ系社会を標的にした事件ということで、今回事件とそうした社会全体の右傾化、大統領選挙での極右票を狙ったキャンペーンなどの関連が指摘されました。
****仏ユダヤ人学校銃乱射:無差別テロ連鎖の不安 人種・宗教理由に市民を標的****
フランス南部トゥールーズのユダヤ人学校での銃乱射事件で、人種や宗教・政治信条などを理由に一般市民を無差別に殺すテロがさらに起こるのではないかとの不安が現場で高まっている。
ノルウェーやドイツでも、昨年から一般市民を巻き込んだ同種のテロが顕在化、新しい「欧州型のテロ」として捜査当局は警戒を強めている。
仏捜査当局が事件を単純な反ユダヤ主義でなく、「テロ」として警戒度を最高レベルに上げているのは、19日にユダヤ人学校を襲撃した犯人が、現場周辺で北アフリカ系の兵士3人も射殺したとみているからだ。3月11日にはトゥールーズで1人が、15日には約50キロ北のモントバンで2人が同じ銃で殺された可能性が高い。再び人種などを理由に市民に銃を向けるとの不安が広がっている。
多くの市民が想起するのは昨年7月、「移民導入を進めた」ことを理由に与党・労働党支持者の若者ら77人が殺害されたノルウェーの連続テロ事件だ。
ドイツでも極右ネオナチの男女3人組が00~07年に、トルコ系移民ら計10人を次々に殺害した事件が昨年、発覚。人種や政治信条を理由に無抵抗な市民など「ソフトターゲット」を殺す欧州型のテロが根強くはびこっていることを見せつけた。
フランスでは極右政党の「国民戦線」が近年「穏健路線」にかじを切るにつれ、不満を抱く極右層が小規模の政治集団を組織するなど動きを活発化させている。極右集団「共和国抵抗運動」と「アイデンティティー連合」は10年に反イスラム運動を組織。連合は2月、トゥールーズに事務所を開き、極左活動家が反対運動を起こすなどした。こうした小規模の極右グループの動きもテロの背景にあるとの見方がある。
トゥールーズ在住の精神分析学者エナールさん(67)は「個人が何かの標的を見いだすことで不満を発散させているとすれば、オスロの事件と似ている。オスロでは標的が社会民主主義の若者で、今回はユダヤ人・外国人だったのだろう」と話す。【3月21日 毎日】
**************************
【「パレスチナの子供の敵を討ち、仏軍を攻撃する」】
上記記事の指摘は一般論としては間違いではありませんが、今回事件については、容疑者は極右関係者ではなく、アルカイダメンバーであるとの見解が内務省から出されています。
****仏銃乱射:容疑者宅で銃撃戦、警察官2人けが****
フランス南部トゥールーズのユダヤ人学校での銃乱射事件で、仏警察当局は21日、容疑者とみられる男(24)の住宅を包囲した。現場は銃撃戦となり警察官2人が軽傷を負った。
内務省当局によると、男は北アフリカ出身で仏国籍。ムジャヒディン(イスラム聖戦士)を自称し、国際テロ組織アルカイダに所属していると主張している。
アフガニスタンとパキスタンに渡航歴があり、包囲する警察官に「パレスチナの子供の敵を討ち、仏軍を攻撃する」と語ったという。警察当局は男の兄弟を拘束し、事情を聴取している。
また検察当局によると、当局は容疑者逮捕に向けた複数の作戦を同時展開している。近隣住民の目撃情報によると、最初の銃声は午前3時ごろ聞こえたという。
事件は19日、ユダヤ人学校前で発生し、男が銃を乱射し、子供3人と男性教師1人の計4人が死亡した。【3月21日 毎日】
***************************
もしネオナチとか極右関係者の犯行ということであれば、イスラム移民を念頭に置いた「移民半減」を掲げるサルコジ大統領の「右旋回」選挙キャンペーンは、こうした人種差別的テロを煽ることにもなりかねないとして、強い批判にさらされます。
しかし、北アフリカ出身のアルカイダメンバーによる犯行ということになれば、逆に、反イスラム移民の社会風潮を後押しし、サルコジ大統領の選挙戦も追い風を受けることにも考えられます。
【オランド候補を追い上げるサルコジ大統領】
大統領選挙選は、社会党オランド候補にリードを許していたサルコジ大統領が追い上げを見せており、第1回投票ではオランド候補を抑える支持率を見せています。決選投票においては、まだオランド候補がリードしているというのが大方の見方ですが、やはりサルコジ大統領の回復傾向が見られるようです。
****仏大統領選 猛追、サルコジ氏 第1回投票まで1カ月****
フランス大統領選は20日までに、現職のサルコジ大統領(57)や最大野党、社会党候補のオランド前第1書記(57)ら計10人の立候補が正式に確定した。4月22日の第1回投票まで1カ月となり、世論調査ではこれまで劣勢だったサルコジ氏が猛追し、第1回投票の支持でオランド氏を上回りはじめた。5月の決選投票ではオランド氏の優位が続くが、選挙の行方は混沌(こんとん)としてきた。
■2氏の競り合い「内向き」に
サルコジ、オランド両氏以外の主要候補は極右、国民戦線の女性党首、マリーヌ・ルペン氏や中道、民主運動のバイル議長、共産党が支持する左派戦線のメランション氏。
18日に公表された世論調査では、第1回投票でのサルコジ氏への支持が27・5%に対し、オランド氏は27%。ルペン氏が17・5%と続く。決選投票ではオランド氏が54%で、サルコジ氏は46%にとどまる。だが、19日発表の別の調査でもサルコジ氏に「好感を持つ」との回答者が今年初めの30%から40%に増え、上昇傾向は鮮明となってきた。
◆激しさ増す舌戦
「朝に『借金を減らす』といい、翌朝には『お金をもっと使う』という。大統領選で嘘はいけない」
南東部リヨンで17日開かれた選挙集会。サルコジ氏は支持者8千人を前に、オランド氏が財政再建の公約に柔軟姿勢を示したことをするどく批判した。
オランド氏も対抗し、同日出演したテレビでは「実績に頼ることができず、自暴自棄になっている」と5年間のサルコジ施政を痛烈に皮肉り、2人の舌戦は激しさを増している。
移民2世でエリート主義を嫌うサルコジ氏は、テレビで国民に直接語りかける政治姿勢が持ち味。2月15日の出馬表明後、集会やメディアとのインタビューなどを精力的にこなし、これが功を奏している。
オランド氏はエリート官僚を養成する国立行政学院(ENA)出身で、約10年間にわたり社会党を率い、調整力に定評がある。スクーターで仕事に通う庶民派でもある。だが、閣僚経験がないことなどもあり、大統領に選ばれた際の指導力には疑問がつきまとう。長年の党務の経験から「党官僚だ」との批判も上がる。
◆「赤」ではない
債務危機で欧州経済の悪化が懸念される中、両候補とも雇用対策などに力を入れるが、その手法は、サルコジ氏が企業の競争力重視であるのに対し、オランド氏は社会党に伝統的な所得再配分に比重を置く。
サルコジ氏はもともと、社会保障重視など国家の介入が伝統的に強いフランスの社会に米英型の自由競争を取り入れることを目指してきた。2007年の前回選挙で掲げたスローガンは「過去との決別」だ。
任期中は激しい抗議デモにも屈せず年金受給開始年齢引き上げを実行した。だが、金融危機や欧州債務危機の対応に追われ、成果を評価する声は少ない。
銀行や大企業への増税を掲げ、「大きな政府」を指向するオランド氏は「金融界は敵」とも訴え、経済・金融界からは懸念が上がる。年収100万ユーロ(約1億1千万円)を超える高額所得者への75%の課税は国民の支持を受けたものの、批判も強い。このため、オランド氏は自身について「『赤』ではなく、『ピンク』だ」と釈明、懸念払拭を図っている。
接戦の中、双方の競い合いは内向きになりがちで、サルコジ氏は不法移民対策強化のため、欧州の自由往来を定めたシェンゲン協定見直しを主張、ドイツ政府が不快感を示す一幕もあった。オランド氏は欧州連合(EU)の新財政協定を「幻想だ」と切り捨て、経済成長のための見直し論を一層強める。両者の戦いは欧州全体にも影響を与えかねない。【3月21日 産経】
**************************