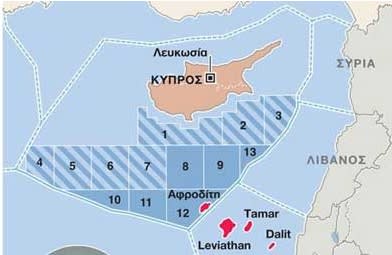(1月の入国トラブルの後、2月末再来日して都内で記者会見するアンワル元首相【2月28日 時事】)
【捜索難航「レーダーはコンテナの他、鯨やイルカを感知した」】
未だ消息がわからない“消えたマレーシア航空機”については、オーストラリア・アボット首相が公表した“マレーシア航空機と関連があるかもしれない二つの物体”を中心にした捜索が続けられています。
現段階では成果は得られていませんが、“捜索に詳しい関係筋によると、衛星画像に写し出された物体が不明のマレーシア機かどうか判明するには「数日」かかる可能性があるという”【3月21日 ロイター】とのことです。
****マレーシア機:豪の捜索で発見できず インド洋南部の物体****
衛星写真で消息不明のマレーシア航空機の残骸の可能性がある物体が発見されたインド洋南部で21日、豪空軍機などによる捜索活動が続けられたが、発見には至らなかった。
豪海上保安局(AMSA)によると、この日の捜索には豪空軍や米海軍の哨戒機計4機の他、民間航空機1機、民間の商船2隻が参加。
AP通信によると、同局報道官は「天候は回復し、視界も良くなっている」と話した。だが、現場は豪西部パースの南西約2300キロの海上で、パースとの往復を除くと航空機が現場付近で活動できる時間は2~3時間しかない。
一方、捜索範囲は2万3000平方キロに及び、洋上には多数のゴミが漂流している。捜索に参加したニュージーランド空軍のヤードレー准将はAFP通信に「レーダーはコンテナの他、鯨やイルカを感知した」と語り、捜索の困難さを強調した。
アボット豪首相は訪問先のパプアニューギニアで、「真相を究明するため、できることは全てやる」と記者団に語った。現場海域は数千メートルの深さ。機体が発見された場合に引き揚げを担う豪海軍の艦船は22日に到着する。【3月21日 毎日】
********************
それにしても“豪西部パースの南西約2300キロの海上”というと、日本を中心にした見慣れた世界地図では、一番南(下)のあたり、“何もない”ような海域で、憶測されているようなハイジャック等によって意図的に向かったとすれば、“どうしたまた、こんな方向に?”と訝しく思われるようなエリアです。
詳細は今後の捜索活動を待つしかありません。
【アンワル氏の挑戦を阻む同性愛疑惑】
ミステリアスな事件の展開から、ハイジャック説を含め、多くの諸説が囁かれていますが、その中のひとつに、マレーシア政治情勢と絡んだザハリ機長の「自殺説(ジハード)」があります。
そもそも、マレーシアに関する国際的ニュースにといえば、最近では、野党を束ねて長期政権打倒の挑戦を続ける野党政治家アンワル氏の動向が中心でした。
マレーシア航空機の事故直前にも、そのアンワル氏の挑戦が“同性愛疑惑”という怪しげなもので危機に瀕しているというニュースがありました。
イスラムの影響が強く、同性愛が法的に禁止されているマレーシア社会にあっては、“同性愛疑惑”は政敵を葬り去る手段ともなりえます。
****マレーシア:同性愛事件、元副首相に逆転有罪****
マレーシアで野党連合を率いるアンワル元副首相(66)が2008年に事務所スタッフの男性に「同性愛行為」をしたとして異常性行為罪に問われた事件の控訴審で、マレーシアの上訴裁判所は7日、無罪とした1審判決を取り消し、有罪判決を言い渡した。
アンワル氏は現職の下院議員。マレーシアのメディアによると、今後収監されれば、失職する可能性がある。
アンワル氏は1998年に政治腐敗を批判して、当時のマハティール首相と対立し失脚。別の「同性愛行為」と「権力乱用」の罪で有罪を言い渡され、約6年間服役した。【3月7日 毎日】
******************
上記記事にもあるように、アンワル氏は1999年4月14日、汚職の罪で懲役6年の有罪判決を、また、2000年8月8日には、同性愛の罪で懲役9年が言い渡されて収監されています。
2004年9月2日、最高裁判所はアンワル氏に下されていた同性愛の罪状を覆す判決を出し釈放されたものの、刑期が終わった後5年間は政治活動を行うことが禁止しているマレーシアの法律によって、表立っての政治活動再開は2008年4月15日からとなっています。
しかし、政治活動開始直後の2008年7月16日、再び同性愛容疑で逮捕されます。この時は翌日に釈放され8月補選で当選し、政界復帰を果たしています。
この2008年の同性愛容疑の裁判の方は、2012年1月9日、高等裁判所は同性愛容疑について無罪を言い渡しました。
2013年5月の総選挙では野党連合を率いて政権交代を目指しましたが、得票率で与党を上回り、大きく議席を伸ばしたものの、過半数獲得・政権交代には至りませんでした。
そして、上記記事にあるように、2014年3月7日、上訴裁判所は同性愛容疑について、一審の無罪判決を覆して有罪判決を下しています。
この上訴裁判所による逆転有罪の直前には、最大自治体の知事にあたるポストを足場に、次期総選挙での政権奪取をめざすアンワル氏の意欲的な戦略が報じられていました。
*****「政権奪取へ州首相目指す」 マレーシアのアンワル元副首相****
マレーシアの野党指導者アンワル・イブラヒム元副首相(66)は27日、都内で朝日新聞記者と会見。首都近郊に位置する最大州のスランゴールで来月、州議会議員の補選に立候補し、州首相をめざす考えを明らかにした。最大自治体の知事にあたるポストを足場に、次期総選挙での政権奪取をめざすという。
アンワル氏は別の州で選出された国会議員だが、兼職は禁じられていない。
スランゴール州は野党連合の地盤。同氏が補選で当選し、議会で州首相に選ばれる可能性は高い。同州は同国の人口の約5分の1を占め、製造業を中心に日本企業も多数進出している。
アンワル氏は「外国投資が集まる最大自治体を、腐敗がなく効率的な政権運営のショーケースにすることで、ナジブ政権に圧力をかける」と話した。
マレーシアでは1957年の独立以来、現在の与党連合が政権を維持している。昨年の総選挙は初の政権交代があるかどうか注目されたが、野党は得票率で上回りながら議席では与党を下回った。
最大9倍を超す一票の格差に加え、野党は大規模な不正があったと抗議しているが、選挙直後を除き、他の新興国のような大規模な街頭活動は展開されていない。
同氏は「次回の総選挙で必ず勝てると信じているからだ。選挙制度改革は必要だが、今の制度でも得票率が55%を超えれば、野党の議席が上回る」と語った。
アンワル氏は1月、笹川平和財団の招待で来日しようとしたが、法務省東京入国管理局が入国を拒否した。権力乱用の罪で有罪判決を受けたことがあり、必要なビザ取得の手続きを行わなかったためと日本政府は説明しているが、同氏は「日本政府の対応には不満だ。私と財団の双方が事前に問い合わせをして問題ないと言われた。このままだとマレーシアで『やくざと関係があるため』などとデマを流されるから、改めて来日した」と説明した。【2月28日 朝日】
*****************
今年1月に来日したアンワル氏の日本入国を法務省東京入国管理局が拒否した件については、昨年7月以降、短期滞在で訪日するマレーシア人はビザを取得する必要がなくなっていますが、「ただし、過去に犯罪歴がある場合は引き続きビザの取得が求められる。アンワル氏はこれに該当する」(大使館の広報担当者)とのことです。
日本側は、“事前に在マレーシア日本大使館から来日に問題はないと聞いた”とのアンワル氏側の言い分についても、「照会は確認されていない」としています。【1月21日 朝日より】
「2013年にマレーシア政府から日本に届いた『最新報告書』に基づく措置」とした日本側の当初の説明、両者の言い分の食い違いなど、もやもやした感じもある出来事でしたが、政権獲得に向けた具体的動きを示したアンワル氏に繰り返しかけられる同性愛疑惑については、非常にわかりやすい政治的策略の臭いがします。
アメリカ政府も“懸念”を表明しています。
****アンワル氏有罪に「懸念」=米****
米国務省のサキ報道官は7日声明を出し、マレーシアの野党連合指導者、アンワル元副首相が性的不品行罪(同性愛行為)で逆転有罪判決を受けたことについて「(マレーシアの)法の支配および司法の独立という点で懸念を生じさせる」と表明した。【3月8日 時事】
*******************
旧知のアル・ゴア元米副大統領がアンワル氏に電話をかけてきて、『非常に残念で、マレーシア政府や司法に落胆している』」と同氏を労わり、激励したそうです。【下記 JB PRESS】
今後は、上告した連邦裁(最高裁)で争われます。
【「自殺説(ジハード)」】
で、アンワル氏とマレーシア航空機との関連ですが、“消えたマレーシア航空機”のザハリ機長は、アンワル氏の熱心な支持者であり、上述のように政権獲得に戦略を“同性愛疑惑の逆転有罪”によって阻まれたことを悲憤して航空機もろとも自殺(ジハード)に及んだ・・・という説があるそうです。
機長がアンワル氏の支持者であり、アンワル氏とも面識があるのは事実ですが、それ以降の話については、野党・アンワル側は当然ながら否定しています。
****機長の自殺説について語るカリスマ野党指導者、アンワル・イブラヒム元副首相単独インタビュー(末永 恵)****
同性愛行為でのアンワル氏有罪判決に落胆した機長の”暴挙”?
・・・・そんな中、今“渦中の人”と、その言動や挙動に注目が集まっているのが、アジアで著名なマレーシアのカリスマ野党指導者、アンワル・イブラヒム元副首相(66歳)。
捜査線上に、ザハリ機長の「自殺説(ジハード)」が同機の有力な失踪原因として浮上する中、同機長が野党支持者で、かつ熱烈なアンワル支持者であることが判明。
しかも、MH370便が消息を絶つ前日の7日夜、マレーシア上訴裁判所でアンワル元副首相に対し、同性愛行為による禁固5年(連邦裁=最高裁にすでに上告)の有罪判決が下ったことにザハリ機長が大きな落胆を覚え、判決の数時間後にクアラルンプール国際空港を離陸した同機を道づれに自決したとも憶測されている。
有罪判決および同機失踪の後、日本のメディアでは初めて単独インタビューに応じたアンワル元副首相は、機長の自殺疑惑や自身との関係、マレーシア政府の対応能力、さらには今月23日に投開票が実施される首都近郊のセランゴール州議会補選や、4月の米オバマ大統領マレーシア訪問への期待などについて語った。
インタビューが行われたのは、アンワル氏が率いる野党連合のPKR(人民正義党)本部。
まず、マレーシア政府の危機管理体制やその対応について中国政府などから批判が上がっていることに対し、「マレーシア政府は、初動の情報開示から失態を繰り返した。ICPO(国際刑事警察機構)に盗難パスポートを利用した乗客の照会をせず、非常に重要な飛行ルート情報に関しても二転三転した」とした上、「国家機密の問題はさておき、非常に未熟でプロフェッショナルでなく、真実を述べていない。情報開示において透明性を欠いており、国際社会から疑いの眼差しで見られている」と非難。(中略)
その上で、「ザハリ機長がアンワルの支持者で、あたかも野党や私が今回の事件に“間接的”にでも関与しているとの疑惑をもたせるような捜索活動は、政治的な陰謀にほかならない」と事件への野党の関与を否定した。
さらに、「同機長は私の息子の妻側の遠戚で、何回か会ったことがある」と個人的に面識があることを明らかにした上で、「野党連合のPKR党員でマレーシアの民主化へ情熱を傾けていて、『moderate』(温厚な)な印象の人だった」とその人柄について語った。
また、7日の上訴裁判所での有罪判決の場にザハリ機長が姿を現していたという欧米メディアの報道を、「誰も彼を見なかった。彼は裁判所に来なかった」と否定した。
その上で、「原因究明が急がれる中、マレーシア政府が常套手段で野党指導者の私に謂われもない嫌疑をかけようとしている政治的な陰謀」と強調。さらに、「機長が他の多くのマレーシア国民と同様に、私の有罪判決に怒りを覚え、落胆したのは確かだ」としながらも、「それが、“ジハード”につながったとは思わない」と機長の自殺説を否定した。(中略)
その上で改めてアンワル氏は「私は無実」と、これまでと同様、容疑を否定した。また、上告した連邦裁の判決によっては、前回のように政治生命を絶たれることになるが、「米国政府などがマレーシアの連邦裁を調査、監視しており、さらに今回のMH370便の事件で世界が注目する中、これまでのように法を欺くような行動は取れないだろう」と発言。
上訴裁判所による同性愛行為への有罪判決についても、「DNA鑑定や物的証拠ですでに一審で無罪判決だったのだから、司法は政府の圧力に屈することなく、法の下の平等に基づいて、粛々と判決を下すべきだ」と第一審での無罪判決を不服とし、上訴裁に上訴した政府への圧力に屈すべきでないと訴えた。(後略)【3月20日 JB PRESS】
*******************
【政権獲得はできても、その後が大変】
アンワル氏は“元副首相”の肩書がしめすように、以前はポスト・マハティールの最右翼と目される与党内の有力政治家でしたが、1997年のアジア通貨危機の対応策のあたりからマハティール元首相との確執が表面化し、ついには職を追われ、同性愛疑惑で逮捕されることになります。
アンワル氏の政治的手腕については知りませんが、マレー系・中華系、インド系の他民族複合国家であるマレーシアにおいては政党も民族ごとに分かれており、中華系左派からマレー系イスラム原理主義政党までを取り込んだ民族的にも政策的にも多様な野党連合を束ねていくことは並大抵のことではありません。
政権獲得までは、長期政権打倒という一大目標で結束できても、政権獲得後の実際の政治運営がうまくいくのか・・・大きな不安は感じます。
ただ、そうしたアンワル氏の可能性・不安はともかくとして、政敵をスキャンダルで葬り去ろうとするのが与党側の対応であるなら(もちろん、与党側は“司法判断であり、政治は関係ない”としていますが)、何とも情けない話であり、早急に政権交代が実現されるべきでしょう。