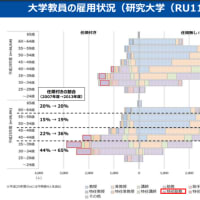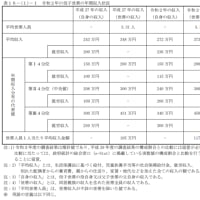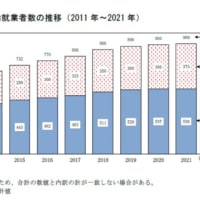8月末ごろ、ネットで知り合った知人からお子さんの「夏休みの宿題」について、アドバイスを求められた。
なんでも、夏休みの宿題の作文が書けずに困っているらしい。
終わっていないのは、作文だけではなく読書感想文もある、というメッセージがきた。
気心の知れている方なので、私からいくつかのアドバイスを書き出し、メールで送信をしたのだが、どうやら学力的な問題ではなく、文章を書くのが苦手、という方は案外いるのかな?と、その時感じたのだった。
その後も、違う方から「文章を書くのって、苦手」と言われたので、同様のアドバイスをしたのだが、その時「作文教室」を開いてくれればいいのに…と、冗談なのか本気なのかわからない言葉を頂いた。
考えてみれば、「文章を書く」という作業は、案外大変な作業だ。
頭をフル回転させ、言葉を選び、文と文を繋げ、話を創っていくのだ。
では、何故文章を書くコトに対して、苦手意識を持ってしまうのだろう?と、考えると「最初から、良い文章を書くことを目指している」からなのでは?という気がしたのだ。
「良い文章とは何か?」と問いかけると、多くの人は「わかりやすい文章」だと答えるだろう。
では「わかりやすい文章とは?」と、掘り下げると「平易な言葉で書かれている」と言われる方は多い。
ということは「良い文章」とは、「平易な言葉で書かれている文章」ということになる。
ところが「良い文章」と言った時、ある一定数の方は「難しい言葉を使っている」とか「流行りのカタカナを使っている」というような、イメージを持たれているように感じている。
「読書は好きだけど、文章を書くのが苦手」という方も、「書かれている文章と文章の間にある、作者の思いや考え」を掬い取ることができれば、「読んだ本に対して、何を感じ・共感をし・あるいは疑問に思ったのか?」ということが、読書と同時進行で頭の中で整理されている。
それをアウトプットする作業が、「読書感想文」なのだ。
「面白くない」とか「作者に共感できない」と感じ・思うことは自由だし、そこに正解はない。
問題なのは、「面白くない。共感できない」等、作品に対してネガティブな言葉を使うと、往々にして学校の先生は良い顔をしないし、評価も与えてくれない。
評価者である担当教員が付ける点数で、内申点等が決まってしまうので、自分の思いとは別の賞賛するような言葉を書かなくては!という、強迫的観念にとらわれてしまいがちになってしまい、それが結局「読書嫌い、作文嫌い」の要因になってしまうのでは?と、考えている。
ところで「平易な言葉」を、沢山見つけることができる場所が、身近にある。
それは、書店だ。
書店には、難しい言葉で書かれている専門書から、児童書や絵本までそろっている。
幼児教育として「読み聞かせ」をされる親御さんは多いと思うのだが、「読み聞かせ」の次のステップは、「自分で読んてみたい本を探す」ということなのではないだろうか?
その場所として、書店はぴったりな場所なのだと思う。
勿論、図書館でも良いのだが、図書館は静かに過ごす場所であって、「知識や情報のアウトプットの場」ではない。
「どこで、何を感じたの?」という、問いかけを重ねることで、その本を読んだお子さんの中に「読書の楽しさ」とは別に「読書の奥深さと、自分の思いを伝える」を実感するのでは?
「問いかけがしやすい」という場となると、図書館よりも書店の一角のザワザワとした周囲の中で、過ごすことの方が、本から得られる情報とは違うモノも得られるのでは?と、考えるのだ。
書籍のデジタル化やAmazon等の書籍通販等の充実により、今や町の本屋さんは風前の灯となっている。
しかし「書店」の存在そのものが、その街の文化や情報の発信地であり、学びの場だと視点を変えることで、町の本屋さんの存在は全く違う物になっていくのでは?
知人から声を掛けられた「作文教室」のコトを考えながら、どんな場所だったら子ども達が文章を書く楽しさを体験できるのか?と思いめぐらしたとき、「町の本屋さん」の存在に、改めて気づいたのだ。
最新の画像[もっと見る]