
1本の山桜を目指して山道を歩いた。
シャガの花が咲き、ヤマブキが黄色く点々と道沿いに映える。落下の椿が赤い。ここでもオニグルミの冬芽はほころびかけていた。
雲ケ畑へと通じる道なのだが、昨日は“この桜”を目的に、それは市中の花見の喧騒を避けたい思いにも重なるが、身も心もかいほうだぁと自然を満喫した。


ハルノ宵子さんの『隆明だもの』が、吉本隆明への関心を小さく呼び起こしてくれている。
『最後の親鸞』の編集に携わった春秋社の“名編集人”小関直さんへの追悼や思い出話にも触れた。
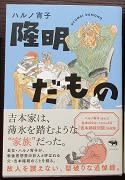

中島岳志氏の話が記憶にある。
オウムによる地下鉄サリン事件が3月にあって、その年の夏ごろ開催の講演会に参加したときのことが書かれてあった。
当時、吉本氏は麻原彰晃の思想を一部評価した過去の文章を巡って、パッシングを受けていた。
生意気な20歳だった。「『親鸞は悪人正機説を説いたが麻原も往生できると言うでしょうか』と質問用紙に書いた。どうせ答えない、答えられないと思っていた。
けれど質問を読み上げて、少し間を置くと「往生できるでしょう」と答えた。
極めて誤解を受けやすい話にも真正面から全身で問に答える。理屈ではない、「思想家の凄み」にしびれた。態度に圧倒された翌朝、書店が開くと同時に『最後の親鸞』を買い、一気に読んだ。
という箇所をよく覚えている。
『吉本隆明 質疑応答集①宗教』の収録は、〈『最後の親鸞』以後 ■1977年8月5日〉
から始まっている。
吉本氏には一読者として傾倒する何人かの文学者がいたが、どう考えているかを切実に知りたい状況、事件においても見解は公表されず、沈黙したままだった。失望していった。そんな体験がひそかに決心させたという。
「わたしは、わたしを知らない読者のために、自分の考えをはっきり述べながら行こう」
「たとえ状況は困難であり、発言することは、おっくうであり、孤立を誘い、誤るかもしれなくとも、わたしの考えを率直に云いながら行こう」と。
「私の判断や理解の仕方を知ることができるはずである」
四方八方から、あらゆる質問が飛んできて、それに間髪入れずに答えていく。質問の趣旨が分かりにくいときは何度も問い返し、
「そうかだいぶ分かってきました。あなたの質問される核心が分かってきました」
と質問を解きほぐしていかれたと。

どこまで感応できるかは、それこそ読む人の「面々の御はからい」(『歎異抄』)。
こんな言葉も解説文に見いだす。
明日は寺子屋エッセイサロンがある。話して考えてみようかな。
自分の考え方が誤ることはあるだろう。でも誠実な態度で自分の意見、見解を述べる(書く)ことの大切さ、必要性。
相手の思いがどこにあるのか、わかろうとする想像力や聞く耳も求められることとか…。
〈大人だって未完なのだ〉。先日何かの案内文書で目にしたが、読み暮れて、空手で戻ってもそれでいいのだ、だったな。















