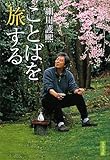http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/rare/pdf/017.pdf
現在当ブログで、【有吉家文書「年中行事抜粋」から花畑館を考察する】を書き始めたが、早速クレームを頂戴した。「絵図がないと判らん・・」
ご尤もなことで何とかせねばと考えていたところだが、熊本大学図書館のサイト「貴重資料」の「貴重資料展→平成12年度 第17回 永青文庫による細川家(藩)の大名屋敷 」のうちの「6-御花畑絵図」をまずは御覧いただけたらと思う。
(出来れば拡大してプリントアウトしていただければ幸いである。)
小さくて判りづらいと思うが中央にあるのが能舞台、その上に左から鷹之御間、佐野之御間、中廊下を挟んで中柱之御間(九曜之御間)と並ぶ。すこし雁行して歌仙之御間、鹿之御間((御座之間)、竹之御間(次之間)、陽春之御間、少し離れて右端に披雲閣が描かれている。但し、これが有吉文書と100%合致するかというと、そうではないから頭が痛い。
あくまで参考ということでご承知おきいただきたい。