「風説秘話」に次のような話がある。
西山大衛弟同傳喜不行跡ニ而一旦出奔せしか、後虚無僧と
成立帰り秘ニ大衛か許ニ居りしか、或時兄弟口論様せしか又深
巧有たるや、家の系圖を盗取出奔す、大衛方々手を延し
吟味せしに廻り役之者捕来、内々ニて大衛に渡したる故早速
手打したり、西山ハ家柄宜敷故系圖を盗他国ニ可有付巧な
り津らんとの風説也
足利道鑑の娘が小笠原備前家の初代・長之の後室となっている。その故を以て長之の二男が養嗣子として西山家の二代目となった。
大衛はその孫にあたる。名門であるが故にこのような事件は頭の痛いことであったろう。
■ 西山大衛 (南東8-1)
足利十三代将軍義輝
尾池玄蕃(足利道鑑)又(小池茂左衛門・入道道閑)
女:桜井兼友・正室 水無瀬兼豊養女(足利義辰・女)
女:小笠原長之・後室
西山左京・至之(尾池伝左衛門)
後・息勘十郎とともに「御家御断申、京ニ被相越候由」(綿考輯録・巻五十二)
細川忠利公御書出(寛永十五年)千石
細川光貞公御書出(寛永十八年)千石
西山勘十郎 細川忠利公御書出(寛永十五年)五百石
細川光貞公御書出(寛永十八年)五百石
1、八郎兵衛(勘十郎弟・山三郎氏房)
(1)人持衆併組外衆 二百七十九石六斗余 (真源院様御代御侍名附)
(2)二百七十九石 (真源院様御代御侍免撫帳)
(3)清田石見組・御番頭 千弐百七十九石六斗 (寛文四年六月・御侍帳)
(4)御番頭・清左衛門組 同上 (御侍帳・元禄五年比カ)
寛文四年一月(着座)~元禄六年六月(病死)番頭
細川忠利公御書出(寛永十八年)
細川光貞公御書出(寛永十八年)三百石
細川綱利公御書出(寛文元年)三百石
西山八郎兵衛加増知行所付目録(寛文元年)千石
2、九郎兵衛・道可(養子 実・小笠原備前長之二男 初・八郎兵衛・氏清)
千弐百七十九石六斗三合二勺八才 着座 屋敷・手取
元禄九年二月(着座)元禄十四年十一月 番頭(同役不和ニテ被差除)
細川宗孝公御書出(享保十九年)千三百石
3、多膳・氏政 享保十二年一月(着座)~享保十六年 番頭
4、大衛・氏章 比着座 千弐百七十九石六斗三合二勺八才 延享元子十月廿日
東山鹿苑院義政将軍ヨリ出
明和五年三月(着座)~安永五年一月 番頭
弟・傳喜

















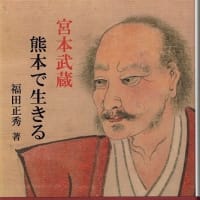







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます