北九州の小倉にお住いの、ソムリエの小川研次氏とは長いお付き合いとなった。
過去にも数々の論考を寄稿されたが、そのたびにお許しをいただき当ブログでご紹介してきたが、今般また、下記のような論考を寄稿された。
ここにご紹介を申しあげるとともに、改めて感謝申し上げる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サンクチュアリ(追記2) 北九州小倉 小川研次
船岡島という孤島に浮かぶ三つの寺の一つはガラシャの菩提寺秀林院である。
ここには「東の御花畑」があり、細川忠利が寛永5年(1628)2月朔日(1628年4月2日)に
夜更けまで過ごしたことは先述した。西暦では復活祭であることも留意したい。
寛永7年(1630)6月10日朝、「津川休閑」という人物が小倉に到着した。休閑は津川近利
(1582~1642)のことであり、伊予松平家の家臣であったという。(木下聡「斯波氏の動
向と系譜」『管領斯波氏』)
9月13日に小倉を離れたことから、およそ3ヵ月の滞在であった。(日帳)
近利の旅の目的は何であったのだろうか。
到着翌日11日には忠利から本丸、18日には「東の御花畑」で接待を受けている。(日帳)
実は忠利と近利には共通の目的があった。それは母ガラシャの命日(7月17日)と近利の父
義近の命日(8月16日)であり、ともに慶長5年(1600)に没している。
つまりキリスト教でいう没後30年記念追悼の年にあたる。
義近は斯波義銀(三松・1540~1600)のことで、尾張守護の家柄であった。
天正12年(1584)の小牧・長久手の戦の時に蒲生氏郷の麾下となり、伊勢で戦っていた。
(『管領斯波氏』)
氏郷との接点が重要である。氏郷は1585年、親友高山右近らの説得によりキリシタンとなり、
友人や家臣らにも勧め洗礼を受けさせている。
(「1585年8月25日付フロイス書簡」『十六・七世紀イエスズ会日本報告集第Ⅲ第7集』)
義近の受洗は伝わらないが、可能性はある。
天正15年(1587)6月、九州平定を終えた豊臣秀吉の博多箱崎での茶の席に「三松」の名が
散見される。21日後、「玄旨」(幽齋)と同席であった。(『神谷宗湛日記』)
しかし、天正18年(1590)6月末、小田原征伐の折、義近は北条父子の助命を行い、秀吉の
勘気に触れ、追放処分となった。(『管領斯波氏』)
天正19年(1591)12月5日付の氏郷宛の徳川家康書状に「三松不慮に其の地へ御牢人、何と
も御笑止(気の毒)に存じ候、定めて貴様も御同前たるべく候」(『桑田忠親著作集6巻
(徳川家康)』)とあり、義近は奥州会津の氏郷を頼ったのである。
文禄4年(1595)、氏郷が病床に臥した時、傍らには右近がいた。氏郷は「私は病気から回
復したら、太閤様に伴天連(神父)一名が伊留満(修道士)とともに自領に滞在し、キリス
トの福音を宣教する(許可)を願い出よう。(中略)自分の望みを達成するために、即ち全
領国がキリシタンとなるようにするためである。と語ったと右近がオルガンティーノに伝え
たのである。(「1595年2月14日付二エッキ・ソルド・オルガンティーノ書簡」『十六・七
世紀イエスズ会日本報告集第Ⅰ期第2巻』)
しかし、氏郷は同年2月7日(西暦3月17日)、敬虔なキリシタンとして没した。享年40歳で
あった。義近は氏郷との深い関係からキリシタンとなったと十分に考えられる。
近利も少年時代に受洗したとすれば、同時代の忠利と同じ身上となり、3ヵ月も滞在するほど
の親しさがあったと理解できる。
近利の実弟である津川辰珍(四郎右衛門)は細川家の家臣であり、頭衆として1250石を受け
ていた。(『於豊前小倉御侍帳』)元和9年(1623)5月の「25人扶持の賄米」(『日帳』)
など散見されることから、この頃に召し抱えとなったとみられる。
また、「津川数馬」(500石)もみられ、辰珍の養子次郎左衛門(近利孫)である。(同上)
寛永3年(1626)12月9日、忠利は足立の菊原五郎兵衛拝領の屋敷を訪ねたが、狭いので少
し拡張するように辰珍に伝えている。(『日帳』)五郎兵衛は「如庵」とみられ、長崎で藩
御用達の商人であった。(前出)著者はキリシタンとみて、足立の屋敷(後の広寿山福聚寺)
は忠利公認の「祈りの場所」であったと推測している。
寛永4年(1627)2月7日忠利は、江戸参勤前日だが、門司で「うなぎ十五」を調達させた。
翌日、門司から戻った辰珍は「殿様が肴に満足された」と報告している。(『日帳』)
西暦3月24日となり、「四句節」に肉食を避け、鰻を食したのであろう。
辰珍は「寛永旧九年津田三十郎へ七百石分知」とあり、1642年に分知していた。(「津田四
郎右衛門跡目配分」『新・保護細川藩侍帳』)
三十郎は織田信長の弟信包の孫にあたる。父は信重、母は津川義近の娘であり、叔父辰珍と
甥の関係であった。(『管領斯波氏』)信長の血筋は細川家で続くこととなる。
さらに興味深いのは大友宗麟ファミリーとの関係である。
宗麟二男の親家(大友道孝/ドン・サバスチャン)は忠興時代に小倉藩の客分になっていた
が、嫡男親英(織部)は江戸詰衆となり、忠利の側近となり活躍していた。この親英から四
代目にあたる四郎左衛門は津川家からの養子であった。辰珍の養子次郎左衛門の二男である。
(「新・肥後細川藩侍帳」)
義近は天正3年(1575)、東庵宗暾を開祖とした妙心寺塔頭の衡陽院を創建する。その後東
庵の弟子密宗宗顕により大嶺院としてさいけんされた。宗顕は明智光秀の叔父であった。
妙心寺に宗顕が建立した「浴室」(明智風呂)が今に伝わる。(大本山妙心寺)この大嶺院
(現大龍院)が義近の菩提寺とみられる。義近と近利の位牌と肖像画が安置されている。
肖像画の讃に寛永10年(1633)と記されており、近利が父を偲んで描かせたのだろう。
本来ならば、義近の法要は大嶺院で行われるべきである。しかし、近利・辰珍兄弟は小倉で
行わなければならない理由があったと考え、私見を述べる。
忠利は用意万端であった。キリストの御血である「正真の葡萄酒」と司祭中浦ジュリアンの
存在である。
母ガラシャの没後30年の祈念追悼ミサを7月17日に秀林院で挙行した。(7月「日帳」欠落)
一方、近利は8月16日に西の孤島「ため池」(小倉北区鋳物師町)で父の追悼を行ったと推
察する。それは、この日の「日帳」に「ため池」に立入禁止の札が建てるように、忠利は
「加々山権左衛門」に指示している。権左衛門はキリシタンであった。(『肥後切支丹史』)
高山右近の旧臣加々山隼人は叔父にあたり、後に細川家に仕えたが、1619年、小倉で殉教し
た敬虔なキリシタンであった(『日本切支丹宗門史』)
翌月の28日に忠利の命令により「ためいけへ、花坊所へ、明朝、人を通さないよう」として
いる。西暦では11月3日にあたり、キリスト教の「死者の日」であったと考えられる。忠興に
より処刑れた殉教者は元和元年(1618)だけで、殉教者37人に上る。特に、中津時代の忠利
の家老であったジョリアン久芳又左衛門は子供共々処刑されたのである。(『日本切支丹宗
門史』)忠利が江戸にいたときに起きた事件であった。
忠利は彼らへの魂救済のために祈りを捧げていたと信じたい。
「花坊」は「光成久兵衛」とみられ、ため池に在所していた。(『細川家家臣略系譜』)
翌年「花畠の寺」の掃除の前に先に行くよう命じられている。(寛永8年10月10日「日帳」)
「花畠の寺」はガラシャの菩提寺秀林院と思われ、西暦12月3日となり、キリスト生誕月であ
る。
「ため池」は大門の石橋と西の平松口を封鎖すれば、完全な孤島となる。
ここは「祇園社」や「茶屋」(別荘)もあり、細川家は度々訪問していた。
では、どこでキリシタンの行事は行われていたのだろうか。イエスズ会の記録「豊前第一の市
で、数多くのキリシタンが住んでいた小倉では、城壁の外の共同墓地にキリシタンのてによっ
て建てられた聖堂が焼き払われた。」とある。
(「1614年度日本年報」『十六・七世紀イエスズ会日本報告第Ⅱ期第2巻』)
著者はこの地域を「ため池」とみている。有力な候補地は「長円寺」(長圓寺)である。
聖堂や教会が破却された土地にはほとんど仏寺が建てられている。正保年間の『豊前国小倉城
絵図』には寺の名は無記名だが、現在と同じ地形で入口の通路が狭い。つまり、外部からの侵
入を防ぐには好都合である。この通路に隣接している所が「花坊の所」であったのではなかろ
うか。監視役も兼ねていたとも考えられる。また、長圓寺には古くから檀家の言い伝えに「ガ
ラシャが大事にしていたマリア観音があった」とある。(長圓寺ブログ)
ガラシャの最期の様子を伝える『霜女日記』に、霜は「内記様(忠利)への御かたみを遣わさ
れ候」(『綿考輯録巻十三』)とあるが、「御かたみ」は「マリア像」であった気がしてなら
ない。
さて、近利の3ヵ月に及ぶ滞在は充実した日々であったに違いない。
小倉を去るにあたって、忠利は上奉行として「赤尾茂兵衛」を指名した。(9月12日「日帳」)
茂兵衛は葡萄酒製造に仕える者であった。(寛永5年9月15日「日帳」)
寛永9年(1632)7月17日、「秀林院様三十三年之御忌に当たるので、豊前にて大法会を御執行」
したのである。(『綿考輯録巻二十二』)仏教式の「年忌明け」である。
同年末、肥後へ転封となった忠利は安国寺の明巌梵徹和尚(明智光秀息と伝わる)を同道しよ
うとするが、条件を付けられていた。秀林院を建立するか、安国寺を建てるか。
しかし「キリスト教は禁教となっていたため、秀林院を許さず、安国寺を建てて梵徹を招いた」
という。(細川護貞氏著『魚雁集』)当時、秀林院をキリシタンの象徴としていたのである。
奇しくもガラシャの死(1600年)から32年間、その御霊を祈り続けた地が豊前小倉藩領であった。
現在、秀林院の跡地は北九州市立医療センターや総合保健福祉センターが建っており、中心に位
置している市立看護専門学校の教育理念は「生命の尊厳と人間愛を基盤として、人々の健康と幸
せに貢献する看護実践者を育成する。」(同HP)とある。
また、偶然にも医療センターの壁の上には十字のステンドグラスが埋め込まれている。
ガラシャの愛に満ちたサンクチュアリなのかもしれない。
(了)














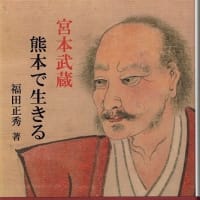










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます