陸尺(六尺)とは、輿(こし)や駕籠(かご)を担ぐ人足のことをいう。いわゆる駕籠舁(かごかき)のことで、大名家に於いては御駕籠者といわれる。先にご紹介したサイト「古文書で読む参勤交代」にある「大名行列絵図」 http://www.ab.auone-net.jp/~xe2918/ezu/ を見ると、藩主の駕籠は前後六人の陸尺によって担がれている。しかしよく見ると交代要員が残り18人ぐるりと駕籠の後からついてきている。次から次に四交代で担いだということであろうか。陸尺(六尺)とは、力者が転じたものというが、身長が六尺とかいうことも関係しているのではないか。ちなみに「陸」とは建築用語にもあり、「ろく」とよませて水平である事を意味する。
井上ひさしの著書に、「おれたちの大砲」という面白い小説が有る。
将軍様の尿筒役に草履持、髪結に駕籠の者、馬の爪髪役という、下役の若者五人が徒党を組み、公方様の危機を救うべく大計画をひっさげて、横浜から京都、江戸へと進んでいく・・という話だが、ここに登場する茂松という駕籠の者の話が可笑しい。(他の四人も同様だが・・)
家は代々、西丸駕籠之者(45人)の頭に次ぐ家格で、五十俵五人扶持である。ところが今は町の駕籠かきふぜいに落ちぶれて、先の五人組に入り込んだ。落ちぶれの原因は彼の身長の寸たらずである。家は相撲取りあがりの妹婿が継いだ。
細川家の御駕籠者とて同様のことであったろう。六尺の大男を24人集めようとは大変な事である。代々の家柄ではなく、選抜されて御駕籠者に採用されたのではなかろうか?
熊本市の中心部の駕籠町通りは、藩政時代御駕籠者が住まい(30数軒?)した所である。今では六尺の大男に代わり、若者たちが闊歩するアパレルや飲食店などが建ち並ぶ町である。
井上ひさしの著書に、「おれたちの大砲」という面白い小説が有る。
将軍様の尿筒役に草履持、髪結に駕籠の者、馬の爪髪役という、下役の若者五人が徒党を組み、公方様の危機を救うべく大計画をひっさげて、横浜から京都、江戸へと進んでいく・・という話だが、ここに登場する茂松という駕籠の者の話が可笑しい。(他の四人も同様だが・・)
家は代々、西丸駕籠之者(45人)の頭に次ぐ家格で、五十俵五人扶持である。ところが今は町の駕籠かきふぜいに落ちぶれて、先の五人組に入り込んだ。落ちぶれの原因は彼の身長の寸たらずである。家は相撲取りあがりの妹婿が継いだ。
細川家の御駕籠者とて同様のことであったろう。六尺の大男を24人集めようとは大変な事である。代々の家柄ではなく、選抜されて御駕籠者に採用されたのではなかろうか?
熊本市の中心部の駕籠町通りは、藩政時代御駕籠者が住まい(30数軒?)した所である。今では六尺の大男に代わり、若者たちが闊歩するアパレルや飲食店などが建ち並ぶ町である。

















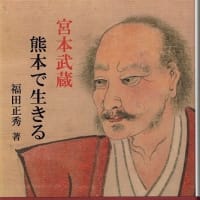







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます