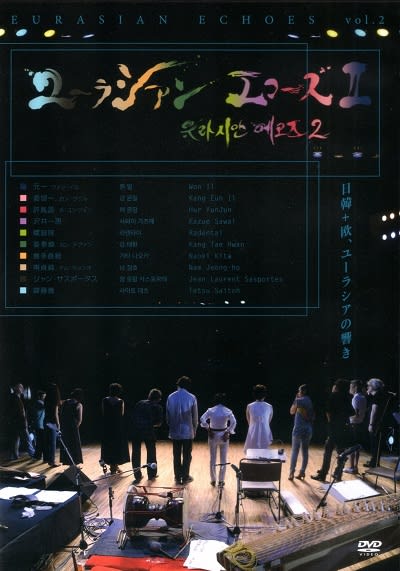デューク・エリントン『Hi-Fi Ellington Uptown』(CBS、1951-52年)を聴く。

Clark Terry, Willie Cook, Shorty Baker, Ray Nance, Francis Williams、Cat Anderson (tp)
Juan Tizol, Quentine Jackson, Britt Woodman (tb)
Jimmy Hamilton (cl, ts)
Willie Smith (as)
Hilton Jefferson (as)
Russell Procope (as, cl)
Paul Gonsalves (ts)
Harry Carney (bs, bcl)
Duke Ellington, Billy Strayhorn (p)
Wendell Marshall (b)
Louie Bellson (ds)
Betty Roche (vo)
普段あまりエリントンのビッグバンドには縁がないのだが、たまに聴くと芸達者な面々のプレイとぶあついサウンドに痺れる。
すでにモダンジャズ勃興期ではあっても、当然、スイングの尻尾(というか本体?)も見え隠れする。ルイ・ベルソンの前のめりなイケイケのスイング・ドラムスなんて燃えるじゃないか。クラリネットやトランペットのアンサンブルもドヤ顔が見えるようでとても良い(なかでもクラーク・テリーはスカしている)。
そしてエリントン楽団の顔のひとり、ポール・ゴンザルヴェス(よく居眠りしていたそうだ)。この塩っ辛いテナーの音は、コールマン・ホーキンスに共通というより、メローなソフトフォーカスの歌謡曲。イガイガして亀の子たわしのようだ。
「Take the "A" Train」でのみ歌っているベティ・ロシェのスモーキーな声も良い。なんでも、美空ひばりはこの録音を聴きこんで自分のものにしたのだそうである。そういえば、美空ひばりのジャズもしばらくご無沙汰している。また聴いてみようかな。
●参照
デューク・エリントンとテリ・リン・キャリントンの『Money Jungle』
デューク・エリントン『Live at the Whitney』