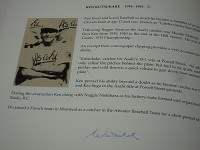石井裕也『バンクーバーの朝日』(2014年)を観る。

実際の「バンクーバー朝日軍」の歴史をもとにした映画である。
1900年代初頭、出稼ぎのためカナダに渡った日本人は、「バンクーバー朝日軍」という野球チームを結成する。かれらは、厳しい労働と生活の合間に練習に明け暮れた。地元のリーグでの試合は、身体の大きな白人に圧倒されていたが、やがて、バント、相手打者の癖の分析と細かな配球、盗塁などによって、次第に屈指の実力チームへと成長する。朝日軍のきめ細かな野球は「Brain Baseball」と呼ばれた。しかし、戦争が激化すると、日本人移民は適性国民と位置付けられ、収容所に強制的に入れられることになる。移民たちが自由を取り戻すのは、1949年になってからのことであった。
主演の妻夫木聡の演技には味わいがある。亀梨和也の出演は、明らかに野球の腕前を買われてのことだろうけど、裡に想いをためるような演技もまた良い。観る前に心配していたのは、ヘンに憎しみをたぎらせた者が出てきたり、過度に悲惨な目に遭う者が出てきたりするナショナリズム高揚映画になってはいないかということだったが(要は、漫画化された『バンクーバー朝日軍』を描く原秀則の作風がそうだということ)、それは杞憂だった。
ところで、映画では、朝日軍はあまりにも非力でヒット1本すら打てないため、バントを多用したことになっている。パット・アダチ『Asahi: A Legend in Baseball』、テッド・Y・フルモト『バンクーバー朝日軍』によると、確かにバントも積極的に使い、いまの「スモール・ベースボール」的であったが、ここまで非力ではなかったようだ。普通にゲームに勝ち、たまにはホームランを打つこともあったようだ。
パット・アダチ『Asahi: A Legend in Baseball』には、次のような新聞記事が紹介されている。地元の興奮ぶりが想像できる。
「(略)其間に北川又二塁へ走り何のことはない球が人間より遅い為め朝日は安打なくして三、二塁を奪ひ得たのである、次にバツトを握つたは中村兄二回目のバントが成功して山村本塁に突進、ホ軍は大狼狽を始めて中村を一塁に生かし二塁をお留守にして盗まれて了ふ、・・・・・・」
遠征に来た巨人軍と試合をしたこともあったようだ。2試合とも完敗してはいるものの、それだけの実力があったということだ。なお、試合には、あのスタルヒンが投げてもいる。また、帯同していた沢村栄治はこの2試合には登板していないが、練習で朝日軍の選手相手に投げ、球の速さを印象付けている。
上の本によれば、強制収容所においても、朝日軍の面々は野球場をつくって試合をしたという。また、解放後チームは二度と結成されなかったが、あちこちで野球を続けたともある。巨人軍との試合はともかく、このあたりは映画でも描いてほしかったところ。
現在では、野球は労働移民のシステムを構築している(石原豊一『ベースボール労働移民』)。バンクーバー朝日軍の活動は、その前史のひとつでもある。





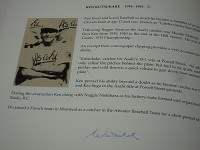

選手たちの写真と署名(パット・アダチ『Asahi: A Legend in Baseball』)
●参照
パット・アダチ『Asahi: A Legend in Baseball』、テッド・Y・フルモト『バンクーバー朝日軍』
石原豊一『ベースボール労働移民』、『Number』のWBC特集