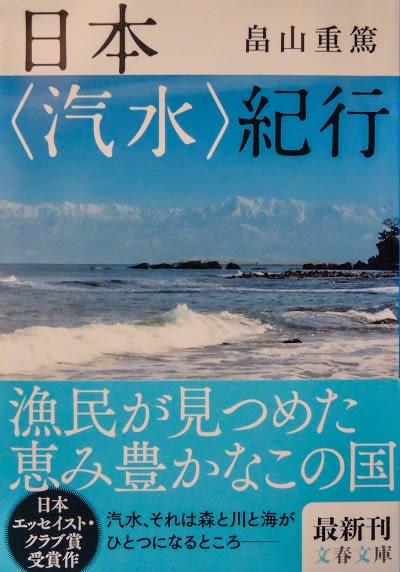NHK・Eテレの『こころの時代』枠で放送された『沖縄でコルヴィッツと出会う』(2015/8/30)を観る。
ケーテ・コルヴィッツは20世紀前半に活動したドイツの版画家。第一次世界大戦において出征した息子を亡くし、嘆きながら、同時に美を見出し、獣のように慟哭する母親の姿を版画作品として結実させた。沖縄・普天間基地の敷地を取り戻して「佐喜眞美術館」を造った佐喜眞館長のコレクションの出発点は、この作品である。というのも、もともと普天間に持っていた土地を米軍に奪われた佐喜眞家には、軍用地料が入ってきて、館長はそのことを不快としてアートの購入を始めたのだった。
場所も時代も違うコルヴィッツの作品が、なぜ現代の沖縄で力を持ちうるのか。徐京植さんは、かつての出来事としてではなく、自らのリアルなこととして描いたことによるのではないかと考える。徐さんにとってのコルヴィッツは、民主化運動に対する白色テロ・光州事件(1980年)であり、また、民主化運動に参加して投獄されたふたりの兄(徐勝・徐俊植)であった。徐さんが橋渡しをして、ソウル北美術館において、佐喜眞美術館所蔵のコルヴィッツ作品が展示された。
コルヴィッツの普遍性がつなぐ先は韓国だけではない。コルヴィッツと同時代に、魯迅も彼女の作品に共鳴し、中国で作品を紹介していた。藤井省三『魯迅』によれば、『世界史のなかの中国 文革・琉球・チベット』を書いた汪暉が沖縄と北京魯迅博物館をつなぎ、展覧会を実現させた。また、杭州の浙江美術館でもまた展示がなされている。(魯迅が生まれた地は、浙江省の紹興であった。)
被抑圧からの解放への希求を紐帯として、沖縄、韓国、中国がつながるという姿は希望を、孕むものではないか。その視線は、『越境広場』、シンポジウム『アジアの中で沖縄現代史を問い直す』などにも見ることができる。もっとも、そういった言い方自体が第三者的でもあるのだが。
●参照
佐喜眞道夫『アートで平和をつくる 沖縄・佐喜眞美術館の軌跡』
佐喜眞美術館の屋上からまた普天間基地を視る
<フェンス>という風景
基地景と「まーみなー」
平和祈念資料館、「原爆と戦争展」、宜野湾市立博物館、佐喜真美術館、壺屋焼物博物館、ゆいレール展示館
汪暉『世界史のなかの中国』
汪暉『世界史のなかの中国』(2)
藤井省三『魯迅』
徐京植のフクシマ
徐京植『ディアスポラ紀行』
高橋哲哉・徐京植編著『奪われた野にも春は来るか 鄭周河写真展の記録』
鄭周河写真展『奪われた野にも春は来るか』
鄭周河写真集『奪われた野にも春は来るか』、「こころの時代」
『越境広場』
シンポジウム『アジアの中で沖縄現代史を問い直す』