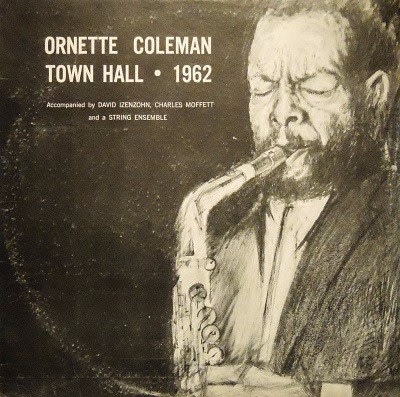大久保の「ひかりのうま」に初めて足を運んだ(2017/4/7)。
大久保駅改札からすぐ近くの筈なのに、ぜんぜん場所がわからない。メイド喫茶の勧誘と思しきメイドふたりがよろよろしていて、それは違う。泥酔したお爺さんふたりがよろよろしていて、そこも違う。裏の路地に回ってみたが、惹かれる沖縄料理店があるくらい。お店のサイトにはキューピットを目印にとあり、人形があるものかと探していたのだが、よく考えたらそれはキユーピー。ようやく見つけたところで橋本孝之さんが現れて、確かに分かりにくいと笑っていた。(ところで橋本さんによれば、その沖縄料理は安くて結構旨いそうである。)
第三回天下一Buzz音会 -披露”演”-

■ 今井和雄 x Shogo Haraguchi
この会の企画・司会を務める原口さんは、この後に出る目秦さんとともに、グループ・gaiamamooにて活動している。以前に新宿西口で白石民夫さんが吹いたときにその場にいて知り合った。かれらの演奏をようやく観ることができて嬉しい。
今井和雄さんは最初から鎖を使い、轟音に轟音を重ねる。もちろんアマウント圧倒ではなく微かな音も轟音に偽装して現れてくる。あらゆる音が、目眩を覚えていられないほどの速度で提示される。音に愛想などはない。そしてHaraguchiさんもベースとペダルで退くことなく音の壁に音をぶつけ続ける。凄いものは凄いというトートロジーしか頭に浮かばない。
今井和雄 (g)
Shogo Haraguchi (b, pedals)


■ ヒグチケイコ x Hiroshi Mehata
ヒグチケイコさんはずっと聴きたい存在だった。
gaiamamooのMehataさんがエレクトロニクスを操りヴォイス、ギターとともに創出するアンビエントな音空間。これにより観る者の脳は既に麻痺させられ、やすやすと武装解除されてしまっている。なお、これを含め最初の3ギグで投影される映像もMehataさんの手による。
ヒグチさんのヴォイスもピアノも、無防備になってしまった粘膜に直接びしびしと付着する。伏屋佳代さんの表現を引用するなら、その直接性はまさに「一瞬にして酷薄に反転しかねないこそ際立つ甘美」なのであり、恍惚としてしまう。どこに連れていかれるのだろうという感覚。
ヒグチケイコ (vo, p)
Hiroshi Mehata (electronics, vo, g)


■ 鈴木放屁 x 橋本孝之
やはり鈴木放屁さんも日本天狗党での活動により気になる存在、今回はじめてナマの演奏を観た。マウスピースを深く加え、ぐわっとでかくぶっといテナーの音。第一音に思わずのけぞってしまった。品とかなんとか呟いてんじゃないとどやしつけられたようだ。そして、どのような時空間でも生命を維持させる異形の音を発する橋本さんのアルト。
鈴木放屁 (ts)
橋本孝之 (as)


■ 組原正 x 多田正美
グンジョーガクレヨンの組原正にマージナル・コンソートの多田正美。今回の共演は組原さんからのオファーであったという。違う世界の異種格闘技なのか類は友を呼ぶのか。
多田さんはピアノに妙な仕掛けを施し、弾いたり跳躍したりしながら、足許に置いたシンバルをひたすら無表情で踏む。バックの荒れ地なのか野原なのかの映像も多田さんによるものである。無慈悲に放置されたような苛烈な感覚。そして女装した組原さんは強面の愛嬌をもってノイズを発し続けた。何なんだ。
演奏の前にご紹介いただいて、多田さんにお話を伺っていると、いやいやいやと仰天してしまう構想が多田さんの口から。ちょっと言えないのだが。
組原正 (g, vo, electronics)
多田正美 (prepared p, perc)

◆
そんなわけでひと組でも濃すぎるのに4バンドの轟音とノイズ、しかも地下空間は暑くて酸欠。チルアウトのために帰宅途中で飲まずにはいられなかった。
Fuji X-E2、XF35mm1.4、XF60mmF2.4
●今井和雄
齋藤徹+今井和雄@稲毛Candy(2017年)
Sound Live Tokyo 2016 マージナル・コンソート(JazzTokyo)(2016年)
広瀬淳二+今井和雄+齋藤徹+ジャック・ディミエール@Ftarri(2016年)
坂田明+今井和雄+瀬尾高志@Bar Isshee(2016年)
齋藤徹+かみむら泰一、+喜多直毅、+矢萩竜太郎(JazzTokyo)(2015-16年)
今井和雄 デレク・ベイリーを語る@sound cafe dzumi(2015年)
今井和雄、2009年5月、入谷
齋藤徹+今井和雄『ORBIT ZERO』(2009年)
バール・フィリップス@歌舞伎町ナルシス(2012年)(今井和雄とのデュオ盤)
●橋本孝之
内田静男+橋本孝之、中村としまる+沼田順@神保町試聴室(2017年)
グンジョーガクレヨン、INCAPACITANTS、.es@スーパーデラックス(2016年)
.es『曖昧の海』(2015年)
鳥の会議#4~riunione dell'uccello~@西麻布BULLET'S(2015年)
橋本孝之『Colourful』、.es『Senses Complex』、sara+『Tinctura』(2013-15年)
●組原正
グンジョーガクレヨン、INCAPACITANTS、.es@スーパーデラックス(2016年)
●多田正美
Sound Live Tokyo 2016 マージナル・コンソート(JazzTokyo)(2016年)