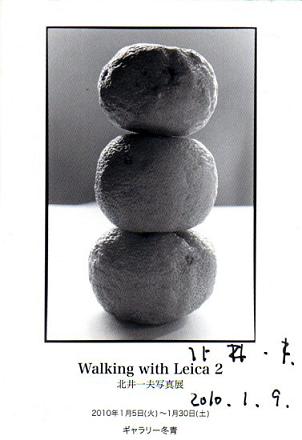年末年始には(たまたま、だが)、萩原朔太郎『猫町』(岩波文庫、原著1935年)と、それについての評論、清岡卓行『萩原朔太郎『猫町』私論』(文藝春秋、1974年)を読んでいた。後者は、札幌の古書店、書肆吉成で入手した。なお、現在では、筑摩叢書として復刊された版の方が入手しやすいようである。
世田谷文学館には、ムットーニによるからくり箱が収蔵されている(>> リンク)。何年か前に観て愉しい驚愕を覚えてから、いつか原作を読もうと思っていた。この現実から離れそうで離れることができない微妙な感覚が、だらしない正月休みにフィットするというものだ。

「私」は、ひなびた温泉街近くの駅で気紛れに下車する。道に迷い、気がつけば繁華街。ところが危ういバランス、張りつめた切実さ、凶兆といったアウラが濃厚となってゆき、突然の沈黙。町の街路にも、家々の窓口にも、猫の大集団がうようよしている。
このあたりの描写は凄まじく、H・P・ラヴクラフトさえも想起させる。(なお、ラヴクラフトは本当に怖いため、私は読みたいのにあまり読んでいない。) 深沢七郎や島尾敏雄の作品にも発狂してしまいそうな切迫感があったように思うが、いずれにしてもムットーニから想像するような人形劇独特の怖さなどを凌駕しており、とてもファンタジックとは言うことができない。
「町の特殊な美しさも、静かな夢のような閑寂さも、かえってひっそりと気味が悪く、何かの恐ろしい秘密の中で、暗号を交わしているように感じられた。何事かわからない、或る漠然とした一つの予感が、青ざめた恐怖の色で、忙しく私の心の中を馳け廻った。すべての感覚が解放され、物の微細な色、匂い、音、味、意味までが、すっかり確実に知覚された。あたりの空気には、死屍のような臭気が充満して、気圧が刻々に嵩まって行った。此所に現象しているものは、確かに何かの凶兆である。確かに今、何事かの非常が起る!起るにちがいない!」
清岡卓郎の評論においては、この作品を産み出した萩原朔太郎という人物について探っている。読みすすめるにつれ、資質的に社会生活から疎外されざるを得なかった詩人に、なぜか感情移入している自分を発見する。
朔太郎は、いわば田舎の金持のボンボンであり、金銭感覚に乏しかった。田舎では変人と蔑まれ、近代に、都会に、憧れた。結婚生活は、都会での放縦な暮らしの中で、悲惨な末路を辿った。夢見ていた欧州への旅を強行するほどの行動力はなく、朔太郎は、脳内での妄想・歪んだ内的世界への旅を肥大化させていった。(阿片やハッシッシが入手できないため)モルヒネやコカインさえも使っていた。
いまふうに言えばコンプレックスとして片付けられるのかもしれないし、このような芸術家はそもそも生きる場所を探すのにもっと困難に直面するかもしれない。実際に、田舎を激烈に憎み(このあたりは共感できなくもない)、かつ、その田舎の父からの仕送りで都会生活を送るという、どうしようもない男である。しかし、そうした朔太郎の屈折した個性が、『猫町』の世界に結実したのであった。
「かなしき郷土よ。人々は私に情なくして、いつも白い眼でにらんでゐた。単に私が無職であり、もしくは変人であるという理由をもって、あはれな詩人を嘲辱し、私の背後から唾をかけた。「あすこに白痴が歩いて行く。」 さう言って人々が舌を出した。」
清岡卓郎は、『猫町』に見られる切迫感が、朔太郎の内在的な「精神的な飢え」だけでなく、30年代という時代の圧迫も影響して産まれたものだとしている。中国への軍事侵略が本格化し、国内的にも2・26事件が起るなど騒然とした中で色濃くなる全体主義は、放縦な個性と相容れなかったのは明らかである。すなわち、突如として「私」が取り囲まれる「猫、猫、猫、猫、猫、猫、猫。」は、匿名・無個性の人間の集団でもあった、ということだ。
もっとも、社会や政治には全く無知無頓着であったというから、外的な要因があったにせよ、それらが精神と言葉の歪みとなってのみ顕れたという意味では、社会派などでは決してなく、やはり前衛と言っていいのか。