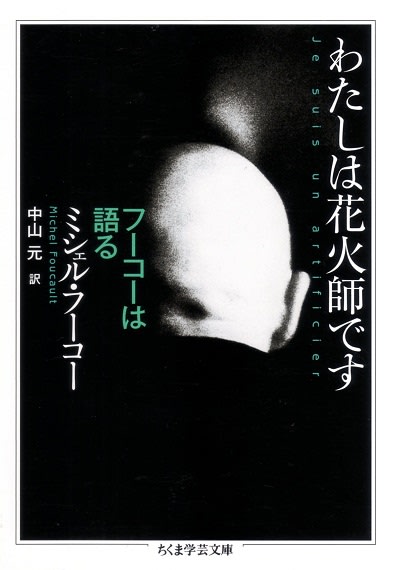マイラ・メルフォードのソロピアノ『life carries me this way』(firehouse、2013年)を何度も聴いている。

Myra Melford (p)
Don Reich (art)
ソロピアノとは言っても、裏面に記されている名前はふたり。2010年に亡くなった画家、ドン・ライヒの作品に触発された演奏集なのである。
ブックレットには11曲それぞれのタイトルを持つライヒの絵が収録されている。具象に近い抽象画であり、パステルなども使ったあたたかみのあるマチエールである。これらを凝視しながらピアノを聴くと、さらにイマジネーションが拡がっていくようだ。邪道の聴き方ではない。
メルフォードのピアノは昔から独自の曲想を持っている。これまで、ピアノトリオや管楽器とのコラボレーションばかりを聴いてきたが、そのことが、他者の勢いとの相乗効果もあって、尖って突き進むメルフォード像をつくりあげてきた。
ソロでもピアノは尖っている。まるで冷たい石を限りなく広い空間で鳴り響かせているようなときもある。しかし、同時に、聴けば聴くほど、さまざまな風景が出現してくる。
●参照
○マイラ・メルフォード『Alive in the House of Saints』 HAT HUTのCDはすぐ劣化する?
○ブッチ・モリス『Dust to Dust』(マイラ・メルフォード参加)
○ジョゼフ・ジャーマン『Life Time Visions』(マイラ・メルフォード参加)
○ヘンリー・スレッギル(5) サーカス音楽の躁と鬱(マイラ・メルフォード参加)