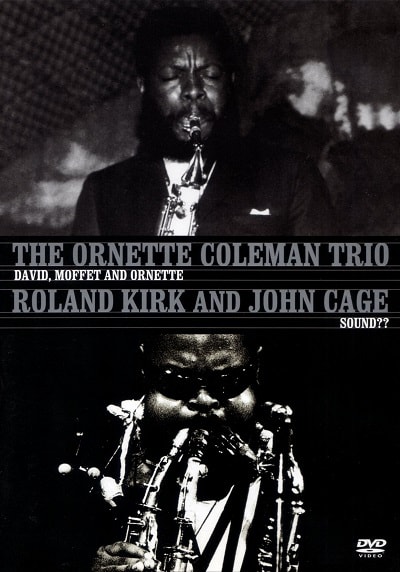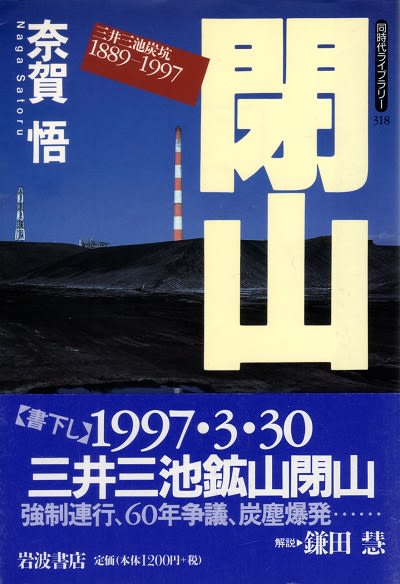市川光太郎『ジュゴンの上手なつかまえ方 海の歌姫を追いかけて』(岩波書店、2014年)を読む。

著者はジュゴンの研究者。日本には沖縄に極めて限られた数のジュゴンが棲息しているだけなので(+鳥羽水族館)、タイやオーストラリアといったジュゴンが多い地帯にフィールドワークに出ており、その研究成果を本書で紹介してくれている。(なお、沖縄には、辺野古近辺に父親が、反対の西側の古宇利島近辺に母親と子供が棲んでおり、その子供が西と東を行き来しているのだという。)
これが、自虐的な書きぶりも相まって、滅法面白い。何でも、ジュゴンは、夜明け前に、えさ場(海草)の外でのみ鳴き、その鳴き声は、短い「ぴよぴよ」の後に長い「ぴーよ」が付け足されるらしい。著者は、「ぴよぴよ」が注意喚起で、「ぴーよ」が仲間に伝えたいメッセージだと推測している。なるほど、ロマンチックな話である。
しかし、声のデータ採取は実に大変なもののようで、しかも、テッポウエビがつめを叩いて出すノイズの中から抽出するのだという。大変なのは声データだけではない。泳ぐジュゴンの横に舟をつけて複数名で飛び込み、ダメージを与えないよう捕獲し、データ取りをするというやり方も紹介されている。「好きこそ・・・」とはこのことだ。わたしなど生まれ変わってもジュゴン研究者にはなれまい。
本書には、「ジュゴン食い」についても言及されている。実際に、オーストラリアの一部ではいまも食べることがあるというし、辺見庸『もの食う人びと』(角川文庫)には、フィリピンでも最近までジュゴンを食べていたとある。柳田國男も、「肉ありその色は朱のごとく美味なり、仁羹(にんかん、人魚の肉)と名づく」と書いており、南方熊楠は「千六六八年、コリン著『非列賓(フィリピン)島宣教志』八○頁に、人魚の肉食うべく、その骨も歯も金瘡(切り傷)に神効あり、とあり」と書いている。また、八重山の新城島(あらぐすくじま)には、食べた後のジュゴンの骨を祀る「七門(ナナゾ)御嶽」があり、琉球王朝に献上していたジュゴンの干肉も残されている。(テレビ朝日『テレメンタリー2007 人魚の棲む海・ジュゴンと生きる沖縄の人々』、2007年) 沖縄本島でも、昔は「獲れてしまった」ジュゴンを食べていたよという話を聞いたことがある。
もちろん、ここで著者が食べたというジュゴンは、漁網にかかって死んでしまった後であり、そのことに問題はまったくない。むしろ、食べた結果、硬くて獣臭かったということには、読んでいて少しがっかりさせられた。
ところで、わたしは米軍基地の新設にも、環境アセスを真っ当に行わなかったことも、もちろん稀少なジュゴンの生態系を脅かすことにも、反対する。しかし、それが、基地に反対する手段としてのジュゴンの利用と感じられるときには、首をかしげてしまう。まずはジュゴンについて知るべし。わたしのような素人にはとても興味深く面白い本である。
●参照
池田和子『ジュゴン』
名古屋COP10&アブダビ・ジュゴン国際会議報告会
ジュゴンと共に生きる国々から学ぶ(2009年)
ジュゴンと生きるアジアの国々に学ぶ(2006年)
『テレメンタリー2007 人魚の棲む海・ジュゴンと生きる沖縄の人々』(沖縄本島、宮古、八重山におけるジュゴン伝承を紹介)
澁澤龍彦『高丘親王航海記』(ジュゴンが「儒艮」として登場)
タイ湾、どこかにジュゴンが?
二度目の辺野古
高江・辺野古訪問記(2) 辺野古、ジュゴンの見える丘