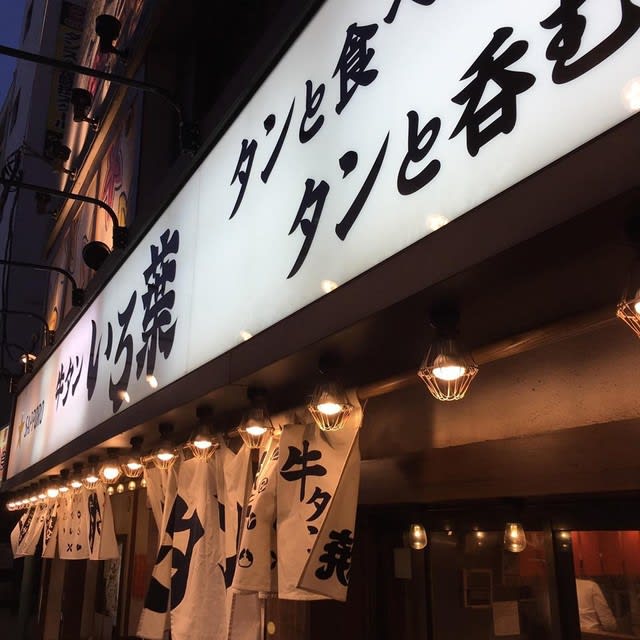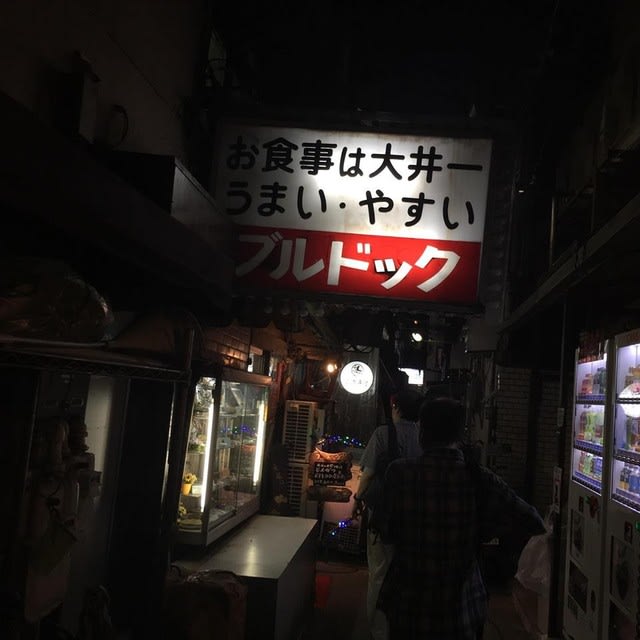本八幡のcooljojoで、西島芳のtriogy(2018/7/16)。

triogy:
Kaori Nishijima 西島芳 (p, vo)
Hiroshi Yoshino 吉野弘志 (b)
Yoshinori Shiraishi 白石美徳 (ds)
この3月に下北沢のApolloで観て素晴らしかったこともあり、5月にもと思っていたのだが、タイミング悪くわたしが入院してしまった。そんなわけで4か月ぶり、また観ることができてとても嬉しい。
西島さんの音楽には、淡い光の中で静かに佇むような独特な世界を垣間見ることができる。時間のあわいを大事に取り出したような感覚である。それがたとえば「Dawn」であり、西島さんの囁きと白石さんのブラシとが重なって何とも言えない夢現のサウンドが出来上がっていた。「Where is my dream?」「hard to remember」と歌っていたように。
「Evening」での魅力的なピアノの和声、「つばめ」での遠くなったり近づいたりする濃淡、「大きな魚」でのヴォイスとピアノとの気持ちよい重なりと微妙なズレなんかも良かった。
またそればかりではなく、「Bran New Cubic」や「ものすごく速いらしいクルマ」ではスピーディーに飛ばし、吉野さんの良い音のベースも、あまり大きな音を好まないらしい白石さんのドラムスも、ここではサウンドを駆動して、他の曲とのコントラストで目が醒めるようだった。先日のApolloでは、休憩時間にキース・ジャレットのスタンダーズ(たしか『Standards in Norway』)が流されていて、西島さんが「スポーツカーのよう」と表現していたことを思い出した。キースとは異なるピアノトリオのサウンドではあるけれど。
吉野さんのベースにはいつもながらに実に味がある。ライヴで歌うことはないが、声もそうであり、無関係ではないに違いない。
こんどの東京でのライヴは9月19-21日、triogyとtrio SONONI(Apolloと新宿ピットイン)。なんとか駆けつけようと思っている。


Fuji X-E2、XF60mmF2.4
●西島芳
西島芳 triogy@下北沢Apollo(2018年)
西島芳 trio SONONI@下北沢Apollo(2018年)
西島芳アンサンブル・シッポリィ『Very Shippolly』(2017年)
●吉野弘志
西島芳 triogy@下北沢Apollo(2018年)
吉野弘志+中牟礼貞則+廣木光一@本八幡Cooljojo(2016年)
松風鉱一トリオ@Lindenbaum(2008年)
向島ゆり子『Right Here!!』(1995-96年)
ジョセフ・ジャーマン
●白石美徳
西島芳 triogy@下北沢Apollo(2018年)
かみむら泰一session@喫茶茶会記(2017年)
照内央晴「九月に~即興演奏とダンスの夜 茶会記篇」@喫茶茶会記(JazzTokyo)(2016年)