マヤ・アンジェロウ『私の旅に荷物はもういらない』(立風書房、原著1993年)を読む。

彼女の文章は、シンプルながらとても説得力がある。それは、卑屈や憎悪の領域に自分を置かず、前向きに生きていくための言葉であり、国籍や性別や年齢や信仰などに関係なく響くものに違いない。変な自己啓発本(知らんけど)よりも百万倍は良い。
●マヤ・アンジェロウ
デイヴ・ホランド『Dream of the Elders』(1995年)
マヤ・アンジェロウ『私の旅に荷物はもういらない』(立風書房、原著1993年)を読む。

彼女の文章は、シンプルながらとても説得力がある。それは、卑屈や憎悪の領域に自分を置かず、前向きに生きていくための言葉であり、国籍や性別や年齢や信仰などに関係なく響くものに違いない。変な自己啓発本(知らんけど)よりも百万倍は良い。
●マヤ・アンジェロウ
デイヴ・ホランド『Dream of the Elders』(1995年)
渡辺隆雄+早川岳晴『Hums For Midnight Amble』(Studio Wee、2018年)を聴く。

Takao Watanabe 渡辺隆雄 (tp)
Takeharu Hayakawa 早川岳晴 (b)
一聴してああこれは良いと思える音楽はあるものだ。早川さんのウッドベースは思った以上に太く豊かな音で鳴り、渡辺さんの滋味深いトランペットとともに、マイペースな感じのデュオを展開している。
ふたりのオリジナル曲もミンガスも良いのだが、もっとも沁みてしまったのは「君を信じてる」。トランペットの音色から、声を絞り出すようにして歌ったキヨシローの姿が見えてくる。
それにしても驚いた、Studio Weeの復活。松風鉱一4の企画とかないかな(勝手な放言です)。
●渡辺隆雄
藤井郷子オーケストラ東京@新宿ピットイン(2018年)
オルケスタ・リブレ@神保町試聴室(2017年)
●早川岳晴
生活向上委員会大管弦楽団『This Is Music Is This?』(1979年)
アート・アンサンブル・オブ・シカゴの映像『Live at the Jazz Showcase』(AECO、1981年)を観る。

Malachi Favors Maghostut (b, perc)
Famoudou Don Moye (perc)
Joseph Jarman (reeds, perc)
Roscoe Mitchell (reeds, perc)
Lester Bowie (tp, perc)
昔、Rhapsody Filmから出ていたVHS『Live from the Jazz Showcase』(微妙にタイトルが違う)と同じである。これはドン・モイエが2016年に来日したときの物販で、あっDVDでも作られているのかと喜んで買った。しかし、DVD『In Concert』と同じようである(それは入手してそのへんに転がっており確かめていない)。
ちょうど『Urban Bushmen』を吹き込んだ少し後。昼間うとうとしながら観たが、そのくらいの態度でちょうど良さそうな自然体の祝祭感である。レスター・ボウイとロスコ―・ミッチェルを除く3人は顔に思い切りペイントしている。みんな実に愉しそうだ。やはり、ひとりひとりの演奏が組み合わさったということではなく、バンドサウンドとしてトータルに展開されるものだという印象が強くなる。
AEOCの映像作品としては、1993年の『LUGANO 1993』がゲストも迎えたステージの華やかさ、1997年の『Null Sonne No Point』がフンベルト=ペンツェルならではの凝った迫り方とそれぞれ違っていて、どれも良い。
それにしても、AEOCはナマで観たかったなあ。間に合わなかった。
●アート・アンサンブル・オブ・シカゴ
アート・アンサンブル・オブ・シカゴの映像『Null Sonne No Point』(1997年)
アート・アンサンブル・オブ・シカゴ『カミング・ホーム・ジャマイカ』(1995-96年)
アート・アンサンブル・オブ・シカゴの映像『LUGANO 1993』(1993年)
アート・アンサンブル・オブ・シカゴ『苦悩の人々』(1969年)
ジミー・フォレスト『All The Gin Is Gone』(Delmark、1959年)を、エルヴィン・ジョーンズ参加という理由だけでずっと聴いてきたのだが、実は、『Black Forrest』(Delmark、1959年)も同じメンバー・同じ日の吹き込みだということに、数日前に気が付いた。なんだ早く教えてくれ。


Jimmy Forrest (ts)
Grant Green (g)
Harold Mabern (p)
Gene Ramey (b)
Elvin Jones (ds)
とは言え、あらためて2枚をまとめて聴いてみても、特に大きな感慨とか感動とかいったようなものはない。もちろんヴェテランであり、太く、ストレートながらうまくよれて、ブルージーで、良いテナーである。太いといえばグラント・グリーンも太い。エルヴィン・ジョーンズは2枚ともに特筆すべきドラミングをみせるわけでもなく、普通の日のエルヴィンである。
それ以上あなたは何を望むのか。
『けーし風』第99号(2018.7、新沖縄フォーラム刊行会議)の読者会に参加した(2018/8/11、秋葉原/御茶ノ水レンタルスペース会議室)。参加者は5人+1人(懇親会)。

特集は「沖縄戦非体験者として伝える戦争」、「追悼・新崎盛暉先生」。さらにこの3日前に亡くなった翁長雄志沖縄県知事のこと。
沖縄現代史のアーカイブ
●県・市町村の歴史資料保管に対する予算不足という大きな問題。
●村岡敬明さん(明治大学)は沖教組(沖縄県教職員組合)が読谷村に寄贈した約8万点の写真等の資料をデジタルアーカイブ化するにあたって、自治体予算ではなく、クラウドファンディングを用いた。
●特に、資料の分散、保管状態の悪さ(8ミリフィルムがどんどん劣化していくなど)、人員不足といった問題が挙げられる。貴重なはずの資料の内容が把握されないと予算もつかないという悪循環がある。
●故・大田昌秀元知事の沖縄国際平和研究所の資料は、数か所に分けられて保管されるという話がある。
●沖縄県が運営する「沖縄平和学習デジタルアーカイブ」がこの4月に突然見られなくなった問題。渡邉英徳さん(東京大学大学院教授)が中心となって5千万円の予算を投じて作成されたもの。県からの反応は遅く、ようやく最近になって、150万円ほどの運営費が不足しているためとの回答があった。再開の方向だが経緯には不可解なところがある。
記憶の継承
●歴史の記憶を継承しようとする運動も、生活が大変な沖縄においては困難。(数十年前に「公務員年金が安定しているからできるんだろう」と言われたことがあるとの発言。)
●小中高校に平和学習専門の人がいない。県内の大学には沖縄戦や沖縄近代史の研究者もいない(少ない)。
●県・市町村で戦争遺跡の整備予算がほとんどついていない。首里の32軍司令部壕さえ未指定の「ほらあな」。
●「日の丸」の問題。新崎盛暉『沖縄現代史』にあるように、1987年海邦国体の前後に、大きな中央からの圧力によって、「日の丸」掲揚率が全国平均を追いぬいた。もとは「復帰」のシンボルだった。その87年国体では知花昌一氏が「日の丸」を焼いた事件があった(ドキュメンタリー映画『ゆんたんざ沖縄』で描かれている)。
●一方、この頃、沖教祖が「日の丸」について総括しようとする動きがあったが、それは頓挫した。「日の丸」や天皇制に対する視線が一貫性をもたなかったことが、その背景にあった。なお、昭和天皇がアメリカ側に沖縄の長期占領の希望を伝えた「天皇メッセージ」が表に出てきたのは1979年だった。
●海邦国体の「日の丸」事件により、右翼がチビチリガマの平和の像(金城実)を壊した。2017年9月12日に少年4人が像を壊したのは2回目ということになる。このときかれらはチビチリガマの中も徹底的に荒らした。誰のどのような意向かはともかく、平和教育と記憶の継承がうまくいかなくなってきたことを象徴するものだった。
●チビチリガマは「霊感スポット」として語られることがある。歴史に対する深い考察よりも、スピリチュアリズムやダークツーリズムが持て囃される浅薄さにも共通するものがある。
●読谷村は2018年6月に「世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアム」を開いた。その中にはチビチリガマのジオラマがあり、子が母に首を切られる「集団自決」の場面が展示されている。稲嶺知事時代に、平和祈念資料館で住民に銃口を向ける日本兵の像の向きが変えられた事件を思い出すがどうか。
●記憶の継承を「学びなおし」として示した屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす』の視点。
新崎盛暉さん
●CTC闘争を中心とした『琉球弧の住民運動』(~1990年)から『けーし風』(1993年~)への動きが明確。
●『琉球弧の住民運動』は2014年に復刻(『けーし風』読者会がきっかけになった)。原典はほとんど残っていなかったが沖縄大学にあった。
●『沖縄現代史』などが韓国語、中国語に翻訳され出版されたことの効果は大きい。研究者、メディア、運動家、アーティストなどの間で新崎さんの知名度は高い。新崎さんははじめから国境を越えた社会のあり方を考えていた。
沖縄県知事選
●名護市長選(2018/2/4、稲嶺進市長が敗北)は、知的な展望が先走り、市民の暮らし目線が足りなかったとの指摘。
●オール沖縄からは金秀グループ、かりゆしグループが離脱。若い人の間には政治への諦めが蔓延している(つまり、どちらにも付きうる)。
●そのような状況下で翁長知事が亡くなり、果たして知事選(9月末?)はどうなるか。
●候補者として出てきている名前。自民は、佐喜眞淳(宜野湾市長)が軸、あるいは安里繁信(実業家)。県政与党の翁長後継者としては、謝花喜一郎(副知事)、糸数慶子(参議院議員)、城間幹子(那覇市長)、前泊博盛(沖縄国際大学)。
●沖縄の政治を保革の切り口で分析しようとする研究者もいるが、それは間違っている。
その他
●戦後、沖縄戦で破壊された土地における緑化運動が、米国の意向により民政府を通じて進められた(緑の学園運動)。表彰制度もあった。米軍機が墜落した宮森小学校も表彰されたことがある。
●その宮森小学校については、戦時中に民間の「石川学園」として発足し、戦後、宮森小学校、城前小学校に分校し公立の小学校となった経緯がある。
紹介された本
●乗松聡子編著『沖縄は孤立していない』(金曜日)
●ジョン・ミッチェル『日米地位協定と基地公害』(岩波書店)
●林博史『沖縄からの本土爆撃』(吉川弘文館)
●『世界』2018年9月号、特集「人びとの沖縄」(岩波書店)
●櫻澤誠『沖縄現代史』(中公新書)
参照
『けーし風』
アーチー・シェップ『Mariamar』(Atomic Records、1975年)を聴く。
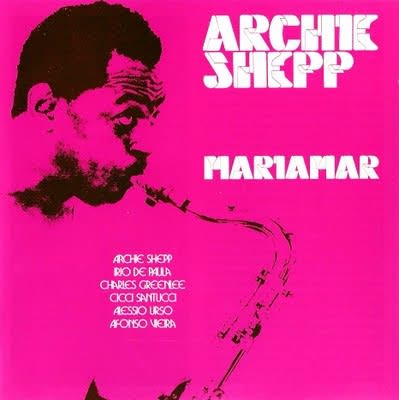
Cicci Santucci (tp)
Charles Greenlee (tb)
Archie Shepp (ts, ss, p)
Irio De Paula (g)
Alessio Urso (b)
Afonso Vieira (ds)
セクステットである。トロンボーンのチャールズ・グリーンリー以外はイタリアとブラジルのミュージシャンたち。
『Kwanza』だとか『The Full Moon Ensemble Live In Antibes』だとか『Attica Blues』だとか、ギタリストと一緒にシェップが演っているものは珍しくはない。しかし、こうしてずっと目立っていると、不思議な組み合わせに感じられてくる。
サウンドにはコミュニティ感もあり、珍しさもあって悪くはないのだが、さして特筆すべき点はない。だが、シェップが吹いていれば凡作であっても問題なし。いつだってそんなものだ。
●アーチー・シェップ
アーチー・シェップ『Tribute to John Coltrane』(2017年)
ヨアヒム・キューン『Voodoo Sense』(2012年)
アーチー・シェップ+ヨアヒム・キューン『WO! MAN』(2011年)
アーチー・シェップ『Tomorrow Will Be Another Day』(2000年)
アーチー・シェップ+ジーン・リー『African Moods』(1984年)
アーチー・シェップの映像『I am Jazz ... It's My Life』(1984年)
イマジン・ザ・サウンド(1981年)
アーチー・シェップ『The Way Ahead』(1968年)
アーチー・シェップ『The Way Ahead』 その2(1968年)
サニー・マレイのレコード(1966、69、77年)
アーチー・シェップ『Mama Too Tight』(1966年)
ロヴァ・サクソフォン・カルテットとジョン・コルトレーンの『Ascension』(1965、95年)
『Jazz in Denmark』 1960年代のバド・パウエル、NYC5、ダラー・ブランド(1962、63、65年)
セシル・テイラー初期作品群(1950年代後半~60年代初頭)
廣木光一+渋谷毅『Águas De Maio 五月の雨』(Hiroki Music、2018年)を聴く。
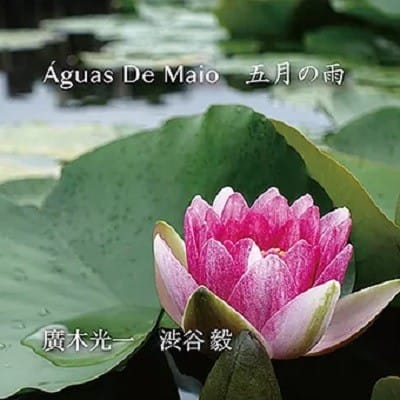
Koichi Hiroki 廣木光一 (g)
Takeshi Shibuya 渋谷毅 (p)
『So Quiet』(Mugendo、1998年)は出た当時から好きで、今に至るまで繰り返し聴いている。それ以来2枚目のデュオ作品である。20年も経っているのか。
再演曲は2曲。「He is Something」(廣木)は故・武田和命のために書かれた曲だそうだが、本人の吹いた録音は出ていない(と、渋谷さんが書いている)。新旧の演奏を比較してみると、新しい方がすこし溌剌としているように聴こえる。主旋律という物語の語り手が廣木さんであり、渋谷さんの合いの手を挟んで、また廣木さんへと戻る。武田さんのブロウはどのようなものだったのだろう。
そして、わたしを含め多くのファンが愛する「Beyond the Flames」(渋谷)、場合によっては「無題」。これはやはり、たゆたい循環する渋谷さんのピアノが中心にある。20年前の演奏では全般に廣木さんのギターが介入していた。本盤では主にピアノの時間の節目においてギターが入ってきており、さらにコラボレーションが動悸を引き起こす。2分過ぎにギターがピアノに重なる音を聴いてほしい。間違いなく小さい声であっと叫ぶだろう。昨日、中野のSweet Rainでこの曲が流され、植松孝夫さんが浅川マキの思い出をぽつぽつと呟いた。たまらないな。
他の曲ももちろん素晴らしい。最近のライヴで廣木さんがよく演奏する「人生は風車」(カルトーラ)とか「Frenesi」(廣木)なんて実に実に良い曲なんである。
何気なさを装って圧倒的に強靭で清冽な音を出すふたりのデュオ。

●廣木光一
高田ひろ子+廣木光一@本八幡cooljojo(2017年)
安ヵ川大樹+廣木光一@本八幡Cooljojo(2016年)
吉野弘志+中牟礼貞則+廣木光一@本八幡Cooljojo(2016年)
廣木光一+渋谷毅@本八幡Cooljojo(2016年)
Cooljojo Open記念Live~HIT(廣木光一トリオ)(JazzTokyo)(2016年)
廣木光一(HIT)@本八幡cooljojo(2016年)
廣木光一『Everything Shared』(2000年)
廣木光一『Tango Improvisado』(1995年)
●渋谷毅
今村祐司グループ@新宿ピットイン(2017年)
渋谷毅@裏窓(2017年)
渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2017年)
渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2016年その3)
渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2016年その2)
廣木光一+渋谷毅@本八幡Cooljojo(2016年)
渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2016年その1)
渋谷毅@裏窓(2016年)
渋谷毅+市野元彦+外山明『Childhood』(2015年)
渋谷毅エッセンシャル・エリントン@新宿ピットイン(2015年)
渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2014年)
渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2011年)
渋谷毅+津上研太@ディスクユニオン(2011年)
渋谷毅のソロピアノ2枚(2007年)
原みどりとワンダー5『恋☆さざなみ慕情』(2006年)
『RAdIO』(1996, 99年)
渋谷毅+川端民生『蝶々在中』(1998年)
『RAdIO』カセットテープ版(1994年)
『浅川マキを観る vol.3』@国分寺giee(1988年)
『山崎幹夫撮影による浅川マキ文芸座ル・ピリエ大晦日ライヴ映像セレクション』(1987-92年)
浅川マキ+渋谷毅『ちょっと長い関係のブルース』(1985年)
カーラ・ブレイ+スティーヴ・スワロウ『DUETS』、渋谷毅オーケストラ
見上げてごらん夜の星を
マーク・ドレッサー+スージー・イバラ『Tone Time』(Wobbly Rail、2003年)を聴く。

Mark Dresser (b)
Susie Ibarra (ds)
マーク・ドレッサーは、コントラバスの中音域を中心として、決して地響きのするような轟音やノイズなど目立つ音は出さない。それでも音楽を推進する力強さが常にあって、耳が吸いつけられる。
一方のスージー・イバラは曲の全体を俯瞰する知性があって、放つパルスは自然体であるという、なんとも言えない魅力がある。
このふたりによるデュオ、聴いてみるとなるほど素晴らしいマッチングである。特にタイトル曲の丁々発止ぶりが見事。
●マーク・ドレッサー
マーク・ドレッサー7@The Stone(2017年)
マーク・ドレッサー7『Sedimental You』(2015-16年)
テイラー・ホー・バイナム+マーク・ドレッサー『THB Bootlegs Volume 4: Duo with Mark Dresser』(2014年)
マーク・ドレッサー『Unveil』、『Nourishments』(2003-04年、-2013年)
『苦悩の人々』再演(2011年)
クリスペル+ドレッサー+ヘミングウェイ『Play Braxton』(2010年)
スティーヴ・リーマン『Interface』(2003年)
藤井郷子『Kitsune-Bi』、『Bell The Cat!』(1998年、2001年)
ジェリー・ヘミングウェイ『Down to the Wire』(1991年)
ジョン・ゾーン『Spy vs. Spy』(1988年)
中野のSweet Rainで、植松孝夫・永武幹子デュオ(2018/8/10)。昨春の北千住Birdland以来である。

Takao Uematsu 植松孝夫 (ts)
Mikiko Nagatake 永武幹子 (p)
開演前。廣木光一・渋谷毅『Águas De Maio 五月の雨』の「Beyond the Flames」が流れ、植松さんが浅川マキの思い出を話している。渋谷さんがいつも弾いていた、この曲のときは自分は吹くことはなかったけれど、と。
ファーストセット。「Lament」(J.J.ジョンソン)、「Four」(マイルス・デイヴィス)のあと、「Softly, as in a Morning Sunrise」。マキさんの話を聞いたせいか、深い倍音でストレートに吹き、駆け上がり、少しレイドバックする植松さんのテナーから、どうしても新宿や池袋の夜の匂いがする。テーマはしばらくしてから現れた。続く「Speak Low」では永武さんのピアノが飛ばし、右肘が上がる。「黒いオルフェ」では、お茶目にも植松さんがピアノの椅子に腰かけた。「All Blues」では、ピアノのあざやかなイントロから、ふたりで合図しあい、テナーが入っていく面白さがあった。
セカンドセット。もう植松さんは自分の椅子を用意した。2曲ほど即興をやったのだが、特に後半のブルースに、植松孝夫カラーがばんばんと放出され、たびたびのけぞる。それは、「Dindi」(ジョビン)においてもそうであって、濃厚な倍音の奔流に、ピアノが手探りするようにあわせていった。「Now's the Time」は植松さんの我流のタイム感、力技で引っ張る引っ張る。やがてふたりともスピードアップしていき、その中で永武さんは高音を転がすような弾き方もみせた。一旦は終わったかと思ったのだが、植松さんはにやりとして、またテーマを吹き始めた。天を仰いで笑う永武さん。最後は「In a Sentimental Mood」。
それにしても唯一無二のテナー。嬉しくて聴きながら笑ってしまった。



Nikon P7800
●植松孝夫
植松孝夫+永武幹子@北千住Birdland(JazzTokyo)(2017年)
本田竹広『EASE / Earthian All Star Ensemble』(1992年)
『山崎幹夫撮影による浅川マキ文芸座ル・ピリエ大晦日ライヴ映像セレクション』(1987-92年)
浅川マキ『アメリカの夜』(1986年)
ジョージ大塚『Sea Breeze』(1971年)
植松孝夫『Debut』(1970年)
●永武幹子
永武幹子+齋藤徹@本八幡cooljojo(2018年)
永武幹子+類家心平+池澤龍作@本八幡cooljojo(2018年)
永武幹子+加藤一平+瀬尾高志+林ライガ@セロニアス(2018年)
永武幹子+瀬尾高志+竹村一哲@高田馬場Gate One(2017年)
酒井俊+永武幹子+柵木雄斗(律動画面)@神保町試聴室(2017年)
永武幹子トリオ@本八幡cooljojo(2017年)
永武幹子+瀬尾高志+柵木雄斗@高田馬場Gate One(2017年)
MAGATAMA@本八幡cooljojo(2017年)
植松孝夫+永武幹子@北千住Birdland(JazzTokyo)(2017年)
永武幹子トリオ@本八幡cooljojo(2017年)
渋谷のメアリージェーンに足を運んだ(2018/8/9)。
たまにコーヒーを飲んだりもするが、ここでライヴを観るのは、20世紀末のサニー・マレイやジョセフ・ジャーマン以来である。99年のマレイに関して言えば、その後、銀座のクロイゾンホールで豊住芳三郎、普門義則とのトリオも観た。薩摩琵琶の演奏を観るのも、その故・普門さん以来のことである。

Yoshino 与之乃 (薩摩琵琶, vo)
Natsuki Tamura 田村夏樹 (tp)
与之乃さんの大きな撥によるばちんという破裂音、これに田村さんが擬態するところから始まった。低く朗々とした謡。物語は一聴ではよくわからないのだが、飛び込んでくる言葉に、その都度意識を喚起させられる(さらに判らない英語の曲もあった)。薩摩琵琶の音は、虫の鳴き声のような連続的な音からいちいち驚かされる撥音まで幅広く、とても新鮮なものだった。インプロにおいては弦からの音を与之乃さん自身が味わっているようで、その内外への意識の動きがまた面白い。
それにしても、田村さんのトランペットの表現力は本当に刮目にあたいする。薩摩琵琶の音に対峙するということもあるのだろうけれど、突き破るような音、息や唸り声とのミクスチャーなどのあれこれを飄々と出してくる。
先日録音した音源が年内にはCD化されるそうで、今から楽しみになってきた。




Fuji X-E2、XF35mmF1.4、XF60mmF2.4
●田村夏樹
Mahobin『Live at Big Apple in Kobe』(JazzTokyo)(2018年)
魔法瓶@渋谷公園通りクラシックス(2018年)
MMM@稲毛Candy(2018年)
藤井郷子オーケストラ東京@新宿ピットイン(2018年)
藤井郷子オーケストラベルリン『Ninety-Nine Years』(JazzTokyo)(2017年)
晩夏のマタンゴクインテット@渋谷公園通りクラシックス(2017年)
This Is It! @なってるハウス(2017年)
田村夏樹+3人のピアニスト@なってるハウス(2016年)
藤井郷子『Kitsune-Bi』、『Bell The Cat!』(1998、2001年)
ポール・ブレイ『Bremen '66』(Hi Hat、1966年)を聴く。

Paul Bley (p)
Mark Levinson (b)
Barry Altschul (ds)
このときポール・ブレイは30代前半。まだ若いブレイも良いものだ。後年の演奏を比較対象にすると、まだ粗削りで歯を凶暴に剥いているようなところもあるが、その一方で、自分自身の発する音の響きに耽溺していることが伝わってくる。
その場で編み出されたフレーズを完成系に持ち込もうとはせず、そのまま怖れず提示することが、かれのアイデンティティのようにも感じる。それは一音一音の響きについても同じことで、自分が直前に弾いたばかりの音に身をゆだね、愛おしむように同じ音で歌っていたりもする。
どの曲も良いのだが、やはり名曲「Ida Lupino」。バリー・アルトシュルはミスマッチでやかましいな。
●ポール・ブレイ
フランソワ・キャリア+ミシェル・ランベール+ポール・ブレイ+ゲイリー・ピーコック『Travelling Lights』(2004年)
ポール・ブレイ『Solo in Mondsee』(2001年)
ポール・ブレイ『Synth Thesis』(1993年)
ポール・ブレイ『Homage to Carla』(1992年)
ポール・ブレイ『Plays Carla Bley』(1991年)
ポール・ブレイ+ゲイリー・ピーコック『Partners』(1991年)
ポール・ブレイ+チャーリー・ヘイデン+ポール・モチアン『Memoirs』(1990年)
チェット・ベイカー+ポール・ブレイ『Diane』(1985年)
イマジン・ザ・サウンド(1981年)
アネット・ピーコック+ポール・ブレイ『Dual Unity』(1970年)
ポール・ブレイ『Barrage』(1964年)
ポール・ブレイ『Complete Savoy Sessions 1962-63』(1962-63年)
サムスクリュー(Thumbscrew)の3、4作目となる『Ours』と『Theirs』(Cuneiform Records、2017年)。
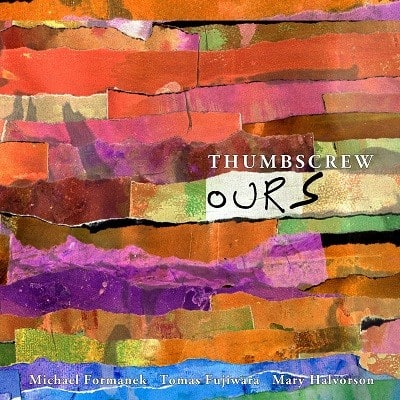

Michael Formanek (b)
Tomas Fujiwara (ds)
Mary Halvorson (g)
タイトルの通り、メンバーのオリジナル曲集と、他の音楽家の曲集。録音は同じときになされている。
どちらにおいてもメアリー・ハルヴァーソンのギターは歪んでいて目眩がさせられるものだが、元の曲を知っていることもあってより過激さに驚かされるのは『Theirs』のほうである。いきなりベニー・ゴルソンの「Stablemates」におけるエフェクトで幻惑されて何が何やら、またスタンリー・カウエルの「Effi」は意外にもケニー・バレルをも彷彿とさせるノリ疾走のジャズギタートリオ的。何しろシンプルなトリオなのに振れ幅が大きい。
いままでメアリーにばかり耳と心を奪われていたけれど、マイケル・フォルマネクの時間軸方向に柔軟なベース、トマ・フジワラのシンバル音を抽出して洗って鮮やかに提示したようなドラムスも、また、個性的で面白いことに気付かされた。
●メアリー・ハルヴァーソン
トム・レイニー・トリオ@The Jazz Gallery(2017年)
メアリー・ハルヴァーソン『Paimon: Book Of Angels Volume 32』(2017年)
トマ・フジワラ『Triple Double』(2017年)
メアリー・ハルヴァーソン『Code Girl』(2016年)
メアリー・ハルヴァーソン『Away With You』(2015年)
イングリッド・ラウブロック、メアリー・ハルヴァーソン、クリス・デイヴィス、マット・マネリ @The Stone(2014年)
『Illegal Crowns』(2014年)
トマ・フジワラ+ベン・ゴールドバーグ+メアリー・ハルヴァーソン『The Out Louds』(2014年)
メアリー・ハルヴァーソン『Meltframe』(2014年)
アンソニー・ブラクストン『Ao Vivo Jazz Na Fabrica』(2014年)
イングリッド・ラウブロック(Anti-House)『Roulette of the Cradle』(2014年)
『Plymouth』(2014年)
PEOPLEの3枚(-2005、-07、-14年)
トム・レイニー『Hotel Grief』(2013年)
チェス・スミス『International Hoohah』(2012年)
イングリッド・ラウブロック(Anti-House)『Strong Place』(2012年)
イングリッド・ラウブロック『Zurich Concert』(2011年)
メアリー・ハルヴァーソン『Thumbscrew』(2013年)
ウィーゼル・ウォルター+メアリー・ハルヴァーソン+ピーター・エヴァンス『Mechanical Malfunction』(2012年)
ステファン・クランプ+メアリー・ハルヴァーソン『Super Eight』(2011年)
ウィーゼル・ウォルター+メアリー・ハルヴァーソン+ピーター・エヴァンス『Electric Fruit』(2009年)
アンソニー・ブラクストン『Trio (Victoriaville) 2007』、『Quartet (Mestre) 2008』(2007、08年)
●マイケル・フォルマネク
メアリー・ハルヴァーソン『Code Girl』(2016年)
メアリー・ハルヴァーソン『Thumbscrew』(2013年)
●トマ・フジワラ
メアリー・ハルヴァーソン『Paimon: Book Of Angels Volume 32』(2017年)
トマ・フジワラ『Triple Double』(2017年)
メアリー・ハルヴァーソン『Code Girl』(2016年)
『Illegal Crowns』(2014年)
「JazzTokyo」のNY特集(2016/8/1)
トマ・フジワラ+ベン・ゴールドバーグ+メアリー・ハルヴァーソン『The Out Louds』(2014年)
トマ・フジワラ『Variable Bets』(2014年)
Ideal Bread『Beating the Teens / Songs of Steve Lacy』(2014年)
ファマドゥ・ドン・モイエ『Sun Percussion』(AECO Records、1975年)。
先日、レコ屋のフリー箱を何気なく覗いたら目に飛び込んできた。しかも未開封。本盤はAECO Recordsの完全ソロシリーズの1枚目であり、これで、2枚目のジョセフ・ジャーマン、3枚目のマラカイ・フェイヴァースとあわせて3枚が揃った。いいだろう。

Famoudou Don Moye (ds, congas, gongs, ballophone, whistles, fl, brake ds, log ds, shekere, bike horns, bells, hubkaphone, bendir, bongos, kalimba, etc.)
打楽器を中心にたくさんの楽器を演奏している。当然ながらアート・アンサンブル・オブ・シカゴに共通する雰囲気が色濃いのだが、本盤では、ソロであるだけにモイエの独自の音色をずっと味わうことができる。
鋭いのだが同時に丸くもあり、この尖ったエッジに向かってきめ細かい紙やすりでピカピカに研いだような感覚。端の尖った部分は透明に透けているような感覚。あるいは高麗青磁のような感覚。耳が悦ぶとはこのことである。
●ファマドゥ・ドン・モイエ
生活向上委員会2016+ドン・モイエ@座・高円寺2(2016年)
ババ・シソコ『Jazz (R)Evolution』(2014年)
ワダダ・レオ・スミス『Spiritual Dimensions』(2009年)
ライトシー+モイエ+エレケス『Estate』(2000年)
アーサー・ブライス『Hipmotism』(1991年)
アート・アンサンブル・オブ・シカゴの映像『Null Sonne No Point』(1997年)
アート・アンサンブル・オブ・シカゴ『カミング・ホーム・ジャマイカ』(1995-96年)
アート・アンサンブル・オブ・シカゴの映像『LUGANO 1993』(1993年)
ドン・モイエ+アリ・ブラウン『live at the progressive arts center』、レスター・ボウイ・ブラス・ファンタジー『Serious Fan』(1981、89年)
ドン・プーレン+ジョセフ・ジャーマン+ドン・モイエ『The Magic Triangle』(1979年)
ジュリアス・ヘンフィルのBlack Saintのボックスセット(1977-93年)
チコ・フリーマン『Kings of Mali』(1977年)
アート・アンサンブル・オブ・シカゴ『苦悩の人々』(1969年)
ニコール・ミッチェル『Maroon Cloud』(FPE Records、2017年)を聴く。

Nicole Mitchell (fl, composition)
Fay Victor (vo)
Aruan Ortiz (p)
Tomeka Reid (cello)
SF的想像力は何もサン・ラに限ったわけではなく、むしろアフロ・フューチャリズムの持つ特徴的な視線のひとつだが、ニコール・ミッチェルもその流れに位置付けることができる。彼女はこれまでにオクテイヴィア・バトラーからの影響を公言してきたし、『Mandorla Awakening II: Emerging Worlds』はその指向性が結実した傑作だった。
本盤もまたSF的想像力に満ちている。行き過ぎた技術によって破壊されてゆく世界にあって、「栗色の雲」が、想像力の源泉として物語化されている。『Mandora...』と同様に、生態系や環境の破壊に危機意識をもって物語を創り、それを音楽として表現するのがミッチェルの面白さである。
このサウンドにはメンバー全員が貢献している。フェイ・ヴィクターの深い声は描かれる世界の真実性を表しているようだ。また雰囲気の創出にあたって、きらめきをみせるアルアン・オルティスのピアノも、底流として濃淡を付けるトメカ・リードのチェロも良い。「a sound」での盛り上がりにはドラマ的な興奮を覚える。
そしてニコール・ミッチェルのフルートは常に靄の中から、本盤で言えば「栗色の雲」の中で、くっきりと浮かび上がる。これは特別だ。フェイ・ヴィクターは、最近のFBへの投稿で、『Rolling Stone』誌から「flutist Nicole M. Mitchell repeatedly expanded the boundaries of the instrument with flutters, trills and ear-catching vocal and breath effects」という文章を引用している。
●ニコール・ミッチェル
「JazzTokyo」のNY特集(2017/9/30)(ミッチェルへのインタビュー)
マーク・ドレッサー7@The Stone(2017年)
マーク・ドレッサー7『Sedimental You』(2015-16年)
ニコール・ミッチェル『Mandorla Awakening II: Emerging Worlds』(2015年)
ニコール・ミッチェル『Awakening』、『Aquarius』(2011、12年)
ジョシュア・エイブラムス『Music For Life Itself & The Interrupters』(2010、13年)
「JazzTokyo」のNY特集(2017/7/1)
「JazzTokyo」のNY特集(2017/5/1)
リー・コニッツ+ダン・テファー『Decade』(Verve、2010, 15, 16年)を聴く。

Lee Konitz (as, ss, voice)
Dan Tepfer (p)
昨年(2017年)、このデュオをNYのJazz Galleryで観た。なかなか感動的だった。コニッツを目の当たりにするのはおよそ20年ぶりだったが、本質が変わっていないこと自体がもう過激で、しかも、毒を吐いていた。その20年前には『Dig Dug Dog』のタイトル曲でスキャットを始めたところだったのだが、その後スキャットが進化しており、フレーズがコニッツのものであることにも驚かされた。
(実は真後ろにシャイ・マエストロが座ってスマホで動画を撮っており、わたしの間抜けな姿も入っていて笑った。隣の老夫婦は、ジャック・デジョネット『Made in Chicago』の収録時ライヴを観ていたんだよ、と。)
ダン・テファーが書いた本盤のライナーによると、実は、テファーがNYに出てきてすぐにマーシャル・ソラールにコニッツを紹介してもらって以来、10年来の付き合いなのだった(だから『Decade』)。55歳の年齢差があるのにテファーに余裕があり、ときにはコニッツをいなしたりするのもそれゆえだろう。音楽的な相性もばっちりであり、コニッツのノリに合わせていったテファーの大きな才覚を感じる。
コニッツのフレージングも音色も永遠に独自のものであり、まるで悠然となめらかな空中遊泳をしているようだ。3曲ではコニッツひとりで多重録音をしており、にやりとして愉しんでいる姿が目に浮かぶようである。
●リー・コニッツ
リー・コニッツ『At Sunside 2018』(2018年)
リー・コニッツ『Jazz Festival Saarbrücken 2017』(2017年)
リー・コニッツ+ダン・テファー@The Jazz Gallery(2017年)
リー・コニッツ『Frescalalto』(2015年)
リー・コニッツ+ケニー・ホイーラー『Olden Times - Live at Birdland Neuburg』(1999年)
今井和雄トリオ@なってるハウス、徹の部屋@ポレポレ坐(リー・コニッツ『無伴奏ライヴ・イン・ヨコハマ』、1999年)
ケニー・ホイーラー+リー・コニッツ+デイヴ・ホランド+ビル・フリゼール『Angel Song』(1996年)
リー・コニッツ+ルディ・マハール『俳句』(1995年)
アルバート・マンゲルスドルフ『A Jazz Tune I Hope』、リー・コニッツとの『Art of the Duo』 (1978、83年)
アート・ファーマー+リー・コニッツ『Live in Genoa 1981』(1981年)
ギル・エヴァンス+リー・コニッツ『Heroes & Anti-Heroes』(1980年)
リー・コニッツ『Spirits』(1971年)
リー・コニッツ『Jazz at Storyville』、『In Harvard Square』(1954、55年)