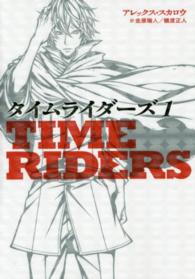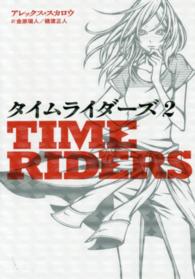「ブーリン家の姉妹」(上・下)フィリッパ・グレゴリー

「子なきは去れ」と貝原益軒は言ったが、
「子なきは首を切れ」とまでは言わなかった。
ヘンリー8世は、アン・ブーリンが男子を生まなかった、として首を切ってしまった。
結婚してわずか2年後のことである。(結局、6人と結婚して、2人斬首)
前妻キャサリン王妃と離婚するため、イギリス国教会を作り、バチカンから離反までしたのに。
本書は、そのアン・ブーリンを「妹」の視線から描いている。
悪名の高いアン・ブーリンだが、私は嫌いじゃない。(好きでもないが)
しかし、本書の著者は好きじゃないようだ。
さらに言うと、その血を受けついたエリザベスも嫌いなようだ。
もしかしたら、著者はカトリック教徒なのかも?
だから、英国をプロテスタント(英国国教会だけど)の国にしたアン・ブーリンとエリザベスを腹立たしく思っているのかも知れない。
読んでいて、そんなことを感じた。
ベストセラーの人気作品だけど、基本となる人物設定が、私の趣味と合致しない・・・。
描き方も、ワイドショー・女性週刊誌のような下世話さを感じた。
(そんな訳で、さほど面白く感じなかったが、様々な思いが湧きあがった)

↑アン・ブーリンとヘンリー8世
【おまけ】
急に本書を読みたくなったのは、英国EU離脱。
まったく状況は異なるが、イギリスという国は、他のヨーロッパと違うことをする。
一番の違いが、イギリス国教会を作ってバチカンから離脱したこと。
私の中では、EU離脱とアン・ブーリンが繋がった。
だから、この時代を扱った作品を読みたくなったのだ。
この時代はめまぐるしく為政者が替わる。
ヘンリー8世→エドワード6世→メアリ1世→エリザベス1世
ちなみに「王子と乞食」は、エドワード6世を描いている。
「イルカの家」も16世紀だけど、後半か。
「王子と乞食」を読むと、あまり良い時代じゃなかったように感じるが、
「イルカの家」を読むと、けっこう豊かな時代だったように思える。
いろんな人々がいた、ということか。
【離婚について】「王妃の離婚」佐藤賢一(P66)
厳密にいえば、カソリックの教義に離婚というものはない。新約聖書、マタイの福音書19の6に「もはやふたりではなく、ひとりなのです。こういうわけで、人は、神が結び合わせたものを引き離してはなりません」とあるからである。コリント人への手紙、第1の7の10、並びに11にも「妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら、結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません」とある。こうした教えを守るべく、カノン法も「婚姻の本質的特性は、単一性及び不解消性である」と明記して、あまねく信徒に離婚を禁じている。
では、意に添わない相手とも、永遠に別れられないかといえば、そういうわけでもなかった。キリスト教徒は事実上の離婚として、「結婚の無効取消」という手続きに訴えることができた。つまり、はじめからなかったことにする、という理屈である。
【はたしてアンに愛はあったか?】「残酷な王と悲しみの王妃」中野京子(P236)
歴史家たちの間でも意見は二分され、定説はない。最初のうち愛していなかったのは確かだ。問題はその後である。一国の王から熱烈なラブレター(ヴァチカンに十七通も残されている。なぜヴァチカンに?それも謎だ)をもらい、他国と戦争になりかけてまで、また宗教改革をしてまで、臣下を処刑し元王妃を退けてまで、自分を求めてくる、国のナンバーワン男を、いつまでも愛さずにいられるものだろうか?
いられる。
その点で、女は男ほど情に流されやすくはない。愛してくれる相手を可愛く思うようになる、というのは男性特有の(不思議な)優しさであり、たいていの女性は嫌なものは嫌なまま、身をまかせたにしてもそれは我慢しているだけだ。だからアンが徹頭徹尾、己の野心だけで行動していた、という説にも説得力はある。
しかし愛というものの性質を考えるとき、一方通行がそれほど長く続くものだろうか、との疑問が湧く。遠くから恋しているだけなら、たとえ相手に嫌われていようと、十年でも二十年でもあるいは一生でも続けれれるかもしれない。だがヘンリーとアンは、後半、ほぼ毎日のように顔を合わせていた。アンに情のひとつもなければ、いかなヘンリーであれ、恋情を保てたとは思えない。アンの心がわずかずつでも自分に傾いてきたればこそ、そしてある瞬間に魂と魂が響きあったればこそ、愛は成就したのではないか。
ヘンリーのようにではないにせよ、アンもきっと愛したのだ。彼女が愛したとき、ヘンリーはうっすら失望した。手に入った愛は、もういらない・・・・・・。
【ヘンリー八世の逸話】P193
八世は「イングランドで初めて梅毒にかかった王」との別名もあり、子どもたちに死産、流産、夭折がふつう以上に多かったのはそのせいと言われる。
【ネット上の紹介】
姉のアン・ブーリンに疎まれた妹メアリーはやがて、宮廷の外に新しい生活を求める。そこには「平凡な男」、スタフォードとの出会いがあった。一方、前の妃を追い出したアンは、栄華の極みを得る。しかし、男の世継ぎを産むことに執着した彼女は、破滅の途をたどり…。のちのエリザベス1世の母、アン・ブーリンと妹メアリーの哀しくも激しい物語は息を呑むクライマックスへ。