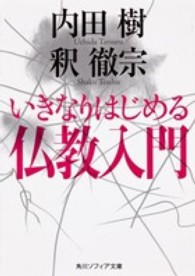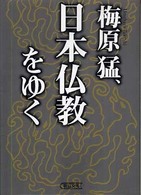「キリスト教と日本人 宣教史から信仰の本質を問う」石川明人
日本にキリスト教が浸透しなかったのはなぜ?
宣教史から振り返った作品。
P52
キリシタンへの改宗者が増えていくと、布施の額が減るという現実的な問題も出はじめたようで、ザビエルと僧侶たちとの関係は悪化して、嫌がらせや攻撃をされるようになっていった。
P87
伴天連追放令の背景としてさらにもう一つ言及すべきなのは、当時ポルトガル人が女性や子供を含む日本人を奴隷として売買していたという問題である。秀吉にはそれも許せなかったのである。(秀吉は、美女の誉れ高いガラシャに振られて、キリシタンを嫌うようになったという説もある)
P98
秀吉の時と違って完全な「禁教」にすることができたのは、カトリックであるスペイン・ポルトガルに対し、プロテスタントのオランダ・イギリスとのあいだで宣教を伴わない貿易が可能になったからでもある。
P106
こうした鎖国およびキリシタン迫害の背景には、カトリック国であるスペイン・ポルトガルと、新興のプロテスタント国であるイギリス・オランダとの世界覇権をめぐる争いもあった。
P114
ペリー自身も当然キリスト教徒である。彼が属していた教派は、英国教会の系統にある「聖公会」だ。初代駐日大使で日米修好条約を締結したタウンゼント・ハリスも、同じく聖公会に属していた。(中略)
海軍のペリーから約90年後、今度は陸軍のダグラス・マッカーサーが連合軍最高司令官として日本にやってきたが、彼も同じく聖公会の信徒で、日本にキリスト教を広めることに大変熱心であった。
P128
フルベッキは集まった日本人に対し、「平和は哲学者の夢であり、キリスト教徒の希望であるますが、戦争は人類の現実の歴史です」と述べた。これまでイギリスが世界各地で何をしたか、フランスやドイツやロシアはこれまで何をしたかを考えてみよ、とフルベッキは言い、現実に「危険」があるのだと繰り返した。
そして次のように続けている。「私の助言は、海岸を固めると同時に、真に国家的な軍隊をつくりなさいということです。若者を訓練し、教育しなさい。そしてすべての人に昇進の道を開きなさい」(『ミカド――日本の内なる力』P137)
P224
日本のキリスト教徒数は、総人口の1%程度という状態が続いている。(中略)
これまで宣教に費やしたコストとその成果に比べるならば、やはりキリスト教は日本で成功したとは言い難い。(中略)
確かに日本でもクリスマスなどのイベントは定着し、キリスト教式で結婚式を挙げる人は多い。(中略)日本人の半数近くは、牧師と神父の区別もついておらず、カトリックとプロテスタントの違いも説明できないのではないだろうか。
(韓国でのキリスト教徒の割合は約30%。この理由は次のように説明されている・・・以下、「教養としての宗教事件史」島田裕巳より――朝鮮王朝(李氏朝鮮)の時代になると、儒教が国教に定められ、仏教は弾圧を受けて衰退した。
儒教は基本的に男性のための宗教、上層部のための宗教であり、女性や下層階級はその枠のなかから排除されてしまう。朝鮮半島でも仏教の信仰が衰えなかったとしたら、それは女性や下層階級を含む民衆を救済する役割を果たし、宗教的な空白を作ることはなかったであろう。ところが、空白が存在したために、代わってキリスト教がそれを埋めることになったのである。P252)
P228
かつて、ヨーロッパのキリスト教徒たちは、外国に行っては現地の宗教文化を排斥し、壊滅させ、反抗する原住民を虐殺してきた。(中略)
しかし、日本はヨーロッパのキリスト教徒による侵略が当たり前だった時代に、それをさせなかった。あるいは、それをされずに済んだ。そのことが日本にキリスト教徒が広まらなかった理由の全てとは言わないまでも、重要な背景の一部であることは確かである。
P230
また森岡(清美)は、日本人には「敬畏すべき神」を忌み、「親しみやすい神」を慕う、という傾向があることも認めている。(中略)
そうした「神」を求める傾向のある多くの日本人には、キリスト教のように、まず何よりもおのれの罪を自覚させ、悔い改めを迫り、神の栄光に奉仕することを求める宗教には入り込みにくいのではないか、というのが彼の分析の大枠である。
【参考図書】
「キリスト教と戦争」 石川明人
「私たち、戦争人間について」石川明人

「佐藤優さん、神は本当に存在するのですか?」竹内久美子
【ネット上の紹介】
日本人の九九%はキリスト教を信じていない。世界最大の宗教は、なぜ日本では広まらなかったのか。宣教師たちは慈善事業や教育の一方、貿易、軍事にも関与し、仏教弾圧も指導した。禁教期を経て明治時代には日本の近代化にも貢献したが、結局その「信仰」が定着することはなかった。宗教を「信じる」とはどういうことか?そもそも「宗教」とは何か?宣教師たちの言動や、日本人のキリスト教に対する複雑な眼差しを糸口に、宗教についての固定観念を問い直す。
第1章 キリスト教を知らずに死んだ日本人に「救い」はない?
第2章 戦争協力、人身売買、そしてキリシタン迫害
第3章 禁教高札を撤去した日本
第4章 「本当のキリスト教」は日本に根付かないのか
第5章 「キリスト教」ではなく「キリスト道」?
第6章 疑う者も、救われる