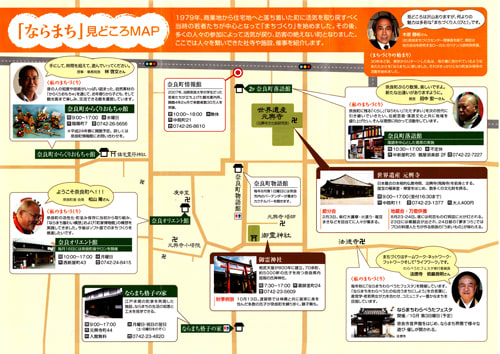いよいよこの土曜日(3/24)は、第9回古社寺を歩こう会「バスで巡る!神武天皇の聖蹟」です。週間天気予報では「曇り時々雨」ですが、雨天決行(荒天中止)です。昨日(3/20)の時点で、94人(打ち上げは48人出席)のご参加申し込みをいただきました。内訳は、当ブログご愛読者が31人(同12人)、奈良まほろばソムリエ友の会メンバーおよびそのご友人が43人(同21人)、私の勤務先のOBが11人(同8人)・現役社員が5人(同4人)、事務局(講師および世話人)が4人(同3人)です。
バスは2台で、1号車には、当ブログご愛読者、勤務先のOBと現役、2号車には、ソムリエ友の会が乗車します。世話人を加えると、補助席を使わなくて済むギリギリの人数となりました。なおバスガイドさんは、奈良検定のソムリエおよび1級の有資格者です。

神武天皇が占いに使ったという厳瓮(いつべ=御神酒の器)
のレプリカ(丹生川上神社で)。写真はすべて3/10撮影
行程表は以下に貼っておきますが、この予定だとお土産を買っていただく時間が全くありません。そこで東吉野村名物、升屋の「たあめん」(太そうめん)と御菓子司・西善の栗羊羹「そまづと」・最中「厳瓮(いつべ)」をバス車中でご希望者に斡旋し、昼食場所の丹生川上神社(中社)で受け取っていただくこととしました。「厳瓮」は、神武天皇が戦勝を賭けた占いをする際に使ったという「御神酒の容器」をかたどった珍しい最中です(みむろ最中ほどの小ぶりのもの)。占いのため厳瓮を川に沈めると、アユが浮いてきました。だからアユは「鮎」と書くそうです。

御菓子司・西善の厳瓮(いつべ)最中
ご参加者のうち、当ブログご愛読者のリストは、以前こちらに記載しましたが、ソムリエに合格されているO原さん、Y田さん、走るソムリエのY田さん・T石さんは2号車に回っていただくことといたしましたので、ご了承ください(席数バランスの都合上)。
※ご留意事項
1.出発時間(奈良商工会議所前8:20、JR奈良駅西口8:30)の数分前にご集合・ご乗車ください。「古社寺を歩こう会」の旗が目印です。
2.高倉山は少し歩きます(距離や標高はわずかですが、急坂です)し、他にも歩くところがあります(20~30分程度)。運動靴など、歩きやすい靴でお越し下さい。
3.昼食場所の丹生川上神社(中社)のベンチはわずかしかありませんので、敷物をご持参ください。なお、お弁当(薬草弁当)にお茶はついていませんので、各自ご持参ください。
4.参加費(@4,500円)はバス内、打ち上げ費用(男性@3,000円、女性@2,500円)は店内で集金します。お釣りの出ないよう、ご用意ください。
5.狭井神社付近で一旦解散式を行います。打ち上げに参加されない方は、近鉄八木駅、近鉄奈良駅、JR奈良駅までバスでお送りいたします。打ち上げ参加(贔屓屋桜井店=桜井駅構内)の方は、桜井駅で解散となります。

夢淵周辺(丹生川上神社近く)の滝
タイムスケジュールは以下のとおりです。3/10(土)に下見に行き、少し変更しました。
奈良―9:20鵄邑(とびのむら 生駒市)9:50出発―10:30針テラス(トイレ休憩)10:50-(榛原経由)―11:30菟田穿邑(うだのうかちのむら 宇陀市)12:00―12:30丹生川上神社(東吉野村 境内で昼食)13:10―13:40菟田高倉山(うだのたかくらやま 宇陀市)14:30―15:00等彌神社(桜井市)15:30―15:50磐余邑(同)16:30―16:50狭井河之上(同)17:30(見学後、解散式)
では皆さん、どうぞお楽しみに!
バスは2台で、1号車には、当ブログご愛読者、勤務先のOBと現役、2号車には、ソムリエ友の会が乗車します。世話人を加えると、補助席を使わなくて済むギリギリの人数となりました。なおバスガイドさんは、奈良検定のソムリエおよび1級の有資格者です。

神武天皇が占いに使ったという厳瓮(いつべ=御神酒の器)
のレプリカ(丹生川上神社で)。写真はすべて3/10撮影
行程表は以下に貼っておきますが、この予定だとお土産を買っていただく時間が全くありません。そこで東吉野村名物、升屋の「たあめん」(太そうめん)と御菓子司・西善の栗羊羹「そまづと」・最中「厳瓮(いつべ)」をバス車中でご希望者に斡旋し、昼食場所の丹生川上神社(中社)で受け取っていただくこととしました。「厳瓮」は、神武天皇が戦勝を賭けた占いをする際に使ったという「御神酒の容器」をかたどった珍しい最中です(みむろ最中ほどの小ぶりのもの)。占いのため厳瓮を川に沈めると、アユが浮いてきました。だからアユは「鮎」と書くそうです。

御菓子司・西善の厳瓮(いつべ)最中
ご参加者のうち、当ブログご愛読者のリストは、以前こちらに記載しましたが、ソムリエに合格されているO原さん、Y田さん、走るソムリエのY田さん・T石さんは2号車に回っていただくことといたしましたので、ご了承ください(席数バランスの都合上)。
※ご留意事項
1.出発時間(奈良商工会議所前8:20、JR奈良駅西口8:30)の数分前にご集合・ご乗車ください。「古社寺を歩こう会」の旗が目印です。
2.高倉山は少し歩きます(距離や標高はわずかですが、急坂です)し、他にも歩くところがあります(20~30分程度)。運動靴など、歩きやすい靴でお越し下さい。
3.昼食場所の丹生川上神社(中社)のベンチはわずかしかありませんので、敷物をご持参ください。なお、お弁当(薬草弁当)にお茶はついていませんので、各自ご持参ください。
4.参加費(@4,500円)はバス内、打ち上げ費用(男性@3,000円、女性@2,500円)は店内で集金します。お釣りの出ないよう、ご用意ください。
5.狭井神社付近で一旦解散式を行います。打ち上げに参加されない方は、近鉄八木駅、近鉄奈良駅、JR奈良駅までバスでお送りいたします。打ち上げ参加(贔屓屋桜井店=桜井駅構内)の方は、桜井駅で解散となります。

夢淵周辺(丹生川上神社近く)の滝
タイムスケジュールは以下のとおりです。3/10(土)に下見に行き、少し変更しました。
奈良―9:20鵄邑(とびのむら 生駒市)9:50出発―10:30針テラス(トイレ休憩)10:50-(榛原経由)―11:30菟田穿邑(うだのうかちのむら 宇陀市)12:00―12:30丹生川上神社(東吉野村 境内で昼食)13:10―13:40菟田高倉山(うだのたかくらやま 宇陀市)14:30―15:00等彌神社(桜井市)15:30―15:50磐余邑(同)16:30―16:50狭井河之上(同)17:30(見学後、解散式)
では皆さん、どうぞお楽しみに!