「神武天皇聖蹟顕彰碑」は、紀元2600年(昭和15年)奉祝の事業として、当時の文部省の肝いりで、神武天皇ゆかりの地に建てられた碑である。「紀元二千六百年奉祝会」が文部省に委嘱し、「神武天皇聖蹟調査委員会」による推考・答申に基づいて選定され、全国に19ヵ所、そのうち奈良県内では7ヵ所に碑が建つ。
来たる3/24(土)、仲間と作る「第9回古社寺を歩こう会」の主催で、これら7ヵ所全てを1日で回るバスツアーを行う。今日はそれに先だち、7つの碑の解説を以下に掲載しておく。ツアーに参加する人もしない人も、「古事記完成1300年」の今年には、頭の片隅に入れておいていただきたい知識である。記紀の登場順に紹介する。
1.神武天皇聖蹟菟田穿邑(うだのうかちのむら)顕彰碑 宇陀市菟田野宇賀志 八坂神社(村社)の近く
顕彰碑の裏面にはこう書かれている(表記を読みやすく改め、カッコ内に振り仮名をつけた。以下同じ)。「神武天皇戊午年(つちのえうまのとし)年頭 八咫烏(やたがらす)の郷導(ごうどう)に依り 道臣命を皇軍の将として菟田穿邑に至り給えり聖蹟は此の地方なるべし」。
※トップ写真は「菟田穿邑顕彰碑」。撮影は3/10(以下同じ)
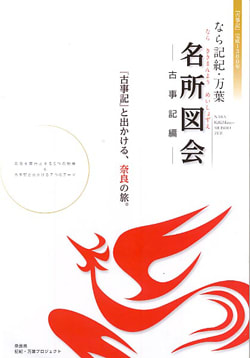
県の『なら記紀万葉 名所図会 古事記編』。電子ブック版は、こちら
伊波礼毘古命(いわれびこのみこと=神武天皇)は、八咫烏の案内で、熊野から大和の宇陀に至った。県の『なら記紀万葉 名所図会 古事記編』の「2.八咫烏、引道(みちび)きてむ」によると《険しき深山に分け入り、道を穿(うが)つようにして進みながら、ようやく一行は宇陀へたどり着く。この宇陀の穿(うかち)という地には、兄宇迦斯(えうかし)と弟宇迦斯(おとうかし)という兄弟がいた。まず八咫烏を遣わして「今、天つ神の御子がお見えになったが、お前たちは御子に仕えるか?」と尋ねると、兄宇迦斯は八咫烏めがけて鏑矢を射放ち、追い返してしまった》。
《兄宇迦斯は伊波礼毘古命一行を迎え撃とうとしたが、十分な軍勢が確保できず、ひとまず帰順する振りをする。大きな御殿を建てて、その内部にはいった者を圧(お)し殺す「押機(おし)」という罠を仕掛けて、伊波礼毘古命を待ち受けた。しかし弟宇迦斯が兄の企みを事前に密告。そこで道臣命(みちのおみのみこと 大伴連らの祖先)と大久米命(おおくめのみこと 久米直らの祖先)の2人が、「汝が建てた御殿だろう。まずは自らが中に入ってみせてみよ」と御殿に追い詰める。追われた兄宇迦斯は自ら作った罠にかかり、命を落としたという。以来、この地を「血原(ちはら)」というようになった》。

2.菟田高倉山(うだのたかくらやま)顕彰碑 宇陀市大宇陀守道 高倉山頂
顕彰碑の裏面には「神武天皇戊午年9月 菟田高倉の頂に登り給いて域中の虜軍(敵軍)の形勢を瞻望(せんぼう=遠くを見渡す)し給えり聖蹟は此の地なりと伝えらる」
Wikipedia「神武天皇」によると《9月、磐余彦(いわれびこ=神武天皇)は高倉山に登ると八十梟帥(やそたける)や兄磯城(えしき)の軍が充満しているのが見えた。磐余彦は深く憎んだ。高皇産霊尊(たかみむすひのみこと)が夢に現れ、その言葉に従って天平瓦と御神酒の器をつくって天神地祇を祀り、勝利を祈願した》。

高倉山頂には顕彰碑のほか、こんな碑も建っていた
3.丹生川上(にふのかわかみ)顕彰碑 東吉野村(丹生川上神社中社摂社 丹生神社北側)
碑の裏面には「神武天皇戊午年9月 天下平定の為 平瓮(ひらか)及び厳瓮(いつべ)を造り給い丹生川上に陟(のぼ)りて天神地祇を祭らせられ又丹生之川に厳瓮を沈めて祈り給えり聖蹟は此の地付近なり」。
上記2の「天平瓦と御神酒の器をつくって天神地祇を祀り、勝利を祈願した」というくだりは、『日本書紀』に出てくる(丹生川上神社[中社]の公式HPが、その全文を紹介している)。川べりに、このくだりを分かりやすく紹介する案内板があった。そこには《昭和15年(1940年)2月7日、文部省による神武聖蹟調査の第1回目の決定があり、「丹生川上の地」は小川村(現東吉野村)丹生川上神社の付近であると発表された》。

丹生川上顕彰碑。周囲は鬱蒼とした林なので、碑はこんな色になっていた
《日本書紀によると、戊午の年9月、神武天皇は、大和平定のため、夢にあらわれた天神の教えのとおり、天香具山の社の中の土を取って平瓮(ひらか)と厳瓮(いつべ 御神酒を入れる瓮)をつくり、丹生の川上にのぼって天神地祇を祀られた。神意を占って「厳瓮を丹生川に沈めよう。もし魚が大小となく全部酔って流れるのが真木の葉の浮き流れるようであれば自分はきっとこの國を平定するだろう」と言われて厳瓮を丹生川に沈めた。しばらくすると魚はみな浮き上がって口をパクパク開いた》。占いで浮かび上がってきた魚なので、アユは「鮎」と書くようになったそうだ。
《椎根津彦がそのことを報告すると、天皇は大いにお喜びになられ丹生の川上の五百箇の榊を根こそぎにして諸々の神をお祀りされた。このときから祭儀のときに御神酒瓶が置かれるようになった。丹生川は、今の高見川で、高見・四郷・日裏の三川が合流したところの深淵は、神武天皇が夢にあらわれた天神の教えによって厳瓮を沈めたところだと伝えられ、『夢淵』と呼ばれています。東吉野村》。

夢淵のあたり
4.磐余邑(いわれのむら)顕彰碑 桜井市吉備(春日神社の北側)
碑の裏面には「神武天皇戌午年11月 兄磯城(えしき)を討ち給い 皇軍の虜(あた=敵)を破るや大軍集まりて磐余邑に充満せり聖蹟は此の地方なりと推せらる」。
國學院大學の「万葉神事語辞典」によると《「磐余」の旧名は片居(かたゐ)、片立(かたたち)で、式内石村山口神社には磐余山がある。地名は、「大きに軍集(いくさびとつど)ひて其の地に満(いは)めり。因りて号(な)を改め磐余と為す」の「満(いは)む=充満する」を由来とする。あるいは磯城(しき)の八十梟師(やそたける)が「屯聚居(いはみゐ)」(人が居住していること)の土地を、神武天皇の勝利により磐余邑と名付けたことから「磐余」の呼称が生まれたとも言う。神武天皇は「日本の磐余の立派な男子」を意味する国風諡号、神日本磐余彦(かむやまといはれびこ)天皇と称せられた》。

春日神社
5.神武天皇聖蹟鵄邑(とびのむら)顕彰碑 生駒市上町 出垣内バス停東南の丘(県立奈良北高校の北側)
碑の裏面には「神武天皇戊午年12月 皇軍を率いて長髄彦(ながすねひこ)の軍を御討伐あらせられたり時に 金鵄(きんし)の瑞(みず、ずい)を得させ給いしに因り 時人其の邑を鵄邑(とびのむら)と称せり聖蹟は此の地方なるべし」。
成田亨氏のHP「月の光」によると、『日本書紀』には《天鈴55年、紀元前663年(即位前3年)12月4日、磐余彦尊(いわれひこ)の軍はついに長髄彦(ながすねひこ)を討つことになった。しかし戦いを重ねたが、なかなか勝利をものに出来なかった。そのとき急に空が暗くなって雹(ひょう)が降り出した。そこへ金色の不思議な鵄(とび)が飛んできて、磐余彦尊の弓先に止まった。その鵄(とび)は光り輝いて、その姿はまるで雷光のようであった。このため長髄彦の軍の兵達は皆幻惑されて力を出すことが出来なかった》。
その続きはWikipedia「神武東征」に出ている。《長髄彦は神日本磐余彦(かむやまといわれひこ)の元に使いを送り、自らが祀る櫛玉饒速日命(くしたまにぎはやひ)は昔 天磐船(あめのいわふね)に乗って天降ったのであり、天津神(あまつかみ)が2人もいるのはおかしいから、あなたは偽物だろう、と言った。神日本磐余彦と長髄彦は共に天津神の御子の印を見せ合い、どちらも本物であることがわかった。しかし、長髄彦はそれでも戦いを止めようとしなかったので、饒速日命は長髄彦を殺して神日本磐余彦に帰順した》。

狭井神社の北側は「大美和の杜」
6.狭井河之上(さいがわのほとり)顕彰碑 桜井市茅原(狭井神社の北)
碑の裏面には「神武天皇 伊須気余理比賣命(いすけよりひめのみこと)の御家ありし狭井河之上に行幸あらせられたり聖蹟は此の地付近なりと推せらる」。
神武天皇の皇后は三嶋(大阪府三島郡)の溝咋(ミゾクヒ)の娘・比賣多多良伊須氣余理比賣(ヒメタタライスケヨリヒメ)、別名富登多多良伊須須岐比賣(ホトタタライススキヒメ)、『日本書紀』では媛蹈鞴五十鈴媛命である。『古事記』によると、《是(ここ)に其(そ)の伊須氣余理比賣命の家、狭井河の上に在りき。(神武)天皇、其の伊須氣余理比賣の許(もと)に幸行(い)でまして、一宿御寝(ひとよみね)し坐(ま)しき》とある。
Wikipedia「ヒメタタライスズヒメ」によると《神武天皇は、東征以前の日向ですでに吾平津姫を娶り子供も二人いたが、大和征服後、在地の豪族の娘を正妃とすることで、在地豪族を懐柔しようとした。天照大神の子孫である神武天皇とヒメタタライスケヨリヒメ(比賣多多良伊須氣余理比賣)が結婚することで、天津神系と国津神系に分かれた系譜がまた1つに統合されることになる。(中略) 皇后の名の中にある「タタラ」とは、たたら吹き製鉄の時に用いられる道具であり、このことは、皇后の出身氏族が、製鉄と深い関係がある出雲(現 島根県安来地方)地域であったことを物語っている》。
《『古事記』では、三輪大物主神(スサノオの子孫大国主の和魂とされる)と勢夜陀多良比売(セヤダタラヒメ)の娘である。勢夜陀多良比売が美人であるという噂を耳にした大物主は、彼女に一目惚れした。大物主は赤い矢に姿を変え、勢夜陀多良比売が用を足しに来る頃を見計らって川の上流から流れて行き、彼女の下を流れていくときに、ほと(陰所)を突いた。彼女がその矢を自分の部屋に持ち帰ると大物主は元の姿に戻り、二人は結ばれた。こうして生れた子がヒメタタライスケヨリヒメである》。
《ホトを突かれてびっくりして生まれた子であるということでホトタタライススキヒメ(富登多多良伊須須岐比賣)と名づけ、後に「ホト」を嫌ってヒメタタライスケヨリヒメに名を変えた》《神武天皇との子は、上から順に、日子八井命、神八井耳命、綏靖天皇(第 2代天皇)である。神武天皇の死後、神武天皇の子である手研耳命(タギシミミ)と結婚するも、タギシミミの反逆において子供たちに夫の謀意について知らせて反逆を防いだ》。
7.鳥見山中靈畤(とみやまなかのまつりのにわ)顕彰碑 桜井市(等彌神社の南側)
碑の裏面には「神武天皇御東征の鴻業を遂げさせ給い 橿原宮に御即位後4年2月 鳥見山中に靈畤(まつりのにわ)を立てて皇祖天神を祭らせられ大孝を申(の)べ給えり聖蹟は此の地付近と伝えらる」。

等彌神社から、丘を少し登る
奈良検定テキスト(『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』)によると等彌神社(桜井市桜井)は《上ツ尾社と下ツ尾社があり、上ツ尾社が本社で大日孁貴尊を祀り、下ツ尾社では品陀和気命と天兒屋根命を祀る。社記によると元は鳥見山中にあったが、天永三年(一一一二)五月に大雨があり、山崩れのため、社殿が谷に埋没した。この年悪疫が流行したので、九月五日、山の尾の現在の場所に遷座したとある。鳥見山は神武天皇神話の伝承地であり、旧社地は「庭殿」「白山」「祭場」などの伝説地でもある。能登宮とも称し、中世は多武峰妙楽寺の支配下であった》。

また同社のご由緒によると《上社(上津尾社)より鳥見山々頂へ道が続いている。この山は神武天皇御即位の後四年春二月鳥見の山中に霊畤を立て大孝を述べ給うた大嘗会の舞台で毎年五月十三日鳥見靈畤顕彰会により、お山の拝所で大祭が斎行されている》。
『古事記』の登場人物で、最も奈良県に関係が深く、また全国的によく知られているのが神武天皇である。その足跡が現在も顕彰碑として残されているのである。ツアーに参加されない方も、ぜひ顕彰碑のいくつかを訪ね、神話の世界を体感していただきたい。
来たる3/24(土)、仲間と作る「第9回古社寺を歩こう会」の主催で、これら7ヵ所全てを1日で回るバスツアーを行う。今日はそれに先だち、7つの碑の解説を以下に掲載しておく。ツアーに参加する人もしない人も、「古事記完成1300年」の今年には、頭の片隅に入れておいていただきたい知識である。記紀の登場順に紹介する。
1.神武天皇聖蹟菟田穿邑(うだのうかちのむら)顕彰碑 宇陀市菟田野宇賀志 八坂神社(村社)の近く
顕彰碑の裏面にはこう書かれている(表記を読みやすく改め、カッコ内に振り仮名をつけた。以下同じ)。「神武天皇戊午年(つちのえうまのとし)年頭 八咫烏(やたがらす)の郷導(ごうどう)に依り 道臣命を皇軍の将として菟田穿邑に至り給えり聖蹟は此の地方なるべし」。
※トップ写真は「菟田穿邑顕彰碑」。撮影は3/10(以下同じ)
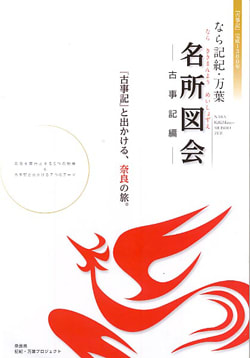
県の『なら記紀万葉 名所図会 古事記編』。電子ブック版は、こちら
伊波礼毘古命(いわれびこのみこと=神武天皇)は、八咫烏の案内で、熊野から大和の宇陀に至った。県の『なら記紀万葉 名所図会 古事記編』の「2.八咫烏、引道(みちび)きてむ」によると《険しき深山に分け入り、道を穿(うが)つようにして進みながら、ようやく一行は宇陀へたどり着く。この宇陀の穿(うかち)という地には、兄宇迦斯(えうかし)と弟宇迦斯(おとうかし)という兄弟がいた。まず八咫烏を遣わして「今、天つ神の御子がお見えになったが、お前たちは御子に仕えるか?」と尋ねると、兄宇迦斯は八咫烏めがけて鏑矢を射放ち、追い返してしまった》。
《兄宇迦斯は伊波礼毘古命一行を迎え撃とうとしたが、十分な軍勢が確保できず、ひとまず帰順する振りをする。大きな御殿を建てて、その内部にはいった者を圧(お)し殺す「押機(おし)」という罠を仕掛けて、伊波礼毘古命を待ち受けた。しかし弟宇迦斯が兄の企みを事前に密告。そこで道臣命(みちのおみのみこと 大伴連らの祖先)と大久米命(おおくめのみこと 久米直らの祖先)の2人が、「汝が建てた御殿だろう。まずは自らが中に入ってみせてみよ」と御殿に追い詰める。追われた兄宇迦斯は自ら作った罠にかかり、命を落としたという。以来、この地を「血原(ちはら)」というようになった》。

2.菟田高倉山(うだのたかくらやま)顕彰碑 宇陀市大宇陀守道 高倉山頂
顕彰碑の裏面には「神武天皇戊午年9月 菟田高倉の頂に登り給いて域中の虜軍(敵軍)の形勢を瞻望(せんぼう=遠くを見渡す)し給えり聖蹟は此の地なりと伝えらる」
Wikipedia「神武天皇」によると《9月、磐余彦(いわれびこ=神武天皇)は高倉山に登ると八十梟帥(やそたける)や兄磯城(えしき)の軍が充満しているのが見えた。磐余彦は深く憎んだ。高皇産霊尊(たかみむすひのみこと)が夢に現れ、その言葉に従って天平瓦と御神酒の器をつくって天神地祇を祀り、勝利を祈願した》。

高倉山頂には顕彰碑のほか、こんな碑も建っていた
3.丹生川上(にふのかわかみ)顕彰碑 東吉野村(丹生川上神社中社摂社 丹生神社北側)
碑の裏面には「神武天皇戊午年9月 天下平定の為 平瓮(ひらか)及び厳瓮(いつべ)を造り給い丹生川上に陟(のぼ)りて天神地祇を祭らせられ又丹生之川に厳瓮を沈めて祈り給えり聖蹟は此の地付近なり」。
上記2の「天平瓦と御神酒の器をつくって天神地祇を祀り、勝利を祈願した」というくだりは、『日本書紀』に出てくる(丹生川上神社[中社]の公式HPが、その全文を紹介している)。川べりに、このくだりを分かりやすく紹介する案内板があった。そこには《昭和15年(1940年)2月7日、文部省による神武聖蹟調査の第1回目の決定があり、「丹生川上の地」は小川村(現東吉野村)丹生川上神社の付近であると発表された》。

丹生川上顕彰碑。周囲は鬱蒼とした林なので、碑はこんな色になっていた
《日本書紀によると、戊午の年9月、神武天皇は、大和平定のため、夢にあらわれた天神の教えのとおり、天香具山の社の中の土を取って平瓮(ひらか)と厳瓮(いつべ 御神酒を入れる瓮)をつくり、丹生の川上にのぼって天神地祇を祀られた。神意を占って「厳瓮を丹生川に沈めよう。もし魚が大小となく全部酔って流れるのが真木の葉の浮き流れるようであれば自分はきっとこの國を平定するだろう」と言われて厳瓮を丹生川に沈めた。しばらくすると魚はみな浮き上がって口をパクパク開いた》。占いで浮かび上がってきた魚なので、アユは「鮎」と書くようになったそうだ。
《椎根津彦がそのことを報告すると、天皇は大いにお喜びになられ丹生の川上の五百箇の榊を根こそぎにして諸々の神をお祀りされた。このときから祭儀のときに御神酒瓶が置かれるようになった。丹生川は、今の高見川で、高見・四郷・日裏の三川が合流したところの深淵は、神武天皇が夢にあらわれた天神の教えによって厳瓮を沈めたところだと伝えられ、『夢淵』と呼ばれています。東吉野村》。

夢淵のあたり
4.磐余邑(いわれのむら)顕彰碑 桜井市吉備(春日神社の北側)
碑の裏面には「神武天皇戌午年11月 兄磯城(えしき)を討ち給い 皇軍の虜(あた=敵)を破るや大軍集まりて磐余邑に充満せり聖蹟は此の地方なりと推せらる」。
國學院大學の「万葉神事語辞典」によると《「磐余」の旧名は片居(かたゐ)、片立(かたたち)で、式内石村山口神社には磐余山がある。地名は、「大きに軍集(いくさびとつど)ひて其の地に満(いは)めり。因りて号(な)を改め磐余と為す」の「満(いは)む=充満する」を由来とする。あるいは磯城(しき)の八十梟師(やそたける)が「屯聚居(いはみゐ)」(人が居住していること)の土地を、神武天皇の勝利により磐余邑と名付けたことから「磐余」の呼称が生まれたとも言う。神武天皇は「日本の磐余の立派な男子」を意味する国風諡号、神日本磐余彦(かむやまといはれびこ)天皇と称せられた》。

春日神社
5.神武天皇聖蹟鵄邑(とびのむら)顕彰碑 生駒市上町 出垣内バス停東南の丘(県立奈良北高校の北側)
碑の裏面には「神武天皇戊午年12月 皇軍を率いて長髄彦(ながすねひこ)の軍を御討伐あらせられたり時に 金鵄(きんし)の瑞(みず、ずい)を得させ給いしに因り 時人其の邑を鵄邑(とびのむら)と称せり聖蹟は此の地方なるべし」。
成田亨氏のHP「月の光」によると、『日本書紀』には《天鈴55年、紀元前663年(即位前3年)12月4日、磐余彦尊(いわれひこ)の軍はついに長髄彦(ながすねひこ)を討つことになった。しかし戦いを重ねたが、なかなか勝利をものに出来なかった。そのとき急に空が暗くなって雹(ひょう)が降り出した。そこへ金色の不思議な鵄(とび)が飛んできて、磐余彦尊の弓先に止まった。その鵄(とび)は光り輝いて、その姿はまるで雷光のようであった。このため長髄彦の軍の兵達は皆幻惑されて力を出すことが出来なかった》。
その続きはWikipedia「神武東征」に出ている。《長髄彦は神日本磐余彦(かむやまといわれひこ)の元に使いを送り、自らが祀る櫛玉饒速日命(くしたまにぎはやひ)は昔 天磐船(あめのいわふね)に乗って天降ったのであり、天津神(あまつかみ)が2人もいるのはおかしいから、あなたは偽物だろう、と言った。神日本磐余彦と長髄彦は共に天津神の御子の印を見せ合い、どちらも本物であることがわかった。しかし、長髄彦はそれでも戦いを止めようとしなかったので、饒速日命は長髄彦を殺して神日本磐余彦に帰順した》。

狭井神社の北側は「大美和の杜」
6.狭井河之上(さいがわのほとり)顕彰碑 桜井市茅原(狭井神社の北)
碑の裏面には「神武天皇 伊須気余理比賣命(いすけよりひめのみこと)の御家ありし狭井河之上に行幸あらせられたり聖蹟は此の地付近なりと推せらる」。
神武天皇の皇后は三嶋(大阪府三島郡)の溝咋(ミゾクヒ)の娘・比賣多多良伊須氣余理比賣(ヒメタタライスケヨリヒメ)、別名富登多多良伊須須岐比賣(ホトタタライススキヒメ)、『日本書紀』では媛蹈鞴五十鈴媛命である。『古事記』によると、《是(ここ)に其(そ)の伊須氣余理比賣命の家、狭井河の上に在りき。(神武)天皇、其の伊須氣余理比賣の許(もと)に幸行(い)でまして、一宿御寝(ひとよみね)し坐(ま)しき》とある。
Wikipedia「ヒメタタライスズヒメ」によると《神武天皇は、東征以前の日向ですでに吾平津姫を娶り子供も二人いたが、大和征服後、在地の豪族の娘を正妃とすることで、在地豪族を懐柔しようとした。天照大神の子孫である神武天皇とヒメタタライスケヨリヒメ(比賣多多良伊須氣余理比賣)が結婚することで、天津神系と国津神系に分かれた系譜がまた1つに統合されることになる。(中略) 皇后の名の中にある「タタラ」とは、たたら吹き製鉄の時に用いられる道具であり、このことは、皇后の出身氏族が、製鉄と深い関係がある出雲(現 島根県安来地方)地域であったことを物語っている》。
《『古事記』では、三輪大物主神(スサノオの子孫大国主の和魂とされる)と勢夜陀多良比売(セヤダタラヒメ)の娘である。勢夜陀多良比売が美人であるという噂を耳にした大物主は、彼女に一目惚れした。大物主は赤い矢に姿を変え、勢夜陀多良比売が用を足しに来る頃を見計らって川の上流から流れて行き、彼女の下を流れていくときに、ほと(陰所)を突いた。彼女がその矢を自分の部屋に持ち帰ると大物主は元の姿に戻り、二人は結ばれた。こうして生れた子がヒメタタライスケヨリヒメである》。
《ホトを突かれてびっくりして生まれた子であるということでホトタタライススキヒメ(富登多多良伊須須岐比賣)と名づけ、後に「ホト」を嫌ってヒメタタライスケヨリヒメに名を変えた》《神武天皇との子は、上から順に、日子八井命、神八井耳命、綏靖天皇(第 2代天皇)である。神武天皇の死後、神武天皇の子である手研耳命(タギシミミ)と結婚するも、タギシミミの反逆において子供たちに夫の謀意について知らせて反逆を防いだ》。
7.鳥見山中靈畤(とみやまなかのまつりのにわ)顕彰碑 桜井市(等彌神社の南側)
碑の裏面には「神武天皇御東征の鴻業を遂げさせ給い 橿原宮に御即位後4年2月 鳥見山中に靈畤(まつりのにわ)を立てて皇祖天神を祭らせられ大孝を申(の)べ給えり聖蹟は此の地付近と伝えらる」。

等彌神社から、丘を少し登る
奈良検定テキスト(『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』)によると等彌神社(桜井市桜井)は《上ツ尾社と下ツ尾社があり、上ツ尾社が本社で大日孁貴尊を祀り、下ツ尾社では品陀和気命と天兒屋根命を祀る。社記によると元は鳥見山中にあったが、天永三年(一一一二)五月に大雨があり、山崩れのため、社殿が谷に埋没した。この年悪疫が流行したので、九月五日、山の尾の現在の場所に遷座したとある。鳥見山は神武天皇神話の伝承地であり、旧社地は「庭殿」「白山」「祭場」などの伝説地でもある。能登宮とも称し、中世は多武峰妙楽寺の支配下であった》。

また同社のご由緒によると《上社(上津尾社)より鳥見山々頂へ道が続いている。この山は神武天皇御即位の後四年春二月鳥見の山中に霊畤を立て大孝を述べ給うた大嘗会の舞台で毎年五月十三日鳥見靈畤顕彰会により、お山の拝所で大祭が斎行されている》。
『古事記』の登場人物で、最も奈良県に関係が深く、また全国的によく知られているのが神武天皇である。その足跡が現在も顕彰碑として残されているのである。ツアーに参加されない方も、ぜひ顕彰碑のいくつかを訪ね、神話の世界を体感していただきたい。
















