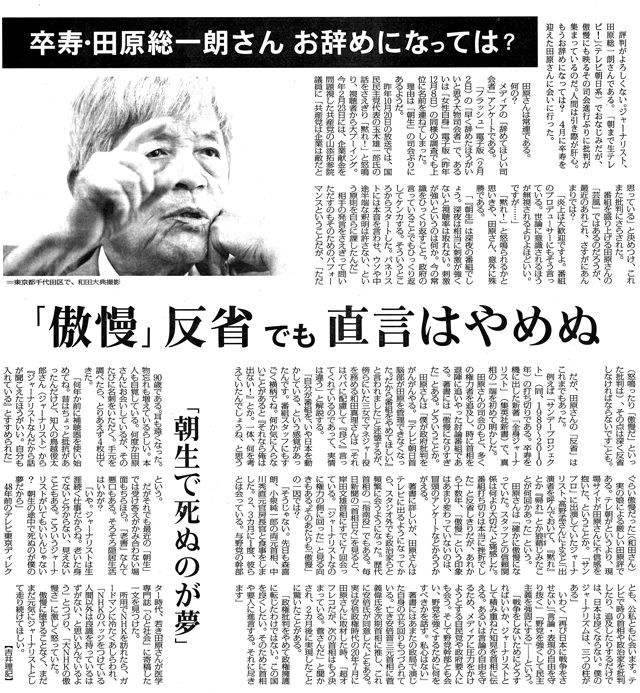久々に「田中利典師曰く」をお届けする。今回は〈蔵王供正行36日目 「フェイスブック恐るべし…」〉(師のブログ2015.6.5 付)である。師はお行の間もSNS(ブログとFB)での情報発信は継続されており、それを見て来られる参拝者も多い。このような発信は、やはり必要なのである。では、全文を紹介する。
※トップ写真は、吉野山の桜(2024.4.5 撮影)
「フェイスブック恐るべし…」
蔵王供正行36日目(6月5日)。雨。今日の一日。
5時に起床。
5時40分、第71座目蔵王権現供養法修法 於脳天堂
7時、本堂法楽・法華懺法 於本堂
9時、第72座目蔵王権現供養法修法 於脳天堂
10時10分、本堂法楽・例時作法 於本堂
12時半、水行 於風呂場
13時、法楽護摩供修法 於脳天堂
14時、法楽勤行 於本堂
参拝者3名。村岡町(兵庫県美方郡香美町村岡区)から吉川さんご家族が来山。護摩に随喜していただく。
****************
「フェイスブック恐るべし…」
何度か書いたが、今回4月28日の前行入行、そして5月1日の正行以来、天気が続いていた。今月3日と昨日は朝から雨だったが、夕方には晴れ間が出たりして、丸一日雨という日がほとんどなかった。今日の雨はほんとに、梅雨らしい雨となった。
22年前の千座護摩がものすごい雨の多い修行で、雨害のため、タイ米を緊急輸入する事態が起きたほど悪天候だっただけに、今回の天気周りの良さは予想外である。
さて今日はそんな足元の悪い中、私の全日本仏教青年会での副理事長時代に、大樹理事長のもとで事務局長を務めたおられた吉川さんが、行見舞いにご家族で来山された。実はフェイスブックのイベント招待でご案内したので、わざわざ村岡町からお尋ねいただいたのだ。
こうしてみると、フェイスブック恐るべしで、ほかにもフェイスブックがらみで、おいでいただいた方が何人かいる。あいかわらず、自坊の信者さんのお参りはからきしだが、それだけにフェイスブックの力の大きさを感じる。
今回、修行に入るので、SNSは封じようかとも思ったが、田舎の寺でこれから活動していくのに、情報発信をおこなうツールを手放すのは少々躊躇した。第一、祈祷申し込みやお札発送の事務作業をしながらの修行なので、通常のように、「諸縁を絶つ」というような形では行が出来ない。
「山の行より里の行」と謳っての修行だし、諸縁の中で行じさせていただいているので、最小限のFBやブログ発信は続けさせていただいた。
そのお蔭で、今日も又、お参りいただくことが出来た。吉川さんは但馬・村岡町の天台宗寺院のご住職だが、おなじ山陰地方とはいえ、但馬と丹波の交流は少ない。全日仏青から、すでに10数年が過ぎているが、有り難いご縁がSNSで繋がったのである。
※トップ写真は、吉野山の桜(2024.4.5 撮影)
「フェイスブック恐るべし…」
蔵王供正行36日目(6月5日)。雨。今日の一日。
5時に起床。
5時40分、第71座目蔵王権現供養法修法 於脳天堂
7時、本堂法楽・法華懺法 於本堂
9時、第72座目蔵王権現供養法修法 於脳天堂
10時10分、本堂法楽・例時作法 於本堂
12時半、水行 於風呂場
13時、法楽護摩供修法 於脳天堂
14時、法楽勤行 於本堂
参拝者3名。村岡町(兵庫県美方郡香美町村岡区)から吉川さんご家族が来山。護摩に随喜していただく。
****************
「フェイスブック恐るべし…」
何度か書いたが、今回4月28日の前行入行、そして5月1日の正行以来、天気が続いていた。今月3日と昨日は朝から雨だったが、夕方には晴れ間が出たりして、丸一日雨という日がほとんどなかった。今日の雨はほんとに、梅雨らしい雨となった。
22年前の千座護摩がものすごい雨の多い修行で、雨害のため、タイ米を緊急輸入する事態が起きたほど悪天候だっただけに、今回の天気周りの良さは予想外である。
さて今日はそんな足元の悪い中、私の全日本仏教青年会での副理事長時代に、大樹理事長のもとで事務局長を務めたおられた吉川さんが、行見舞いにご家族で来山された。実はフェイスブックのイベント招待でご案内したので、わざわざ村岡町からお尋ねいただいたのだ。
こうしてみると、フェイスブック恐るべしで、ほかにもフェイスブックがらみで、おいでいただいた方が何人かいる。あいかわらず、自坊の信者さんのお参りはからきしだが、それだけにフェイスブックの力の大きさを感じる。
今回、修行に入るので、SNSは封じようかとも思ったが、田舎の寺でこれから活動していくのに、情報発信をおこなうツールを手放すのは少々躊躇した。第一、祈祷申し込みやお札発送の事務作業をしながらの修行なので、通常のように、「諸縁を絶つ」というような形では行が出来ない。
「山の行より里の行」と謳っての修行だし、諸縁の中で行じさせていただいているので、最小限のFBやブログ発信は続けさせていただいた。
そのお蔭で、今日も又、お参りいただくことが出来た。吉川さんは但馬・村岡町の天台宗寺院のご住職だが、おなじ山陰地方とはいえ、但馬と丹波の交流は少ない。全日仏青から、すでに10数年が過ぎているが、有り難いご縁がSNSで繋がったのである。