都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
 「おかあさん」の語源は、平安時代に身分の高い人の奥方のことを「おかたさま」呼んだことにあります。
「おかあさん」の語源は、平安時代に身分の高い人の奥方のことを「おかたさま」呼んだことにあります。
高貴な人の奥方に住む部屋は、寝殿造り(しんでんづくり)の建物の北に方角と決まっていたそうです。そのため、「北の方」いたのが、「方」をとって、「おかたさま」と呼ばれるようになります。それが時代を経て「おかかさま」、「おかあさん」に変わってきたといわれています。
お‐かあ‐さん【▽御母さん】
1 子供が自分の母親を呼ぶ語。また、子供にとって母親のこと。もとは江戸末期、京坂地方の中流以上の家庭で使われていた。江戸の庶民は「おっかさん」「おっかあ」などと呼んでいたが、「おとうさん」とともに明治37年から使用した文部省「尋常小学読本」(国定教科書)に採用されて、全国的に広まった。「―、誕生日おめでとう」
2 第三者がその人子の母親を親しみを込めて呼ぶ語。「新聞の集金ですが、―はご在宅ですか」「あなたの―はいつもお元気そうで何よりですね」
3 子供のいる家庭で、家族が子供の母親を呼ぶ語。子供の視点に立って、父親が妻を、祖父母が娘を指して言う語。「―、幸子ちゃんの帽子はどこですか」
4 子供をもつ女性を親しんで呼ぶ語。また、子供をもつ母親のこと。「子育て中の―」
5 母親が自分を指して言う語。「―といっしょに絵本を見ましょう」
6 (特に「お義母さん」と書く場合)配偶者や婚約者の母親のこと。
7 芸妓・女郎が、置屋や茶屋の女主人を敬って呼ぶ語。
◆第三者に対して自分の母親をいう場合、公の場や手紙文などでは「お母さん」ではなく、通常「母」を用いる。
大辞泉
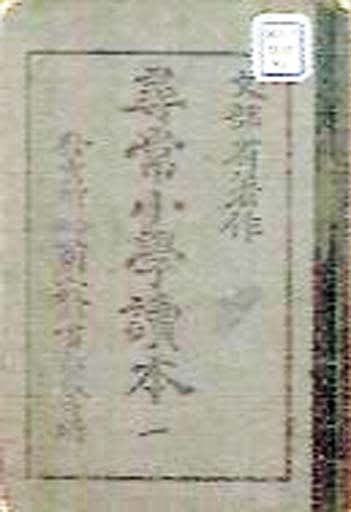 しかし、「おかあさん」が広く使われるようになったのは、「大辞泉」にもあるように、明治時代の後半以降のことだそうです。明治36年発行の「尋常小学校読本」で、「オカアサン、オハヨウゴザイマス」、「オカアサン、オヤスミナサイ」と教え始めてからのことだそうです。
しかし、「おかあさん」が広く使われるようになったのは、「大辞泉」にもあるように、明治時代の後半以降のことだそうです。明治36年発行の「尋常小学校読本」で、「オカアサン、オハヨウゴザイマス」、「オカアサン、オヤスミナサイ」と教え始めてからのことだそうです。
江戸時代までは、一般に武士は「おかかさま」、町人は「おっかさん」「おっかあ」と読んでいたそうです。上方では幕末の頃すでに中流以上の家では「あかあさん」という言い方をしているところもあったそうです。
上方の「おかあさん」が全国制覇・・・。「恵方巻き」も上方発・・・。そのうち、関西弁が標準語になるんとちゃうのん?
今でも、江戸時代の人、私は知っています。
したっけ。



















