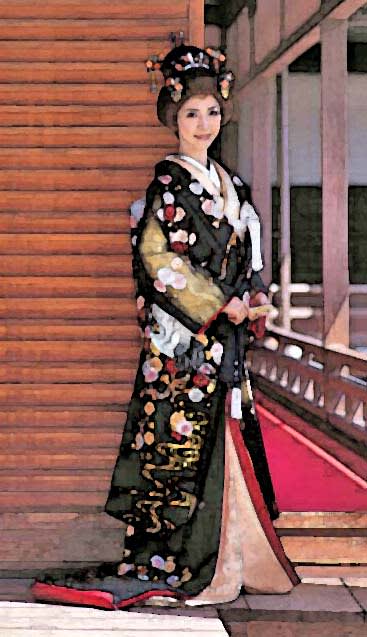都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
妻女を呼ぶ言葉に、「夫人」、「細君(さいくん)」、「女房」などがあります。今では、「奥様」、「奥さん」と呼ぶのが一般的ですね。
※「妻君」は当て字です。
今でこそ誰でも使っている「奥様」は、江戸時代には旗本の妻女に限って使われていたのです。
身分格式がやかましかった江戸時代において、身分によって妻女をどう呼び分けていたのでしょうか。
御三家、御三卿:「御簾中(ごれんじゅう)」
10万石以上の大名:「御前様(ごぜんさま)」
10万石以下の大名:「奥方」
旗本:「奥様」
御家人:「御新造様(ごしんぞうさま)」
庶民:「おかみさん」
ご‐さんけ【御三家】
徳川家康の第9子義直を祖とする尾州家、第10子頼宣(よりのぶ)を祖とする紀州家、第11子頼房を祖とする水戸家のこと。
ご‐さんきょう【御三卿】
徳川将軍家の一族で、田安・一橋・清水の三家をさす。田安は8代将軍吉宗の子で宗武、一橋は同じく宗尹(むねただ)、清水は9代将軍家重の子で重好に始まる。三卿。
はた‐もと【旗本】
1 戦場で大将のいる本陣。本営。2 大将に直属し、本陣を守る役目の武士。幕下(ばっか)。麾下(きか)。旗下(きか)。3 江戸時代、将軍家直参(じきさん)で、1万石未満、御目見(おめみえ)以上の武士。
ご‐けにん【御家人】
江戸時代、将軍直属の家臣のうち、御目見(おめみえ)以下の者。
大辞泉
 妻女を呼ぶにもこのような格式があるとは、随分と面倒な時代だったようです。
妻女を呼ぶにもこのような格式があるとは、随分と面倒な時代だったようです。
因みに、主人のことは、将軍家では「公方様(くぼうさま)」、大名家では「殿様(とのさま)」、旗本でも「殿様」、御家人では「旦那様」、町家でも「旦那様」だったそうです。
庶民の妻女も今では「奥様」。旗本並みに格上げになったようです。
※御新造様にも色々説がありますので下記を参照ください。
したっけ。