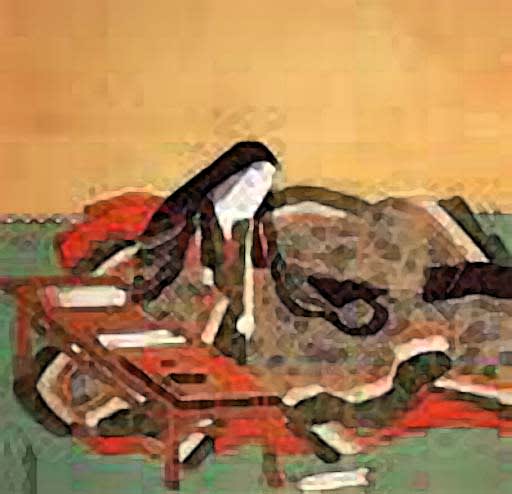都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
たらちね【垂乳根】
《枕詞「たらちねの」から》
1 母。母親。
「―の消えやらで待つ露の身を風より先にいかでとはまし」〈増鏡・新島守〉
2 親。両親。父母。
「―はいかに哀れと思ふらむ三年になりぬ足たたずして」〈今鏡・六〉
3 父。父親。
「―もまた垂乳女(たらちめ)もうせはてて頼む陰なき歎きをぞする」〈拾玉集・一〉
たらちね‐の【垂乳根の】
[枕]「母」「親」にかかる。語義・かかり方未詳。 「―母が問はさば風と申(まを)さむ」〈万・二三六四〉 「―親のいさめし転寝(うたたね)は」〈拾遺・恋四〉
大辞泉
万葉集の訓仮名表記には「垂乳根乃」「足乳根乃」が多く、かつては、乳房が垂れた、乳の満ち足りたなどの語源解釈がされていたようです。語源は、「母」。即ち、「たら」は「垂らす」、「ち」は「乳」、「ね」は「女性」という解釈です。
『たらちねの母が呼ぶ名を申さめど 道行く人を誰れと知りてか』(作者未詳:万葉集)
足千根乃 母之召名乎 雖白 路行人乎 孰跡知而可
読み:[たらちねの] ははがよぶなを まをさめど みちゆくひとを たれとしりてか
あなたは ただの行きずりの人
母が呼ぶ私の名をお教えしたいのですが
通りすがりのあなたが誰かも知りません
たとえ高貴なお方でも お教えできません
しかし「垂る」「足る」ともに四段活用動詞(語形が五十音図のア・イ・ウ・エの四段の音で語形変化するもの)であり、未然形に名詞の接続する「たら乳」という言葉は不自然だといわれています。
 一説に、「たらち」は「たらし」の転で、「満ち足りた」の意を表すほめ言葉「ね」は女性に対する親愛の気持ちを表す接尾語ともいいますが、未詳。
一説に、「たらち」は「たらし」の転で、「満ち足りた」の意を表すほめ言葉「ね」は女性に対する親愛の気持ちを表す接尾語ともいいますが、未詳。
枕詞の「垂乳根の」は「母」または「親」にかかります。ですから、母親限定の解釈は適当ではありません。
「たらちね」は、もと母の意。のちに母を「たらちめ」、父を「たらちを」と分け、やがて両親を「たらちね」と呼ぶようになったともいわれますが未詳です。
落語「たらちね」
長屋でただ一人の独り者の八五郎のところに、大家が縁談を持ちかけてきます。
年は十九で、近所の医者の姪だという。
器量は十人並み以上、夏冬の着物もそろえているという、まことに結構な話。
結構すぎて眉唾なくらい。
「そんな女が、あっしのような男のところへ来るわけがない。なんか、疵(きず)でもあるんじゃないですか」
「ないと言いたいが、たった一つだけある。もとは京の名家の出で、言葉が女房言葉。
馬鹿丁寧すぎてまるきりわからないという。この間も、目に小石が入った時、ケサハドフウハゲシュウシテ、ショウシャガンニュウス(今朝は怒風激しゅうして、小砂眼入す)」と、のたもうたそうな。
「そんなことはなんでもない」と八五郎が承諾したので、その日のうちに祝言となりました。
なるほど美人なので、八五郎は大喜びだが、いざ話す段になると、これが相当なもの・・・。
名を聞くと「そも我が父は京都の産にして姓は安藤名は慶三あざなを五光、母は千代女と申せしが、わが母三十三歳の折、ある夜丹頂の鶴の夢を見てはらめるがゆえに、たらちねの胎内を出でしときは鶴女と申せしがそれは幼名、成長の後これを改め清女と申しはべるなぁりいー」
「ナアムミョウ、チーン、ご親類の方からご焼香を・・・」
これではかみ合いません。
ネギが一文字草、米はしらげと、通訳がいるくらい。
朝起きれば起きたで「アーラ、わが君、しらげのありかはいずこなりや」
「頼むから、その“アーラわが君”てえのはやめてくれ」と言っているところへ、葱屋がやって来ました。
「こーれ、門前に市をなす商人、一文字草を朝餉(あさげ)のため買い求めるゆえ、門の敷居に控えておれ」
「へへへー」
ようやく味噌汁ができたが、「アーラわが君。日も東天に出御ましまさば、うがい手水に身を清め、神前仏前へ燈灯(みあかし)を備え、御飯も冷飯に相なり候へば、早く召し上がって然るべう存じたてまつる、恐惶謹言(きょうこうきんげん)」
「飯を食うのが恐惶謹言なら、酒ならよって(=酔って)件の如しか・・・」
きょうこう‐きんげん【恐惶謹言】
《おそれつつしんで申しあげる意》改まった手紙の末尾に書き添え、相手に敬意を表す語。恐惶敬白。
大辞泉
したっけ。