都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
 もり蕎麦はなぜ「蒸籠(せいろ・そいろう)」に盛られているのでしょう。水気を切るためといわれれば、その通りでしょう。ただ水を切るためだけなら、わざわざ「蒸籠」にする必要はないと思います。簾(すだれ)状のものが下に敷かれていれさえすればいいのですから。
もり蕎麦はなぜ「蒸籠(せいろ・そいろう)」に盛られているのでしょう。水気を切るためといわれれば、その通りでしょう。ただ水を切るためだけなら、わざわざ「蒸籠」にする必要はないと思います。簾(すだれ)状のものが下に敷かれていれさえすればいいのですから。
蕎麦といえば、昔は「蕎麦切り」言われたようです。
現在の一般的な蕎麦の食べ方と言えば、蕎麦を茹でて水で洗ったものを、冷たい蕎麦なら「笊(ざる)」や「皿」にもって汁につけて食べます。
暖かい蕎麦なら洗った蕎麦をもう一度温め、椀に入れて熱い汁をかけて食べる、いわゆる「掛け蕎麦」が知られています。
ただ、今でこそ当たり前なこの食べ方が、蕎麦切りが発生した当時は少し違ったものだったようです。
江戸で「蕎麦切り」の言葉が最初に見られる書物は『慈性日記』(近江の僧侶)で、1614年(慶弔19年)2月3日に「常明寺でそば切りを振舞われた」と書いてあるものだとされてきました。
ところが、最近になって木曽郡大桑村の臨済宗妙心寺派の寺「定勝寺」が、1574年(天正2年)に仏殿の修理を行った時の『番匠作事日記』の3月16日の条に、落成祝いに寄進された品物が書いてあり、中に「徳利一ツ、ツハフクロ一ツ 千淡内」、「振舞ソハキリ 金永」と書かれていたことが発見されたそうです。
また、食べ方の初見は『中山日録』(尾張公のお供で旅した儒者堀杏庵による)に1636年(寛永13年)4月4日のこととして「蕎麦切は冷麦のように長細く冷たく作られている。少量の味醤を加え、鰹粉と葱韮(そうきゅう、葱類)を入れた大根の絞り汁で、この蕎麦を食べる。大まかに噛んで食すると、味わいはまことに良い。」とあるそうです。
麺としての蕎麦・蕎麦切は寺で出されるか、茶の席で出されるかで、しばらくは庶民の食べ物では無かったようです。
「蕎麦切り」が発明された当時は蒸し蕎麦が主流だったということです。蕎麦はうどん粉(小麦粉)などと違い、非常に繋がりにくく麺にするのは難しかったのです。
当時の蕎麦は十割蕎麦だったために、「蕎麦切り」の考案によって、なんとか麺にするところまではたどり着きましたが、まだまだ茹でて洗うなどといった手法に耐えうるほどの強度を、当時の「切り蕎麦」は持ち合わせていなかったようです。
そこで考えられたのが「蒸籠(せいろ)」で蒸すことでした。しかも、その発想は当時、蒸籠を使っていた菓子屋から出たようです。菓子屋で蒸した蕎麦を出していたようです。
「蕎麦切り」の製法を記した最初の記録は、1643年(寛永20年)に出された『料理物語(著者不詳)』だそうです。この記述によれば、そばは茹でてから蒸して仕上げると書かれているそうです。
そして、この後「蒸し蕎麦切り」と称し、湯通しせず蒸籠で蒸すだけのそばが流行るようになったということです。
今でも蕎麦屋に入ると、蒸籠にもった蕎麦を「蒸籠蕎麦(せいろそば)」と品書きに表示している所がありますが、この名残だそうです。
では、「蒸し蕎麦」を、当時はどのようにして汁をつけて食べていたのでしょう。蒸したそばを平椀や皿にもって食べたことは分かっているのですが、汁をどのようにつけて食べていたかは、正確には分かっていないそうです。
1692年(元禄5年)に出された艸田寸木子(くさだすんぼくし)の『女重宝記(おんなちょうほうき)』には、「そうめんの食べ方」という女性のための教訓が書かれているそうです。それによると。「そうめんは汁の器に椀からすくい入れて食べる」と書かれているそうです。
うどんも同様としているため、蕎麦も同じように食べられていたと考えるのが自然です。すなわち、最初から現在の「ざるそば」の食べ方、だったと推測されます。
また、「女重宝記」は、女は男のように汁をかけて食べてはいけないと書かれていて、皿または椀にもったそばに直接汁をかけて食べる、いわゆる「ぶっかけ」で食べる男がいたことも伺えるということです。
現在、冷たいそばと言えば「もり」か「ざる」ですが、名称自体の登場は「ざる」の方が早いそうです。
 「ざるそば」の元祖は、江戸中期に深川洲崎にあった「伊勢屋」で、竹で編んだ笊(ざる)に盛って「ざる」と名乗り評判になったということが、1735年(享保20年)刊の『続江戸砂子(えどすなご)』に江戸の名物として紹介されているそうです。
「ざるそば」の元祖は、江戸中期に深川洲崎にあった「伊勢屋」で、竹で編んだ笊(ざる)に盛って「ざる」と名乗り評判になったということが、1735年(享保20年)刊の『続江戸砂子(えどすなご)』に江戸の名物として紹介されているそうです。
これは、「もり」という形態の蕎麦は早くからあったのですが、「ざる」という名称が出現したが「もり」という名称で呼ばれたのは、その後のことだったということです。
1751年(寛延4年)刊『蕎麦全書』には、「ぶっかけ」は新材木町(現在の日本橋あたり)にあった「信濃屋」が始まりと書かれているそうです。
元禄初期には下賎な食べ方とみられていたようですが、便利さから広まり流行っていったようです。
「ぶっかけ」が、流行ることによって、それまでの汁につけて食べていた「蕎麦切り」は「もり」と呼んで区別されるようになったようです。また「ぶっかけ」は「かけ」と略して呼ばれるようになったということです。
「ざるそば」ができたから「もり」という名称が生まれたのか、「ぶっかけ」ができたから「もり」になったのかはあいまいです。
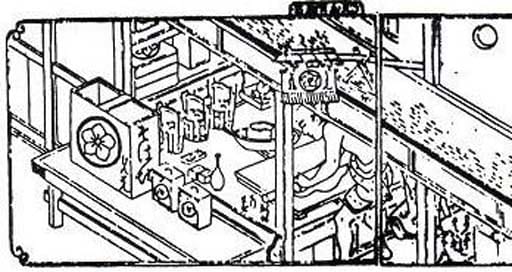 1773年(安永2年)の『俳流器の水』初編に「お二かいハぶっかけ二ツもり一ツ」の句が見えるので、既にこの時代には一般に使われていたようです。
1773年(安永2年)の『俳流器の水』初編に「お二かいハぶっかけ二ツもり一ツ」の句が見えるので、既にこの時代には一般に使われていたようです。
その後、独立したそば屋が出来たり、小麦をつなぎに使う蕎麦が登場したりして、蒸した蕎麦はすたれましたが蒸籠に盛る様式は残りました。おそらく、その時水切りの役に立つ事が「蒸籠」を生き残らせたのでしょう。
 「蒸籠に盛る蕎麦を盛りといひ、盛蕎麦の下略なり」と、喜田川守貞著、起稿は1837年(天保8年)の『守貞漫稿』あるが、「高く盛りあげるからもり」とも言われる。
「蒸籠に盛る蕎麦を盛りといひ、盛蕎麦の下略なり」と、喜田川守貞著、起稿は1837年(天保8年)の『守貞漫稿』あるが、「高く盛りあげるからもり」とも言われる。
「もり」にもみ海苔をかけて、蒸籠も替えて「ざるそば」として売り出したのは、明治以降のことである。
なお、世間でよく言われている「もり」と「ざる」の違いは、海苔がのっているか、いないかの違いだというのは、誤った俗説です
「ざるそば」は、「もり」とは明確に区別する為、汁もぐんとコクの深いざる汁を用いるのが決まりだった。「ざる汁」とは、普通の「かえし(煮かえし)」にさらに、みりんを混ぜた「御膳がえし」を加えた辛汁のことです。
かえし【返し】
醤油と砂糖を混ぜ合わせたものをいう。これに、味醂を加える場合もある。
醤油を「煮返す」ことからきた言葉といわれている。返しをねかせることで、醤油の角をとり、まろやかにする。また、醤油の劣化を抑えるなどの効果があるとされている。そば店では、一般的に返しにだしを合わせてだし汁を作る。
しかし、近年では、一部の老舗などを別として「ざる汁」を別に作る店は非常に少なくなっており、一般には「もり」と「ざる」の違いはもみ海苔の有無だけになってしまっているようです。
したっけ。



















