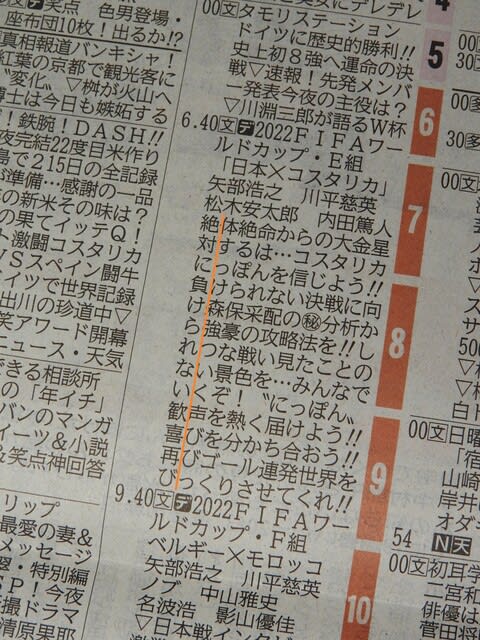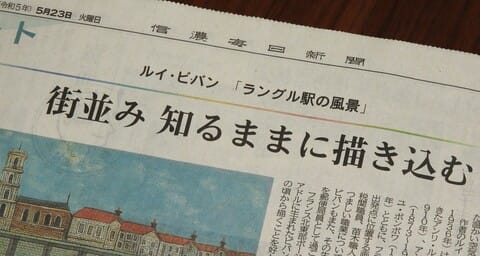
■ ルイ・ビバンという素朴派の画家が5月23日付 信濃毎日新聞の文化面で取り上げられ、「ラングル駅の風景」と「ノートルダム・ド・パリ」という作品と共に紹介されていた。素朴派については独学で絵を学んだ画家、ということくらいしか知らない。素朴派の画家はアンリ・ルソーくらいしか知らず、ビバンの名はこの新聞記事で初めて知った。
記事によるとルイ・ビバンは1861年にフランス東北部のアドルという小村に生まれ、18歳のときに鉄道会社の郵便部局の仕事に就いたそうだ。31歳のとき、パリに出て郵便配達人となったビバンは、仕事の傍ら絵を描いていたという。ビバンは子どものころから絵を描くことが好きだったそうだ。1922年、61歳で郵便局を退職してから絵を描くことに専念、評論家に認められて素朴画家としての道が開けたとのこと。
**「素朴派の画家は、見える通りにではなく、知っている通りに描く」とよく言われます。ビバンは、まさにこの言葉にぴったりとあてはまる画家でしょう。** 遠藤 望さん(下諏訪のハーモ美術館長)は記事にこのように書いている。記事を読んで、この箇所にサイドラインを引いた。
優れた画力、テクニックによって、見える通り、リアルに描かれた絵もすごいとは思う。けれど、理解した通り、把握した通り描かれた絵により強く惹かれる。後者はすごいなぁ、ではなく、いいなぁ。
**風景をなにもリアルに描く必要はない。無い方が好いと思う要素は省略するなどして、風景を魅力的に再構成すること。創造行為とはそういうものだ、と私は思う。** 4月3日、ブログにこのように書いた。過去ログ
ルイ・バランは目の前の風景をそのままリアルに描くのではなく、郵便配達人として熟知している通り描いた。ビバンは生まれ故郷に近いラングル駅をよく知っていて、「ラングル駅の風景」では遠くに立つ塔もその手前の家も近くの駅舎や列車もどれも同じ密度できっちり描き込んでいる。遠近感を表現することには全く無関心かのように。他の作品も同じような描きかたをしているようだ。
「対象を知らなきゃ、アートをする資格がない」 植物写真家・いがり まさしさんのこの言葉をラジオ深夜便で聞いた(5月24日午前4時5分からの「心に花を咲かせて」)。この言葉にアンカーの須磨佳津江さんが「自分の姿勢ということですね」と応じていた。「自然のすばらしさを伝えるために自然のことをよく知る」「正確に知ることとイメージを届けることは矛盾しない」という言葉も印象に残った。
いがりさんは自然のことをよく知って、そのすばらしさを伝えるために写真を撮っている。ルイ・ビバンは仕事を通じて知った街の魅力を伝えるために描いた。アートとはそういうものだろう。
ここで改めてなぜ火の見櫓のある風景をスケッチするのか自問。火の見櫓の立つ風景っていいなぁ、と思うから。そしてその魅力を伝えたいから、と自答。










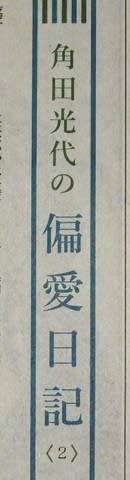

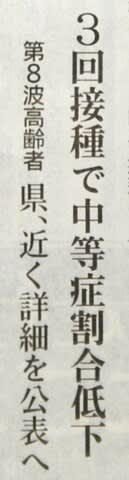
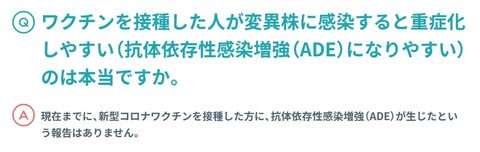
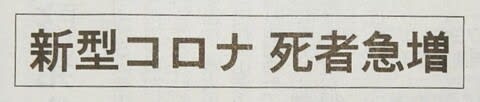

 「店舗でしか味わえない楽しみ」ってこのようなことを指すんだろうな。
「店舗でしか味わえない楽しみ」ってこのようなことを指すんだろうな。
 360
360 サッカーのワールドカップ、明日(12月2日)の早朝、日本はスペインと対戦する。新聞のテレビ欄は深夜の時間帯にスペースを割かないから、ドイツ戦やコスタリカ戦(
サッカーのワールドカップ、明日(12月2日)の早朝、日本はスペインと対戦する。新聞のテレビ欄は深夜の時間帯にスペースを割かないから、ドイツ戦やコスタリカ戦( 360
360