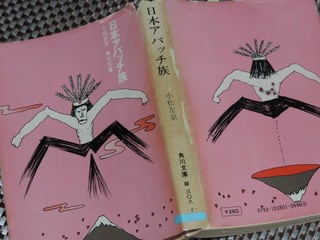■ 電話が無い時代には、直接会うか手紙でしか相手に用件を伝えることができなかった(伝言を頼むこともできたか・・・)。直接会えば相手の様子がよく分かる。少し太ったとか痩せたとか、髪を短くしたとか、白髪が増えたとか、洋服のセンスが変わったとか・・・。
電話では、声の調子などで、相手の様子をある程度知ることができる。弾んだ声で元気そうだとか、元気が無いなとか。でも直接会う場合に比して相手の様子に関する情報は限定的で密度も薄い。
ファクシミリでは手書きの文章だと筆跡から相手が誰なのか分かることが少なくないが、相手の様子は分からない。メールでは相手の様子などの情報は全く伝わらない。
情報伝達手段の変化、これは直接伝達から間接伝達への変化だと言える。この変化に伴って人と人の繋がりが希薄化した。カフェで向い合いながら、共にスマートフォンの画面に見入っていて会話をしない男女。スマートフォンがなければあり得ない光景だ。いや、共に下を向いてマンガを読みふける光景もかつては見られたか・・・。
そしてリアルなつきあいからネット上での仮想的なつきあいに転じていく・・・。
防災の日(11月5日)に鈴鹿市で行われた津波避難訓練の際、寺の梵鐘を叩いて住民に知らせたということを書いた(191225に再掲)。防災無線のスピーカーの音がよく聞こえない住民がいることを考慮しての対応だったようだ。
火の見櫓の半鐘による情報伝達、これは言葉で伝えるわけではないが、直接的な情報伝達だ。一方、防災無線のスピーカーからは言葉で情報が伝えられるが、それは間接的な情報伝達で、どこで誰が伝えているのか分からない。人ではなく、機械というかコンピュータが原稿を読み取って合成音で情報を流す、というような場合は情報伝達者はいない、ということになる。
火の見櫓の半鐘から防災無線のスピーカーへ、この変化は上に書いたような世の中の情報伝達の変化、直接的な伝達から間接的な伝達への変化と重なっている。火の見櫓に替わって防災無線柱が立つ様は人と人との繋がりの希薄化の象徴のように思われて寂しく切ない・・・。

長野県朝日村にて 撮影日120422
「点と線」 過去ログ



 Yちゃんは私が持参した資料にも全く興味を示さなかった・・・。
Yちゃんは私が持参した資料にも全く興味を示さなかった・・・。














 をした。その時に会いたいね、ということに。で、昨日、Y君と
をした。その時に会いたいね、ということに。で、昨日、Y君と で遠路はるばる出かけたのだった。東京からT君もかけつけてきてくれて、4人でプチいとこ会、となった次第。岐阜県内某所のホテルで痛飲した。
で遠路はるばる出かけたのだった。東京からT君もかけつけてきてくれて、4人でプチいとこ会、となった次第。岐阜県内某所のホテルで痛飲した。 、食べて、食べて
、食べて、食べて ・・・。普段はお酒を全く口にしないというYちゃんも生ビールをジョッキで1杯飲んだ。その後ホテルの売店で酒を買い求めて部屋でまた飲むという、よくあるパターンだった。
・・・。普段はお酒を全く口にしないというYちゃんも生ビールをジョッキで1杯飲んだ。その後ホテルの売店で酒を買い求めて部屋でまた飲むという、よくあるパターンだった。